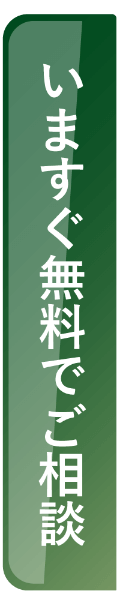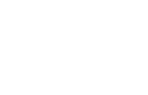相続時精算課税制度とはどんな制度?メリットやデメリット、効果的な使い方などを解説します
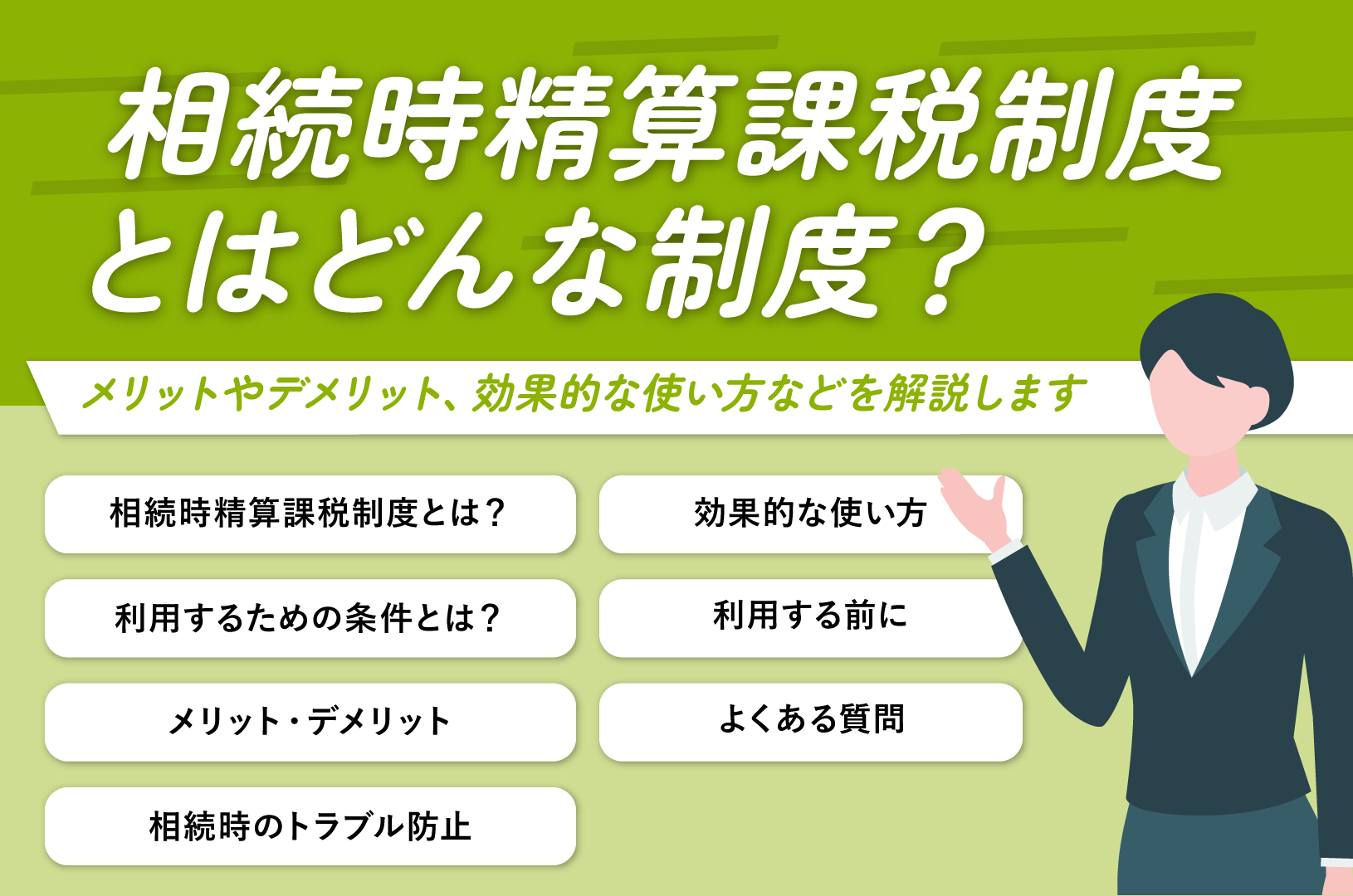
一般的には聞きなれない相続時精算課税制度。相続税が軽減される制度として知られていますが、どのような制度なのかを理解していない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、相続時精算課税制度の基礎知識やメリット、デメリット、有効的な利用方法などを解説していきます。
目次
相続時精算課税制度とは?
これまでに贈与や相続に関して考えたことがない方にとって、相続時精算課税制度はあまり馴染みのない言葉ではないでしょうか。
相続時精算課税制度を簡単に説明すると、生前贈与をおこなう場合に2,500万円までは贈与税が非課税になる一方、相続が開始された際には相続財産に生前贈与した財産を加算した上で、相続税を課税する制度です。
本制度が作られた目的は、高齢世代から若い次世代に財産をスムーズに移転させることで経済を活性化させることと言われています。
相続時精算課税制度を利用することで2,500万円までは贈与税が非課税となることは、受贈者にとって優位に働くことになります。しかし、最終的には相続時に生前贈与した財産も加算されて相続税が課税される点には注意が必要です。
つまり、相続時精算課税制度は税金を支払うタイミングを、相続開始時に先送りにしているとも言えます。
しかし、通常の贈与では非課税となる限度額が年間110万円ですので、2,500万円という大きい額を非課税にできる点は、相続時精算課税制度の大きな特徴であり、メリットだと言えるでしょう。
受贈者にとっては、発生時期が決まっていない相続時に財産を受け取るよりも、子どもの進学や、住宅の取得など大きなライフイベント時にまとまったお金を受け取りたいと考えることもあり得ます。
このようなニーズに応えられるのが、相続時精算課税制度なのです。
相続時精算課税制度を利用するための条件とは?
相続時精算課税制度は制度の趣旨が、高齢の方の資産を早期に子や孫など若い世代にスムーズに移転することですので、基本的には相続を念頭においています。この目的を踏まえて、相続時精算課税制度は適用を受けることができる対象者が決まっています。
贈与者に関しては、贈与した年の1月1日の時点で60歳以上の直系尊属(父母または祖父母)、受贈者に関しては、贈与を受けた年の1月1日の時点で18歳以上の直系卑属(子または孫)とされています。令和4年3月31日までに贈与を行った場合は、20歳以上の子または孫となるので注意が必要です。
さらに、相続時精算課税制度を利用した場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に必要な書類を揃え、贈与税の申告をおこなう必要があります。必要な書類は以下の通りです。
- 贈与税の申告書
- 相続時精算課税選択届出書
- 贈与者の戸籍謄本または戸籍抄本
- 受贈者の戸籍謄本または戸籍抄本
相続時精算課税制度は、贈与者ごとに相続時精算課税制度か暦年贈与をおこなうかを選択できます。
例えば、父母双方から相続時精算課税制度を選択する場合は、5,000万円まで贈与税が非課税となりますし、父母の一方から相続時精算課税制度を、他方からは暦年贈与というように選択が可能なことも覚えておいてください。
また、相続時精算課税制度の利用を選択した場合、選択した翌年以降、贈与者が亡くなるまで継続して適用され、贈与税が非課税となりますが、贈与のたびに贈与税の申告をおこなう必要がある点にも注意しておきましょう。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度のメリットといえば、なんと言っても2,500万円を限度に贈与税が非課税になる点ではないでしょうか。
ここからは、相続時精算課税制度のメリットを節税以外のものも含めて解説していきます。
2,500万円まで非課税での贈与が可能
相続時精算課税制度の大きなメリットとして知られているのが、2,500万円までの贈与が非課税になる点でしょう。
注意しておくべき点があるとすれば、相続時には贈与した財産も相続財産に含めて相続税を計算しますので、相続時には相続税が課税される点です。
つまり、相続時精算課税制度は税金の支払い(ここでは贈与税)を先延ばしができる制度だと考えておきましょう。
暦年贈与をおこなう場合、非課税額は年間110万円以内のため、2,500万円を贈与しようと考えると20年以上かかることになります。相続時精算課税制度はそれを一括でおこなうことができ、その上で贈与税は非課税です。
例えば、贈与者の子どもや孫が事業を始める際にまとまったお金が必要なときや、留学のための資金が必要なときに、2,500万円までの資金を一気に贈与することができます。
相続の場合、被相続人が亡くなって初めて財産を受け取ることができますが、時期は決まっていません。そのため、必要なときに財産を移転させることは不可能です。その点、相続時精算課税制度を利用すれば、必要なときに財産を与えられるので受贈者にとってメリットは大きいと言えるでしょう。
また、贈与者は父母それぞれが相続時精算課税制度を選択できるため、父から2,500万円、母から2,500万円を贈与してもらうことが可能です。つまり、5,000万円まで贈与税を非課税で受け取ることができます。
このように、父母それぞれから贈与を受け、双方ともに相続時精算課税制度を選択した場合には、より多くのお金を贈与税が非課税で受け取れます。
2,500万円は複数年にわたって分割利用可能
相続時精算課税制度を利用する際、次のような誤解をされている方も多いのではないでしょうか。それは、「2,500万円を一括で贈与しなくてはいけない」という誤解です。
相続時精算課税制度は、贈与財産の種類や金額、贈与する回数に制限が設けられていません。つまり、2,500万円の範囲内であれば、どのような不動産をどれくらい、何回贈与しても良いということです。
例えば、祖父から孫へ教育資金1,000万円を相続時精算課税制度を利用して贈与した場合、1,000万円の贈与税は非課税になります。数年後、孫が留学をする際に800万円を贈与した場合の800万円も、贈与税は非課税です。さらに数年後に孫が事業を始めるために、700万円を贈与した際の贈与税も非課税になります。
このように、2,500万円の非課税枠を数年かけ、何回かに分けて贈与をおこなうことも可能なのです。
また、父母また祖父母の双方が相続時精算課税制度を利用する場合には、5,000万円までは非課税になると解説しました。
このような場合に、子どもの住宅購入資金として、相続時精算課税制度を利用して、父親から2,500万円、母親から1,000万円を贈与することも可能です。さらに、母親からは残り1,500万円を贈与する際には贈与税が非課税になります。
相続時精算課税制度は、2,500万円の非課税限度額内であれば、複数年に渡っても、何回に分けても、どのような財産であっても贈与税が非課税で贈与が可能です。
2,500万円を超過した額に対しては一律20%しか課税されない
贈与税は累進課税制度を採用しているため、贈与する金額が大きければ大きいほど、税率が上がっていきます。
例えば暦年贈与を利用し、2,500万円以上の金額を贈与する場合には45%〜55%の贈与税がかかってしまいます。
このような場合、特例税率を利用して計算しますので、暦年贈与を利用して2,500万円贈与した場合の贈与税額は810万円です。
それでは、相続時精算課税制度の利用を選択した場合は、どうなるのでしょうか。
相続時精算課税制度は、2,500万円までは非課税となることは前述の通りです。それでは、2,500万円を超えて贈与した場合はどうでしょうか。
このような場合、贈与税は超過した分の贈与額に一律20%の贈与税がかかります。どれだけ贈与額が2,500万円を超えていたとしても一律20%です。
子どもの住宅購入のための資金として、父親が4,000万円を相続時精算課税制度を利用して贈与を行った場合を考えてみましょう。
まず、相続時精算課税制度を利用しているため、2,500万円には非課税となります。残り1,500万円が贈与税の対象です。贈与税は一律20%ですので、1,500万円×20%となり、この場合の贈与税は300万円となります。
暦年贈与を利用して同様の贈与を行った場合、贈与税は1,530万円となり5倍以上の税額を負担しなくてはなりません。
以上のことからお分かりいただけますように、相続時精算課税制度を利用することによって税額の負担軽減に期待できます。
相続時のトラブル防止
相続の場合、遺言書を残していたとしても、相続人同士で利害が不一致になってしまうとトラブルのもとになる可能性があります。
また、遺言書を残していなかった場合、法定相続人全員による遺産分割協議をおこなう必要があります。
ここでも、相続人同士の意見がまとまらなかった場合には、いつまでも遺産分割協議がまとまらず、相続が終わらないという問題が発生する可能性もあるでしょう。
相続時精算課税制度を利用して生前贈与を行っておけば、上記のようなトラブルを防ぐことが可能です。
生前に贈与者の意思で財産を与えることができるので、相続人となる人への説明ができ、贈与に関して納得してもらうこともできます。
例えば、贈与者が現金のほかに賃貸マンションなどの不動産を所有していたり、事業を行っている場合を考えてみましょう。
贈与者には、賃貸マンションを受け継いでもらいたい特定の相続人や、事業を承継してもらいたい特定の相続人がいたとします。相続時精算課税制度を利用すれば、これらの資産を望み通りの人物にスムーズに移動させることが可能です。
しかし、生前贈与を行わずに亡くなってしまうと、相続人同士が集まって遺産分割協議をおこなうことになります。
このような場合、賃貸マンションを受け継いでもらいたいと考えていた相続人と、事業を承継してもらいたいと考えていた相続人が、逆の結果を求めてトラブルになってしまう可能性がないとは言い切れません。
特定の財産を、特定の誰かに確実に受け継いでもらいたいと考えている場合、相続時精算課税制度を利用して、相続開始時にトラブルになることを回避することが可能です。
相続時精算課税制度のデメリット
2,500万円もの金額を非課税で贈与できる相続時精算課税制度は、さまざまなメリットがあることをご理解いただけたのではないでしょうか。
それでは、相続時精算課税制度にはデメリットはないのでしょうか?メリットが存在する限り、デメリットももちろん存在します。
ここからは、相続時精算課税制度のデメリットを解説します。
相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与が利用できなくなる
相続時精算課税制度を利用するデメリットとして、暦年贈与との兼ね合いが問題となります。
相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与が利用できなくなるのが大きなデメリットです。暦年贈与に関しては、一生使えなくなりますので注意が必要になります。
例えば、相続時精算課税制度を利用して2,500万円を贈与したとしましょう。その後、100万円を10年間に渡り1,100万円を贈与していた場合、2,500万円には贈与税がかかりませんが、後に贈与した1,100万円は贈与税がかかってしまいます。
これは、相続時精算課税制度を利用したことによって、暦年贈与が利用できなくなった結果です。
このことを忘れていた場合、気が付いたときには相当な額の贈与税を支払わなくてはならなくなりますので注意しておきましょう。
しかし、相続時精算課税制度のデメリットは、同一贈与者からの贈与にだけ適用されます。つまり、そのほかの贈与者からであれば暦年贈与の利用が可能です。
祖父が孫に対して相続時精算課税制度を利用した場合、祖父からの贈与については暦年贈与の利用はできません。しかし、祖母からの贈与については暦年贈与による非課税枠を利用できます。
一括で大きな金額を贈与したいという考え方と、長期に渡ってコツコツと贈与したいという考え方を比較して、どちらのほうが得になるのかをしっかりと吟味する必要があります。
小規模宅地等の特例が利用できなくなる
小規模宅地等の特例をご存知でしょうか?本特例は、一定の要件を満たした宅地を相続した際に、評価額を大幅に減額ができる、相続税に対する特例です。
小規模宅地等の特例は、被相続人が居住用または貸付事業用として使用していた宅地を相続した場合に適用される特例で、評価額が居住用の場合には80%貸付事業用の場合には50%減額されます。
不動産の相続税額は大きくなることが多いため、本特例を利用することで、相続税の負担を大幅に軽減可能です。
本特例を利用したいと考えている方は、相続時精算課税制度の利用は慎重に検討しなくてはいけません。
なぜならば、相続時精算課税制度を利用した場合、相続時に小規模宅地等の特例が利用できなくなるからです。
小規模宅地等の特例が適用されるのは、あくまでも相続や遺贈によって取得した土地に限られています。そのため、贈与によって取得した土地に関しては適用されなくなります。
評価額が高い土地を所有している場合、相続時精算課税制度を利用すると高額な相続税を負担しなくてはならないため、贈与税が非課税になるというだけの理由で利用するのはおすすめできません。
その他の税負担が増える可能性がある
上記の通り、相続時精算課税制度を利用して不動産を取得した場合には、相続税の負担が大きくなります。
しかし、贈与によって不動産を取得した場合には相続税の負担が大きくなるだけでなく、その他の税負担が増える可能性があるので注意が必要です。
贈与による不動産取得の際に負担が増える主な税は、「不動産取得税」と「登録免許税」です。
不動産取得税は、読んで字のごとく不動産を取得した場合に課税される税金で、固定資産税評価額等の3%が課されます。例えば、4,000万円の評価額の不動産を所得した場合、不動産取得税は120万円かかることになります。
一方、相続で不動産を取得した場合は、不動産取得税がかかりません。同じ評価額の不動産を相続した場合と比較すると、120万円もの税金を支払う必要が出てきます。
登録免許税は、不動産登記の際にかかる税金で、固定資産税評価額に税率をかけて算出されます。
贈与によって不動産を取得した場合、登録免許税は固定資産税評価額に2%です。先ほどと同様、評価額4,000万円の不動産を取得した場合には、80万円の登録免許税が課税されます。
相続で不動産を所得した場合はどうでしょうか。相続によって取得した場合の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。評価額4,000万円の不動産の場合、16万円の登録免許税が課税されます。
相続で不動産を取得した場合には、贈与で取得した場合よりも登録免許税は64万円も減額されることになります。
不動産を相続時精算課税制度などを利用して贈与する場合には、不動産取得税や登録免許税など、その他の税負担があることを念頭に置いて慎重に検討しましょう。
相続時精算課税制度の効果的な使い方
ここまで見てきたように、相続時精算課税制度は大きなメリットもあれば、デメリットもあります。
そのために、相続時精算課税制度を利用するかどうか迷っている方もおられるでことでしょう。
ここからは、相続時精算課税制度を効果的に利用するケースを解説します。当てはまる方は、ぜひ相続時精算課税制度の利用を検討してみてください。
将来値上がりしそうな株式や不動産を有している場合
将来、値上がりしそうな財産、例えば株式や不動産を所有している方は、相続時精算課税制度を利用して節税ができます。
その理由は、相続時精算課税制度を利用して贈与を行った場合、その財産は贈与時の価値で相続税が計算されるからです。
値上がりしそうな財産とは、再開発計画が持ち上がっている土地や、値上がりが期待される株式などを指します。
つまり、そのような値上がりが期待される財産を、値上がり前に相続時精算課税制度を利用して、価値が低いうちに贈与することで相続税の負担を軽減する効果が得られるのです。
具体例を見てみましょう。ある方が、資産価値1,000万円の土地を所有しており、その土地が再開発地区に指定され、5年後には3,000万円まで資産価値が上がる可能性があったとします。
このような場合、資産価値が1,000万円の時点で相続時精算課税制度を利用すると、相続が開始されたときに贈与時の1,000万円に対して相続税が課税されます。
ところが、5年後に資産価値が3,000万円に上がったときに相続が開始されると、相続税の対象となるのは3,000万円に値上がりした土地です。つまり、相続税の対象となる金額に2,000万円の差が発生します。
上記の例のように、将来的に資産価値が上がりそうな財産を所有している方は、相続時精算課税制度を利用すると相続税の節税が可能です。
不動産などの収益物件を有している場合
賃貸マンションやアパートなど、収益物件を所有している場合にも相続時精算課税制度を利用することで節税を見込めます。
収益物件は、毎月一定額の入金があり、収益分がそのまま相続財産に組み込まれる形になります。
相続税も累進課税制度を採用しているため、毎月の収益がそのまま相続財産に組み込まれるとなれば、年数を重ねるごとに相続財産は増えていき莫大な額になることでしょう。
例えば、毎月200万円の収益があった場合、1年間で2,400万円、10年間になると2億4,000万円もの収益が上がり、それがすべて相続財産になるため相続税も高額になります。
相続税率は取得金額によって10%から55%までと幅広くなっています。もし、2億4,000万円を子1人が相続した場合、納める相続税額は約6,500万円とかなり高額になってしまうのです。
相続時精算課税制度を利用して収益物件を贈与しておけば、収益物件から得られる収益は受贈者の収入になるので、毎月相続財産が積み上がっていくことはありません。ゆえに、相続税の負担額も軽減できるのです。
収益物件を所有している場合には、相続時精算課税制度を利用することで、将来の相続に備えることができます。
相続時精算課税制度を利用する前に
以上のように、相続時精算課税制度は利用の仕方によって税負担の軽減ができます。
しかし、慎重に検討しておかないと思ったような節税効果を得られなかったり、相続税を納める際にトラブルになることがあるので注意が必要です。
ここでは、相続時精算課税制度を利用する前に注意しておくべき点を解説します。
使い方次第では節税にならないこともあるので注意が必要
相続時精算課税制度は、必ず節税効果を得られる制度ではありません。
「これまで、さまざまなメリットや節税効果について解説していたのに何故なの?」と思う方もおられるでしょう。
確かに、相続時精算課税制度は贈与税が控除されます。しかし、相続発生時には、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産と、そのほかの相続財産を合算して相続税を算出します。
算出後の総額が基礎控除額を超えない場合は非課税となりますが、基礎控除額を超えた分は相続税が課税されるので、基本的には、相続時精算課税制度は税金の先送りに過ぎないとも言えるのです。
ただし、相続時精算課税制度は2,500万円もの金額を控除できるため、大きな財産をすぐに移転させたい場合には非常に有用な制度と言えます。
また、贈与時の価格が相続財産の価格となるため、値上がりが期待できる財産を早めに贈与しておくことで節税効果を見込めることもあります。
相続時精算課税制度を利用して節税を考えている方は、専門的な知識が必要になる場合もありますので専門家に相談することがおすすめです。
贈与を受けた財産は、相続時に物納することができない
相続税を納付する際、現金が用意できなかった場合には相続した不動産そのものを納める「物納」という制度があります。
しかし、相続時精算課税制度など、贈与によって取得した財産については「物納」ができません。
これは、贈与についても「物納」を認めるとおかしなことになるためです。
例えば、贈与によって不動産を取得したとしましょう。しかし、贈与税を支払うことができないために、贈与された不動産を物納してしまうと、せっかく贈与された不動産を自分で所有ができないことになってしまいます。
贈与された不動産を自分のものにできないとなれば、贈与を受ける意味がありませんので、おかしなことになってしまうのです。
あくまでも、物納制度が用意されているのは相続で取得した不動産などに限られているので注意してください。
相続時精算課税制度を利用して取得した財産は、相続税の対象になりますので、評価額の高価な不動産を取得した場合には、相続した現金などよりも相続税が高額になる可能性があります。
そのような場合、相続によって不動産を取得していれば物納が可能ですが、贈与によって取得した不動産は物納ができません。
相続時精算課税制度など、生前贈与をおこなう際には相続税のことも念頭に置いて、慎重に検討するようにしましょう。
相続時精算課税制度についてのよくある質問
贈与税と相続時精算課税はどちらが得ですか?
贈与開始の時期によっても異なりますが、一般的に贈与の期間が長いほど贈与税は有利でしょう。毎年110万円という非課税枠しかありませんが、大きな金額を非課税枠で贈与できるからです。逆に、財産が豊かな方が、子や孫へ多額の贈与を希望する場合は、2500万円の非課税枠を使える相続時精算課税制度が有利になる場合もあります。
贈与税110万円がなくなるのはいつからですか?
令和5年の税制改正において、2024年の贈与から年110万円までなら相続税も贈与税もかからなくなりました。 そして、相続時精算課税制度に新たに「年110万円の基礎控除」の枠が加わります。つまり2024年以降、相続時精算課税制度を選択した人でも、年110万円までなら贈与税も相続税もかからないことになります。
まとめ
相続時精算課税制度は、限度額2,500万円もの大きな額について贈与税が非課税になる制度です。
令和5年度の税制改正を受け、暦年贈与とは別に110万円を上限とした非課税枠が創設されました。そこで、110万円未満の贈与財産は持ち戻されないこととなり、贈与税の申告も不要とされます。
さらに、相続時精算課税制度によって贈与を受けた一定の土地または建物について、災害によって被害が発生した場合、相続時に再計算できることになりました。
この改正については、令和6年1月1日以降に行われる贈与について適用されることになります。
相続とは違い、受贈者のライフイベントにあわせて、タイミング良くまとまった金額を援助する際には重宝します。
しかし、利用の仕方によっては思ったような節税効果を得ることができなかったり、相続税の負担が大きくなってしまう可能性もありますので、慎重に検討することが肝心です。
もし、専門的なアドバイスや、相続時精算課税制度の詳細や効果的な利用方法に関して詳しく知りたい方は、ぜひ税理士への依頼を検討してみてください。
サン共同税理士法人では、相続時精算課税制度についてはもちろん、そのほかの生前贈与の方法、さまざまな税務に関するご相談をお受けしています。相続時精算課税制度を利用した生前贈与についての詳しいアドバイスだけでなく、相続税の負担軽減に利用できるそのほかの方法についてもご相談いただけます。
初回無料のオンライン・メール相談にも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。