個人事業主としての事業がうまく起動に乗ったとき、次に考えることとして法人化が挙げられます。さらに事業を拡大することを考えると、会社という形を取ったほうがよいのではないか。そのように考えるのは自然なことでしょう。
しかし、いざ法人化について考えると、いつ実行するのが最適なのか疑問を抱くことが多いのではないでしょうか。
法人化は一見すると手続きが煩雑であり、社会保険料など費用が増える面もあります。しかしその一方で、法人化には信用度の向上や税制上のメリットなど、個人事業主には得られない多くの利点もあります。
本記事では、法人化の意味から始まって、法人化の最適なタイミングやメリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。
目次
法人化(法人成り)とは何か?
法人化とは、個人事業主が法人組織に移り変わることを指します。法人成りとも呼ばれています。これまで個人事業主として事業を行っていた人が会社を設立し、その会社が従来の事業を引き継ぐのが通常のパターンです。
個人事業主であったころの事業形態を、法人化のあとにまったく同じ形で保たなければいけないルールはありません。むしろ法人化をきっかけとして事業拡大を図ったり、新たな事業にチャレンジしたりといった動きは妥当なものだといえるでしょう。法人化したということは、そうするだけの理由があったということです。
法人化することにより、個人事業主であった人物と事業とは別々の存在になります。具体的には、事業の利益と個人の所得が明確に分けられます。個人事業主であった人物(法人化した人物)は、法人の取締役になるなどによって収入を得るのが王道です。
法人化するにあたって知っておくべき3つのこと
法人化するにあたって知っておくべきこととしては、主に以下の3つが挙げられます。
- 役員報酬の額によって法人税が変わる
- 資本金の額によって消費税額や融資額が変わる
- 社会保険に加入する義務が発生する
これらをしっかり理解しておくことによって、今の自分にとって法人化することが妥当なのかが判断できるようになります。以下の解説を読んで一通り把握しておきましょう。
役員報酬の額によって法人税が変わる
法人化すると、役員(いわゆる社長以下の取締役)が受け取る報酬の額によって、法人税の計算が変わります。節税に関わる大切な要素なので、役員報酬の額は妥当なものに設定しておく必要があるといえるでしょう。
具体的には、役員報酬は経費として計上できるため、役員報酬を増やすと法人税を節約できるという関係にあります。しかしその一方で役員報酬は個人の所得であるため、個人事業主であった人物が1人で法人化して役員報酬を受け取る場合、そこに所得税が発生することも考慮しなければいけません。
法人税を節約することを重視したほうがよいのか、個人としての所得税を節税したほうがよいのか、理想のバランスはその法人ごとの経営状態で決まります。一概に判断できるものではありません。
役員報酬をどのくらいに設定することが全体としての税負担軽減につながるのか、しっかりとシミュレーションを重ねておきましょう。
資本金の額によって消費税額や融資額が変わる
法人化する際には、資本金の額をいくらにするかもしっかり決めなければいけません。資本金の額によって、納めるべき消費税の額や融資額が変化するからです。
特に融資額に影響を与えることについては真剣に考慮する必要があるでしょう。一般的に資本金が高い企業は信用力が高いと評価され、銀行などの金融機関からの融資条件が有利になるのが現状です。
融資を受けたいと考えている法人について金融機関が見るのは、返済能力です。「この会社はきちんと借りたお金を返済できるか」が金融機関にとっての最重要項目であり、その判断材料の一つとして資本金が使われます。
現在の法律では資本金の下限は存在しないため、資本金1円でも法人化はできます。しかし実際には資本金1円では融資を受けることは難しく、うまく事業を軌道に乗せることは難しいと考えられます。
無理をしてまで資本金の額を大きく見せる必要はありませんが、事業計画や財務状況に応じて適切な資本金を設定することは大切だといえるでしょう。
社会保険に加入する義務が発生する
法人化すると、厚生年金保険や健康保険といった社会保険に加入する義務が発生します。これによって、会社は健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の半分、そして雇用保険料の一部と労災保険料全額も負担することになります。
個人事業主が1人だけで法人化した場合、個人の保険料と会社の保険料を両方納付することになるため、個人事業主であった頃よりも負担額が増えてしまう点に注意が必要です。
しかしこれらの保険は病気やケガ、老後の生活を保証する重要な制度であるため、長い目で見れば個人のリスクを軽減する性質があります。
法人化するのに最適な3つのタイミング
法人化するのに最適なタイミングとしては、主に以下の3つが挙げられます。
- 個人事業主としての課税所得が900万円を超えたとき
- 売上高が1,000万円を超えたとき
- 事業を拡大したいと考えているとき
いずれも「個人事業主であり続けた場合と比べて、どちらが金銭的に得であるか」を考慮した結果としておすすめできるタイミングです。以下の解説を読んで、具体的な理由をきちんと把握しておきましょう。
個人事業主としての課税所得が900万円を超えたとき
個人事業主としての年間の課税所得が900万円を超えたときは、法人化する適切なタイミングであるといえます。課税所得が900万円を超える頃には、所得税率がかなり高くなっており、法人化して法人税を支払ったほうが節税につながるからです。
個人事業主における所得税は、法人における法人税に相当します。しかし所得税が累進課税の制度をとっているのに対し、法人税は比例税率の制度を取っているという大きな違いがあります。
個人事業主の課税所得が900万円を超えたときの所得税率は33%です。しかし法人税の場合、「課税所得が800万円以下なら15%、800万円超なら23.2%」という2つの基準しかありません。つまり課税所得が900万円のとき、法人税は23.2%であり、所得税率の33%と比べて大幅に低いことになります。
したがってこのくらいの売上を安定的に得られるのであれば、法人化したほうが手元に利益が残りやすいといえるわけです。
売上高が1,000万円を超えたとき
個人事業主としての課税売上高が1,000万円を超えたときも、法人化するよいタイミングであるといえます。個人事業主の課税売上高が1,000万円を超えると、免税事業者から課税事業者となり、売上に含まれる消費税を国に納める義務が発生するからです。
しかし上記と同じタイミングで法人化すると、最大2年間の消費税免除が適用されます。これは簡易課税制度と呼ばれているもので、小規模事業者に対する事業創出の促進を目的としたものです。
ちょうど消費税を支払わなければいけなくなるのと同じタイミングで免除が適用されるので、法人化して間もない時期に資金を確保しやすくなります。何らかのチャレンジをするために法人化をした人にとっては、非常に有利に働くことでしょう。
事業を拡大したいと考えているとき
現在行っている事業を拡大したいという意思があるならば、法人化を検討するタイミングだといえます。なぜなら以下の3つのような理由で、法人化したほうが事業拡大の成功率を高められるからです。
- 法人でなければ契約ができない案件に手を出せる
- 株式発行などによって資金調達がしやすくなる
- 法人でしか活用できない補助金や助成金を利用できる
さらに法人化することによって、事業者としての信頼性が向上し、ビジネスパートナーや顧客からの信頼を勝ち取れるメリットもあります。事業拡大を考えているときには、このことは大変有利に働くことでしょう。
サン共同税理士法人では、法人化のメリット・デメリットに詳しい税理士が多数在籍しています。起業の成功をサポートするので、法人化のタイミングを迷っている方は、ぜひご相談ください。
法人化する5つのメリット
個人事業主が法人化するメリットとしては、主に以下の5つが挙げられます。
- 税制面で有利になる
- 賠償の範囲を制限できる
- 赤字を10年間繰り越せる
- 決算月を任意で決められる
- 社会的信用が得られる
いずれも事業を進めていくにあたっては重要な要素ばかりです。以下の解説を読んで、法人化のもたらす恩恵をきちんと理解しておきましょう。
税制面で有利になる
法人化することで、税制面で有利になる場合があります。これには以下の3つの意味があります。
- 所得税から法人税に移ることで節税できる場合がある
- 役員報酬を損金として扱える
- 役員への退職金を損金として扱える
まず、所得税から法人税に移ることで節税できる場合についてですが、これは課税所得が一定以上の場合に得られるメリットです。所得税が累進課税なのに対し、法人税は一定の税率であるため、課税所得が大きくなればなるほど、法人税の形で税金を納めたほうが節税につながります。
次に役員報酬を損金として扱える場合についてですが、法人は自分自身に対して出す給与(役員報酬)が経費として認められます。給与所得控除の対象となり、そのぶん全体の所得が減るため、支払うべき法人税の額が少なくなる仕組みです。
ただし、役員報酬は給与所得扱いであるため、受け取る個人に対しては所得税が課されます。したがって、会社として支払う法人税と、個人として支払う所得税の合計がもっとも少なくなるように役員報酬を設定することが、節税においては必要不可欠だといえるでしょう。
最後に役員への退職金を損金として扱える場合についてですが、これは原則として損金算入が認められています。役員報酬と同じ扱いであると考えておけばよいでしょう。
賠償の範囲を制限できる
法人化することで、賠償責任の範囲は制限することが可能となるのもメリットの一つです。
法人は独立した法的主体であるため、法人の財産と設立した個人の財産は分離されています。したがって法人が契約違反や違法行為を行った場合でも、原則として個人の財産には一切影響がありません。これにより、ビジネス上のリスクを抑えながら事業を展開することが可能となります。
具体的には、100万円を出資して株式会社を設立した場合、その株式会社が1億円の負債を背負って倒産したとしても、出資者は出資した100万円を失うだけであり、1億円の負債について責任を負う必要は一切ありません。
ただしここで解説した仕組みは、法人のなかでも株式会社と合同会社に限られます。たとえば合名会社の場合は社員全員が無限責任を負うので、会社が多額の負債を背負って倒産した場合、その全てを社員が負担しなければいけません。
赤字を10年間繰り越せる
法人化すると、赤字を10年間繰り越すことが可能となります。これもメリットであるといえるでしょう。
同じような制度は個人事業主にもあります。青色申告制度です。この場合も赤字を翌年以降に繰り越すことは可能となりますが、繰越期間は3年間に限定されています。
一方で法人の場合は繰越控除期間が最初から10年間です。10年間あれば、ある年に大きな赤字が発生した場合、時間をかけてゆっくりと節税につなげることが可能となります。
参考:No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除|国税庁
繰越期間が短いと制度を十分に活用できない可能性があるので、節税の点で法人化するメリットは大きいと考えられます。
決算月を任意で決められる
法人化すると、決算月を自由に設定できます。個人事業主の場合、事業年度は法律によって1月から12月までと定められており、これを変更することはできません。しかし法人は事業年度の決算月を自由に設定できる(会社法や会社計算規則に規定がない)ので、自分の都合に合わせることが可能です。
参考:会社法
参考:会社計算規則
たとえば事業の関係上、12月の繁忙期になることが確実であるとしましょう。一方で6月頃に比較的自由な時間を確保できるとします。この場合には事業年度を7月から6月までと設定することにより、時間のある6月に決算を行うといった工夫が可能となります。
社会的信用が得られる
法人化することで、個人事業主のときよりもはるかに高い社会的信用が得られます。この理由としては、法人化することによって公開する情報が増えるため、事業体としての透明性が増すことなどが挙げられます。また純粋なイメージの問題として、「個人」より「会社」のほうが資金の点や覚悟の点で信頼できるというのもあるでしょう。
世間の事業者のなかには、法人としか取引をしないと決めているところもあります。個人事業主のままでは、そのような事業者とは取引ができません。法人化することで取引先を確保しやすくなり、活動の幅が広がるのは確実です。
金融機関から融資を受ける場合でも、個人事業主では審査が厳しく、多くの場合において保証人が求められます。法人化することで信用が高まり、金融機関や投資家からの資金調達がしやすくなります。
さらに人材を採用する場面においても、個人事業主として募集するよりは法人として募集する方が、優秀な人材を確保しやすいといえるでしょう。
法人化する4つのデメリット
法人化はメリットばかりではありません。どんな物事にも共通することですが、デメリットも存在します。法人化することのデメリットとしては、以下の4つが挙げられます。
- 赤字でも税金を支払わなければならない
- 社会保険に加入しなければならない
- 会計処理や事務手続きなどが増える
- 交際費を損金として扱えないことがある
順番に見ていきましょう。
赤字でも税金を支払わなければならない
法人化すると法人住民税を支払う義務が生じますが、この支払義務は赤字になってしまった場合でも失われません。したがって法人は、赤字の事業年度にも税金を支払う必要があります。
個人事業主の場合は、事業が赤字になってしまった事業年度には所得税や住民税の負担がありません。
住民税について教えてください。所得税とはどう違うのですか?そもそも国税と地方税の違いはなんですか? | 財務省
しかし法人に課される法人住民税は「均等割」と「法人税割」によって構成されています。均等割は法人の規模に応じて納める税額が決定するものです。そのため、たとえ課税所得が0円であっても法人住民税は納税しなければいけません。
法人住民税の税率は自治体によって異なります。たとえば東京の場合、資本金1,000万円以下で従業員が50人以下の小規模法人であれば、7万円の法人住民税が課せられます。
社会保険に加入しなければならない
法人化した場合、自社の従業員全員を社会保険に加入させる義務が発生します。このとき厚生年金などの社会保険料が事業主負担となるため、会社からすれば経済的な負担が増す要素にほかなりません。
これは従業員の人数にかかわらず必須のものであり、個人事業主が自分1人の会社を立ち上げた場合でも、やはり社会保険への加入は必須のものとなります。
ただし国民年金や国民健康保険よりも手厚い補償を受けられる内容となっているので、費用がかかるだけのメリットはあるといえるでしょう。
会計処理や事務手続きなどが増える
法人化すると、会計処理や事務手続きなどの作業量が増えます。税務申告や労働関連の法令遵守、社会保険手続きなど、その内容は多岐に渡ります。
場合によっては専門的な知識も必要になるので、自分だけで行おうとすると時間と労力を大きく奪われることになりかねません。その場合には専門家に依頼するのも選択肢のうちですが、その際には費用が発生します。また事務スタッフの採用を検討する必要もあるでしょう。
法人化する際には、これらのコストも考慮しなければいけません。
交際費を損金として扱えないことがある
法人化した場合、交際費の扱いには注意が必要です。個人事業主では全額経費にできる交際費ですが、法人化すると必ずしも全額経費にできるとは限らなくなります。
具体的には、飲食費のみ50%を経費として認められ、上限は年間800万円と定められています。これは資本金が1億円以下の企業の場合です。
参考:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁
そのため、個人事業主として多額の交際費を使っていた場合、そのままの事業スタイルで法人化すると、経費として計上できない額が多くなってしまう恐れがあります。
法人化する際の手続き
法人化する際の手続きはいささか複雑ですが、ざっくり流れをまとめると以下のようになります。
- 定款の作成
- 資本金の準備
- 法人登記の申請
順番に見ていきましょう。
定款の作成
法人設立のためには、まず定款を作成する必要があります。定款とは法人の基本的なルールを記載したもので、法人の名称・目的・本店の所在地・株式の総数・取締役の数などが明記されていなければいけません。
株式会社を設立する場合、作成した定款は公証人による認証を受ける必要があります。認証には30,000~50,000円の手数料がかかります。合同会社など株式会社以外の会社を設立する場合には、公証人の認証は必要ありません。
また定款には、紙の定款と電子定款の2種類があります。どちらを選んだとしても、定款としての効能に違いはありません。
資本金の準備
次に資本金の準備をします。ここでいう資本金とは、出資者が拠出するお金のことであり、実際に定款に定めた通りの資本金が払い込まれていなければいけません。
資本金の下限は会社法で定められていないので、1円でも会社を立ち上げることは可能です。しかし後々の取引のしやすさや融資の受けやすさを考慮するのであれば、資本金の額はある程度確保しておいたほうがよいでしょう。
資本金は、事業活動を行うための初期費用やリスク対策のための資金として使われます。
法人登記の申請
資本金の準備が整ったら、法人登記の申請を行います。これは法務局に提出するものであり、設立届出書・定款認証証明書・印鑑証明書などが必要です。設立登記のために必要な登録免許税は、立ち上げる会社の種類によって異なります。
設立登記の申請は司法書士に依頼することが多く、その場合には司法書士に対して報酬を支払う必要もあります。
インボイス制度が開始するまでにすべき準備
2023年10月1日から、消費税の納税に関する新たな仕組みであるインボイス制度が始まります。インボイス制度が始まるにあたって、以下のような準備をしておく必要があるでしょう。
- 適格請求書発行事業者になるべきか検討する
- 納税することになる消費税の額を事前にチェックする
一つ一つ解説します。
適格請求書発行事業者になるべきか検討する
インボイス制度とは、仕入れに使った費用に含まれる消費税分を納税する消費税から、控除できる「仕入税額控除」を適用するために、インボイス(適格請求書)を必要とする制度です。
インボイスは仕入先から発行してもらう必要がありますが、仕入れ先がインボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」でなければ、そもそも発行してもらうことができません。
これを仕入先の側から考えると、適格請求書発行事業者でないことで取引先の仕入税額控除に貢献できないことを意味します。これによって取引先を失ってしまうリスクが考えられます。
したがってインボイス制度の導入にあたり、これまで免税事業者として事業を行ってきた人は、課税事業者となって適格請求書発行事業者になるべきか検討する必要があるでしょう。
納税することになる消費税の額を事前にチェックする
これまで免税事業者であった人が、インボイス制度に対応すべく課税事業者となった場合には、新たに消費税を納税する義務が発生します。
資金不足で消費税を納められなくなると、延滞税が加算されるなどのデメリットがあります。具体的にどれくらいの消費税を納めることになるのかを事前にチェックし、きちんと納税できる体制を整えておきましょう。
法人化するタイミングで困ったら税理士に相談しよう
一口に法人化といっても、理想のタイミングは個々のビジネス状況によります。どの程度の規模感で事業を行っているのか、利益は出ているのか、これからのビジネスの展望はどうなのか、などこれらの状況の全てが法人化のタイミングを左右します。
しかし初めて事業を立ち上げた人からすれば、数多くの事例に触れているわけでもないので、なかなか最適なタイミングを見極めるのは難しいでしょう。
法人化するタイミングで困ったときは、ぜひ弊社・サン共同税理士法人までお問い合わせください。
サン共同税理士法人では、初回相談が無料となっています。法人化するタイミングを始め、事業を続けるにあたって発生するあらゆるお悩みに対し、豊富なノウハウに基づいて的確なアドバイスとサポートを提供させていただきます。
法人化するタイミングに関するよくある質問
- 個人事業主から法人化するタイミングは?
- 個人事業主から法人化するタイミングを見計らう判断材料としては、以下のようなものが挙げられます。
- インボイス制度が始まる前(2023年9月30日まで)
- 個人事業主としての課税所得が900万円を超えたとき
- 売上高が1,000万円を超えたとき
- 事業を拡大したいと考えているとき
- 法人化するメリットは?
法人化するメリットとしては、以下の5つが挙げられます。
- 税制面で有利になる
- 賠償の範囲を制限できる
- 赤字を10年間繰り越せる
- 決算月を任意で決められる
- 社会的信用が得られる
まとめ
法人化すべきタイミングについて、一通りのことを解説しました。
法人化する理想のタイミングは、事業の規模や利益、将来像などによって変わります。法人化することで信頼性が向上したり税制上の利点を得られたりなど、さまざまなメリットがあるのは確かです。しかしタイミングを間違えてしまえば、それらのメリットを十分に享受することはできません。
ベストなタイミングを狙いたいのであれば、やはり税制面でのプロフェッショナルである税理士に相談をするとよいでしょう。
法人化はビジネスの成長を加速させる大きなステップです。この記事を参考にして、あなたのビジネスを最適な形で成長させていってください。

税理士登録:2013年
税理士登録番号:123285
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にsankyodo税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。


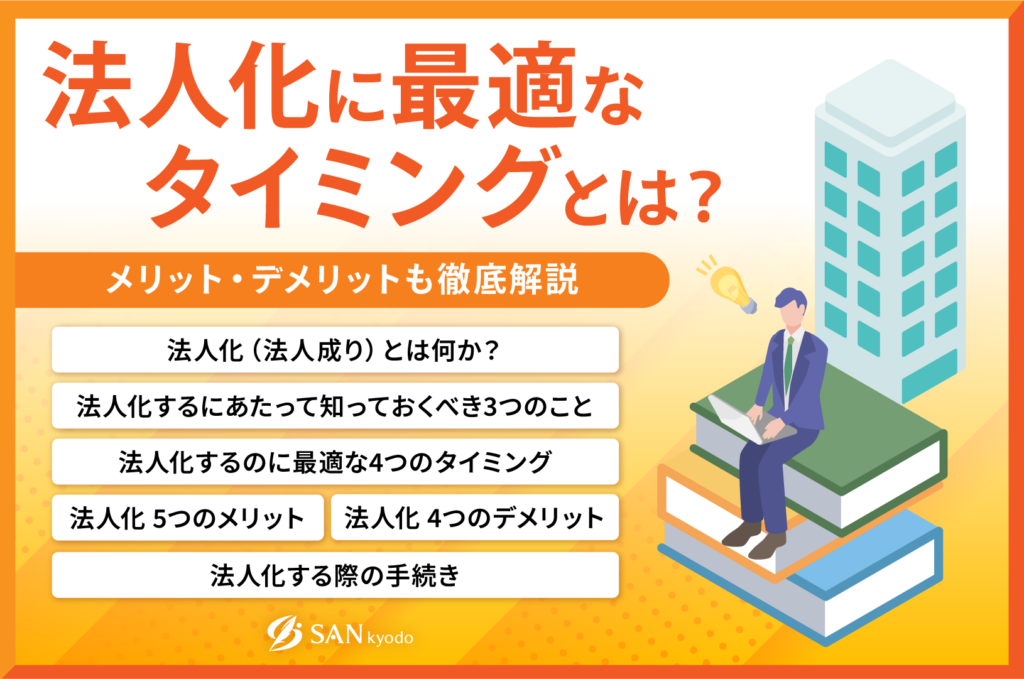
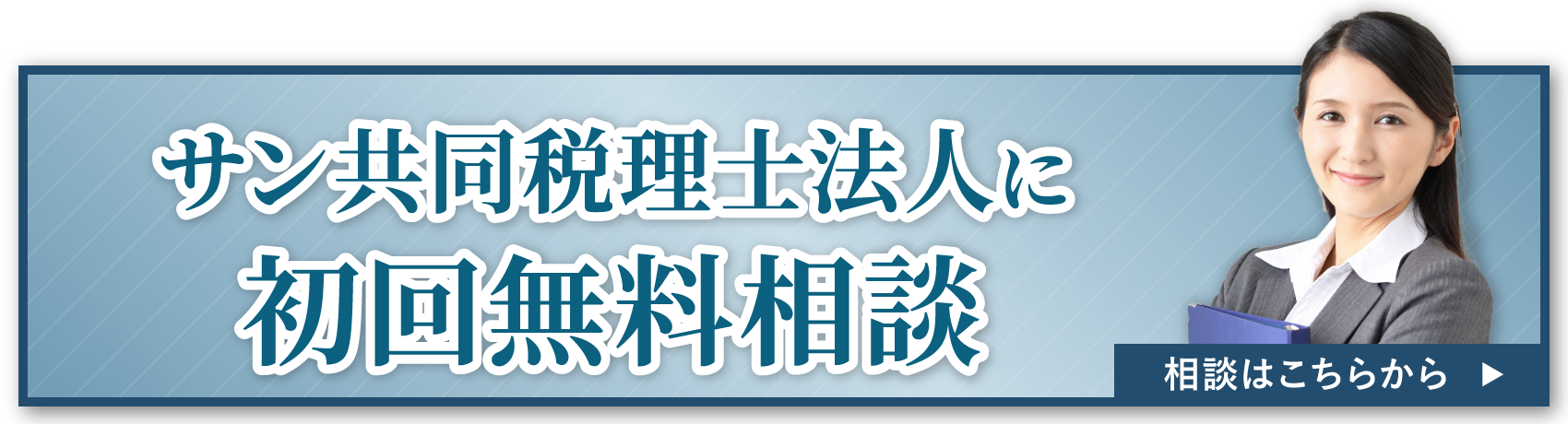


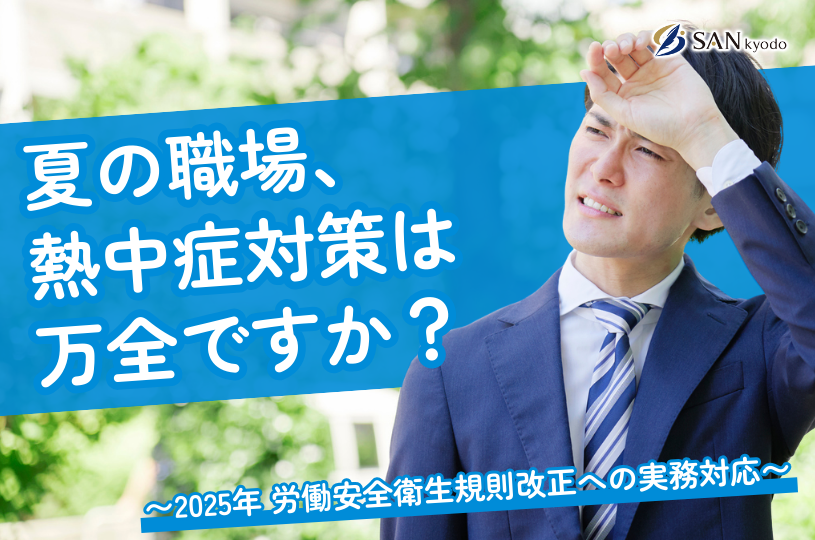
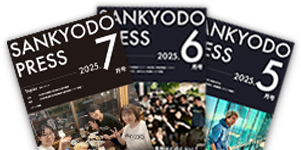
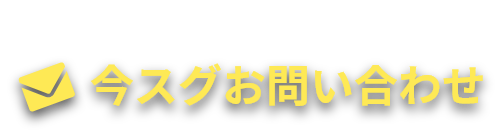

 CLOSE
CLOSE