ビジネスにおける消費税の取り扱いに関する新たな制度として、インボイス制度が始まります。個人事業主やフリーランスから企業に至るまで、新たな体制を整えるためにさまざまな準備が求められています。
インボイス制度は2023年10月から始まりますが、内容が複雑でわかりにくいため、まだ正確に把握できていない方も多いのではないでしょうか。
この記事ではインボイス制度が始まるにあたって必要な準備の内容と、インボイス制度にともなう経過措置の内容について解説します。
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
目次
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除に関して新たにスタートする制度のことです。正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
ここではインボイス制度の主なポイントについて、3つの項目に分けて解説します。
仕入税額控除の仕組み
仕入税額控除とは、消費税の納税額の計算において、売上から受け取った消費税から仕入れの際に支払った消費税を差し引ける制度のことです。
たとえば22,000円(うち消費税2,000円)で仕入れたものを33,000円(うち消費税3,000円)で販売した場合、3,000円から2,000円を控除した残り1,000円が、納税するべき消費税となります。
控除される2,000円は、仕入先の業者が売上に含まれる消費税として国に納めるものです。つまり仕入税額控除がおこなわれないと、二重に消費税を納めることになってしまいます。
仕入税額控除を行うにはインボイスが必要
インボイス制度が導入されると、仕入税額控除を適用するためにインボイスの保存が必要となります。
仕入先からインボイスを入手できない場合、前項で解説した仕入税額控除の仕組みを利用できません。つまり仕入先の業者が収める消費税と重なる部分を、自分も国に対して納めなければいけなくなります。
インボイスを発行するには適格請求書発行事業者になる必要がある
インボイスは事業を行う者すべてが自由に発行できるわけではありません。適格請求書発行事業者として、国に登録する必要があります。
適格請求書発行事業者になるためには、まず課税事業者にならなければいけません。現時点で免税事業者であるフリーランスや個人事業主などは、まず課税事業者となる手続きを済ませ、それから適格請求書発行事業者になるために登録をおこなう必要があります。
インボイス制度は2023年10月から始まる!
ビジネスをおこなうすべての方に影響を与えるインボイス制度は、2023年10月から導入されると決定しています。本記事を執筆している2023年6月の時点で、あと4か月に迫っています。
カウントダウンが始まっている状態ですが、影響の大きさから、今もなお内容に関しては激しい議論が繰り返されています。国はインボイス導入による混乱の緩和措置として、数年間の経過措置をいくつか設けました。
次項では経過措置に関して解説します。
数年間は経過措置が適用される
インボイス制度に関する経過措置としては、主に以下の3つが挙げられます。
- 仕入税額控除の経過措置
- 少額仕入れのインボイス不要
- 納税額の支援措置
順番に見ていきましょう。
仕入税額控除の経過措置(買手側)
インボイス制度は2023年10月から導入されることが決定していますが、開始後すぐに完全な状態で適用されるわけではありません。仕入税額控除に関して、一定の経過措置の適用を受けることができます。
具体的には、インボイスを発行できない事業者から仕入れをおこなった場合にも、インボイス制度導入からしばらくのあいだは、消費税の一部が仕入税額控除の対象となります。
最初の3年間(2026年10月まで)は、課税仕入れの80%が控除可能です。次の3年間(2029年10月まで)は、同じく50%が仕入税額控除の対象となります。
少額仕入れのインボイス不要(買手側)
すべての取引に関して、インボイスがなければ仕入税額控除できないわけではありません。1万円未満の課税仕入れに関しては、インボイスを保存しなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除を適用できます。
この措置の対象となるのは、基準期間(2年前)の課税売上が1億円以下であるか、または1年前の上半期の課税売上が5,000万円以下の中小事業者です。
2029年9月30日までが対象期間となっています。すなわち仕入税額控除の経過措置と同じタイミングで終了します。
納税額の支援措置(売手側)
小規模事業者に向けて、納税額の支援措置も用意されています。
インボイス制度をきっかけとして免税事業者から適格請求書発行事業者となった場合には、売上に係る消費税額から、売上税額の8割を差し引いて納付税額を計算できます。これを「2割特例」と呼びます。
2割特例が適用されるのは、2023年10月から2026年9月までのあいだです。
2割特例の適用にあたっては、消費税の申告を行うたびに、適用を受けるかどうか選択することが可能です。ただし適用期間中に課税売上高が1,000万円を超えた場合には適用できなくなります。インボイス制度がなかったとしても、消費税を納めるべき立場だからです。
経過措置のまとめ
以上のように、インボイス制度の導入にあたっては、緩やかに少しずつ事業者の義務が増していくように設計されています。ここでもう一度、経過措置をまとめてみましょう。
- 2029年9月まで、インボイスがなくても消費税の80%または50%を仕入税額控除が適用できる
- 2029年9月まで、1万円未満の課税仕入れに関してはインボイスなしで仕入税額控除が適用できる
- 小規模事業者は、インボイス制度の導入から最初の3年間は売上に係る消費税額から売上税額の8割を差し引いて納付税額を計算できる(2割特例)
【売り手】請求書を発行する個人事業主や企業が2023年9月までに対応すべきこと
請求書を発行する個人事業主や企業が対応すべきことは、以下の6つです。
- 適格請求書発行事業者になるかどうかを決める
- 適格請求書発行事業者の登録申請をおこなう
- 取引先にインボイスに登録した旨を伝える
- 請求書のフォーマットを変更する
- 税務処理方法を確認する
- 発行したインボイスの保存方法を決める
一つ一つ見ていきましょう。
適格請求書発行事業者になるかどうかを決める
まずは適格請求書発行事業者になるかどうかを決めなければいけません。とくに個人事業主は免税事業者として業務をおこなっているケースも多いので、この決断は資金繰りに大きな影響を及ぼします。
適格請求書発行事業者になるメリットとしては、インボイスを発行できるため取引先が仕入税額控除をしやすくなることが挙げられます。つまり取引先の節税に協力できるということです。
デメリットはその逆で、取引先の節税に協力できないことにより、取引継続を断られてしまったり、値下げを求められたりする可能性があることです。
適格請求書発行事業者の登録申請をおこなう
適格請求書発行事業者になるためには、2023年9月30日までに登録申請をおこなう必要があります。しかし実際には申請したものが認可されるまでに一定の期間がかかるので、登録番号を早く取得したい方は、余裕を持って申請したほうがよいでしょう。
適格請求書発行事業者になるための登録申請の手順は、以下の通りです。
- 「適格請求書発行事業者の登録申請書」税務署に提出し審査を受ける
- 審査のあと「登録通知書」が発行される
免税事業者の場合は、登録申請により適格請求書発行事業者になるとともに、課税事業者の選択を行う必要があることに注意してください。取引先にインボイスに登録した旨を伝える適格請求書発行事業者となったら、取引先に登録した旨を伝えましょう。その際には登録番号を伝えておくと、後々のやりとりがスムーズになります。
また適格請求書発行事業者となったことは、取引しやすい相手としてアピールすることにもつながる可能性があります。すでに解説した通り、インボイスを発行することで取引先の節税に協力できるからです。
請求書のフォーマットを変更する
適格請求書発行事業者となったら、これまで発行していた請求書のフォーマットを、インボイス制度を適用した形式、すなわち適格請求書に変更しましょう。
適格請求書に必要な記載事項は以下のとおりです。
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引の内容(8%軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した取引金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 相手先の氏名又は名称
具体的には、請求する総額だけでなく、含まれる消費税を内訳として記載します。消費税には8%と10%があるので、これらを分割し内税としてきちんと区分します。消費税がどのくらい含まれているかきちんと記載しないと、取引先は仕入税額控除に利用できません。
また適格請求書には、適格請求書発行事業者としての登録番号も記載する必要があります。記載漏れのないよう、しっかりフォーマットを定めておきましょう。
税務処理方法を確認する
適格請求書発行事業者となることで、税務処理はどうしても複雑になってしまいます。消費税の計算を細かくおこなわなければならないからです。
本格的に制度が始まる前に、必要な処理をチェックしておきましょう。
発行したインボイスの保存方法を決める
インボイスは必ずしも紙で発行するものではありません。電子的な方法で発行する電子インボイスも許可されています。
電子帳簿保存法が改正されたことにより、電子的に発行された領収書や請求書は、紙に印刷するのではなく電子データの状態で保管しなければならないルールになりました。そのため電子インボイスをどのように保存しておくのかを、きちんと決めておく必要があります。
なお、電子保存の義務は実質的に猶予されており、2024年1月から対応が必要となり、2023年12月までは紙保存でも良いとされています。
【買い手側】請求書を受ける企業や個人事業主が2023年10月までに対応すべきこと
請求書を受ける企業や個人事業主が対応すべきこととしては、以下の4つが挙げられます。
- 免税事業者への対応を考える
- 取引先のインボイス発行可否と登録番号を確認する
- 受け取ったインボイスの保存方法を決める
- 社内の各部門にインボイス制度を周知する
順番に見ていきましょう。
免税事業者への対応を考える
取引先が免税事業者であった場合、その事業者からの仕入れ費用に関しては仕入税額控除を適用できなくなります。言い換えるなら、余分な消費税を支払わなければいけません。
免税事業者にどう対応するのか、はっきりと決める必要があります。取引をやめて、適格請求書発行事業者と新たに取引をする選択肢もありますし、値引き交渉するという手段もあるでしょう。
ただし一方的に値下げを通告するなどの手段は、独占禁止法や下請法に抵触する可能性があるので慎重な対応が必要となります。
取引先のインボイス発行可否と登録番号を確認する
取引先がインボイスを発行できるのかできないのか、取引を継続するにあたってしっかり確認しておく必要があります。
またインボイスを発行できるとなった場合には、登録番号をあらかじめ聞いておきましょう。インボイスには適格請求書発行事業者としての登録番号の記載が必須であり、番号が正しいか確認できる状態にしておくべきだからです。
受け取ったインボイスの保存方法を決める
受け取ったインボイスをどのように保存するか、具体的な方法も決めておくべきです。
電子帳簿保存法の改正によって、電子データは紙に印刷するのではなく、電子データとして保存しなければいけなくなりました。そのため電子インボイスを受け取った場合にどのように保存しておくのか、制度が導入されるまでにしっかり決めておく必要があります。
社内の各部門にインボイス制度を周知する
社内の各部門に、インボイス制度をしっかり周知させておきましょう。ほとんどの従業員にとっては自分の生活に直接関係ない制度なので、しっかり勉強している割合は少ないのが現実です。
社内でドキュメントを共有するなどして、インボイス制度の具体的な内容と重要性を全員が理解している状態に持っていきましょう。
インボイス制度に関するよくある質問
インボイス制度に関する、よくある質問に回答していきます。
- インボイス制度はいつから始まりますか?
- インボイス制度は2023年10月から始まります。しかし10月1日にすぐ完全な状態でスタートするのではなく、合計6年間の経過措置が設けられています。その間に、新しい制度にしっかり適応していきましょう。
- 2023年10月から適格請求書発行事業者になるにはいつまでに登録申請すべきですか?
- 2023年9月30日までに登録申請すれば、問題なく適格請求書発行事業者になれます。
しかし申請してすぐに登録番号を受け取れるわけではないので、インボイス制度のスタートと同時にインボイスを発行できる状態になるためには、余裕をもった申請が必要となるでしょう。インボイス制度は経過措置があると聞きましたが、いつからどのような影響があるのか知りたいです
インボイス制度の経過措置としては、以下のようなものが挙げられます。- 2029年10月まで、インボイスがなくても消費税の80%または50%を仕入税額控除できる
- 2029年10月まで、1万円未満の課税仕入れに関してはインボイスなしで仕入税額控除できる
小規模事業者は、インボイス制度の導入から最初の3年間は売上に係る消費税額から売上税額の8割を差し引いて納付税額を計算できる(2割特例)
経過措置が続いているあいだに、新たな体制に向けた基盤を作っていきましょう。
まとめ
インボイス制度がいつから始まるのか、具体的にどのような影響があるのかなどについて解説しました。
インボイス制度は内容が複雑であるのと同時に、どう対応するのが適切なのか判断が難しい制度でもあります。とくに現時点で免税事業者である個人事業主やフリーランスは、適格請求書発行事業者になるべきなのか否か、難しい決断を迫られているのが現状です。
ご自身のビジネスにおいて、どのような選択をすべきか判断がつかない場合には、ぜひ弊社・サン共同税理士法人までお問いあわせください。
弊社はこれまでインボイス制度に関してさまざまなご相談に応じてきました。そのノウハウを駆使し、お客様1人1人に寄り添ったアドバイスと、的確なサポートをさせていただきます。

税理士登録:2013年
税理士登録番号:123285
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にsankyodo税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。



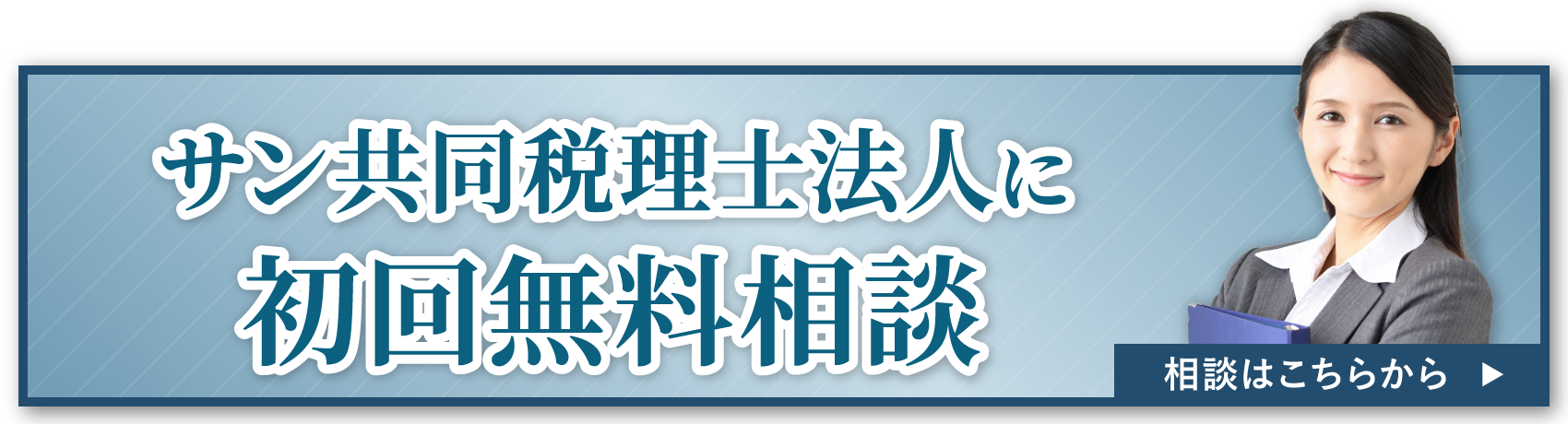


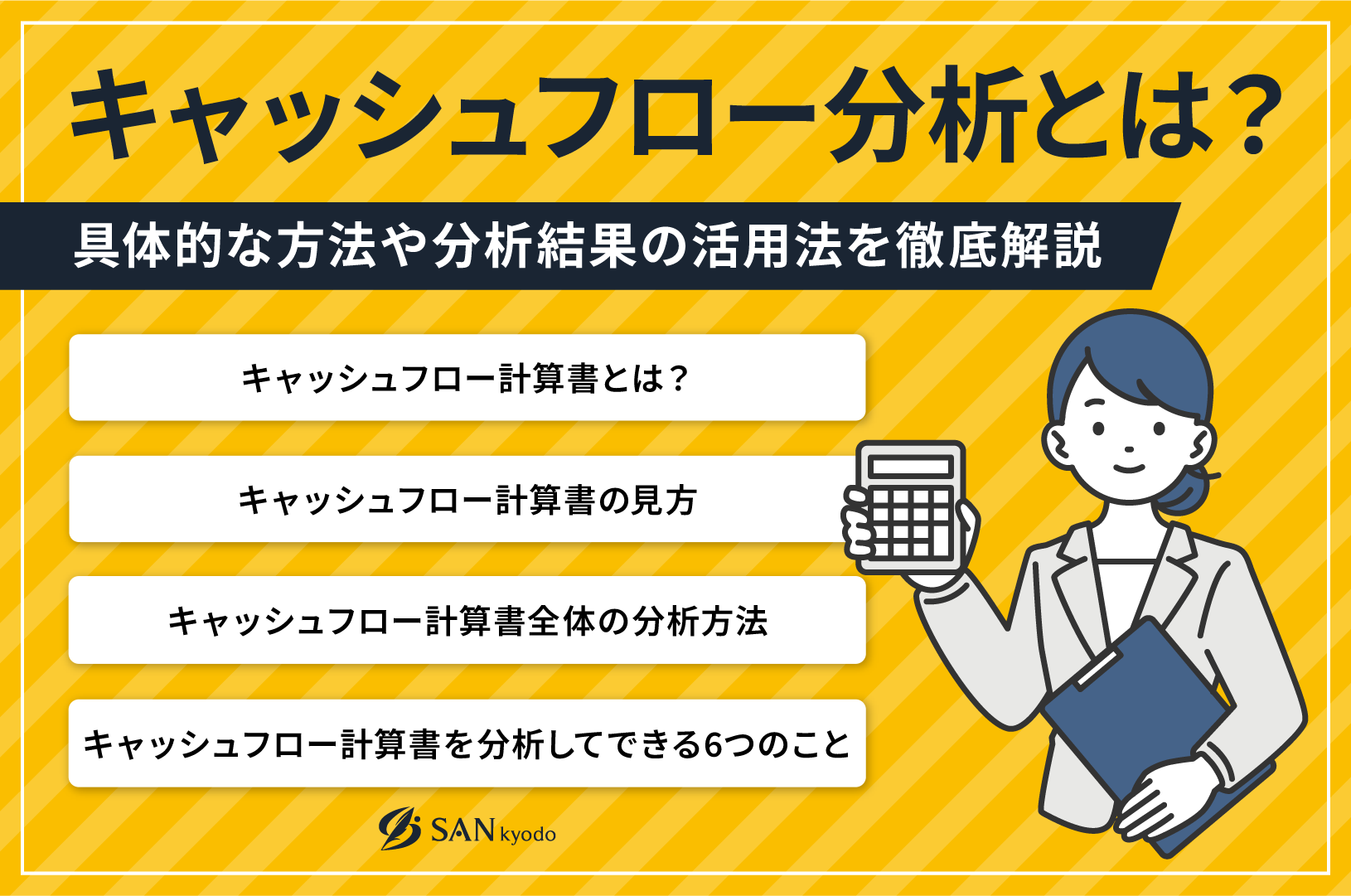
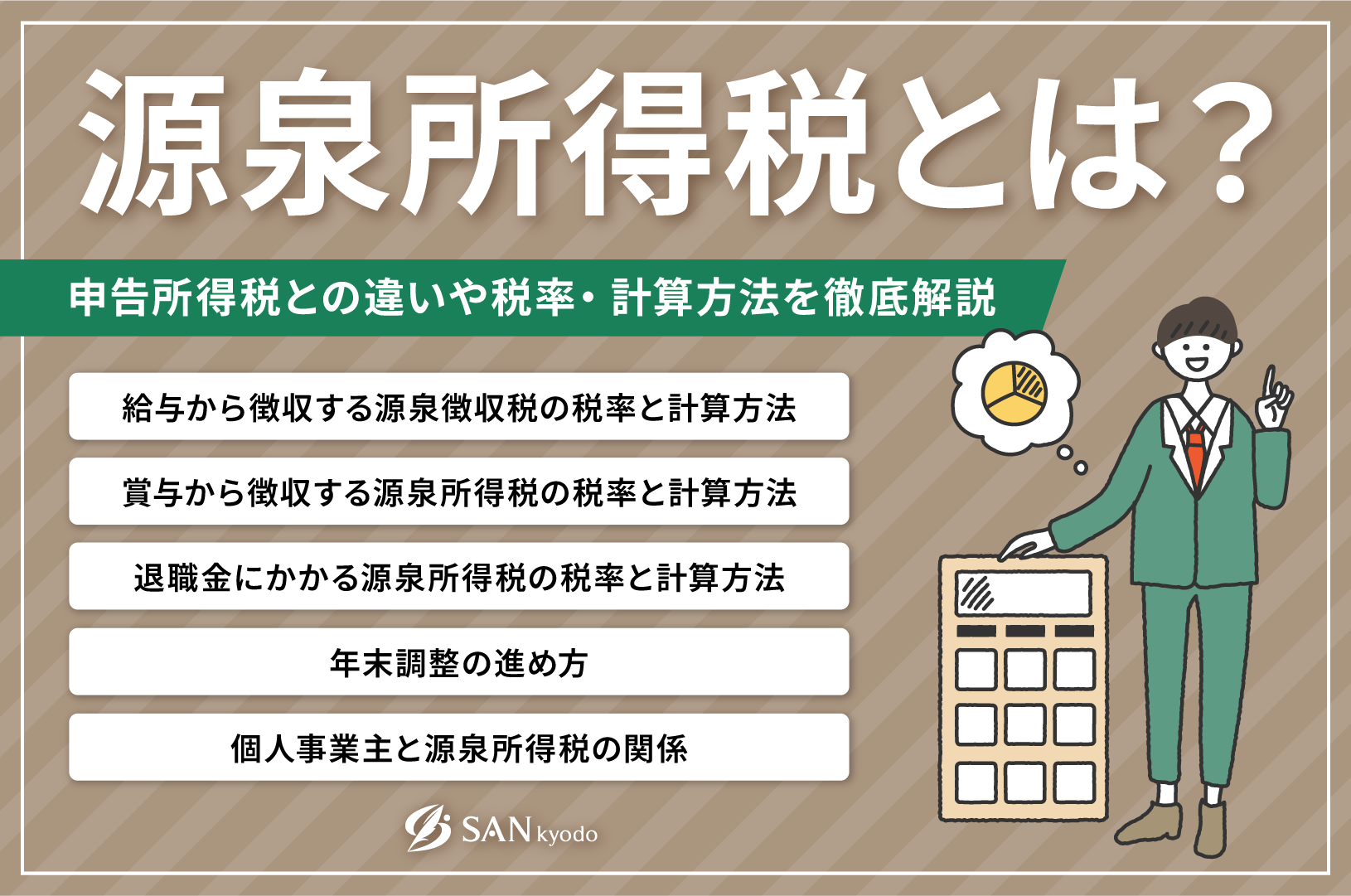
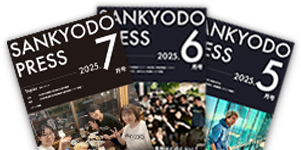
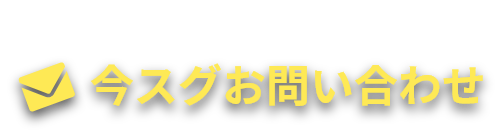

 CLOSE
CLOSE