2023年10月から、消費税の納税に関する新たな制度であるインボイス制度がスタートします。あらゆる事業者に関係のあるものですが、とくに売上高1,000万円以下の個人事業主に、多大な影響を及ぼすものです。
売上高1,000万円以下の個人事業主の多くは、現時点で免税事業者として事業をおこなっています。しかし制度が導入されると、適格請求書発行事業者になることが求められる可能性が高く、課税事業者として活動することを余儀なくされるかもしれません。このことが収入減につながる可能性について、問題視されています。
この記事では、インボイス制度が免税事業者である小規模個人事業主に与える影響と、具体的な対策方法について解説します。
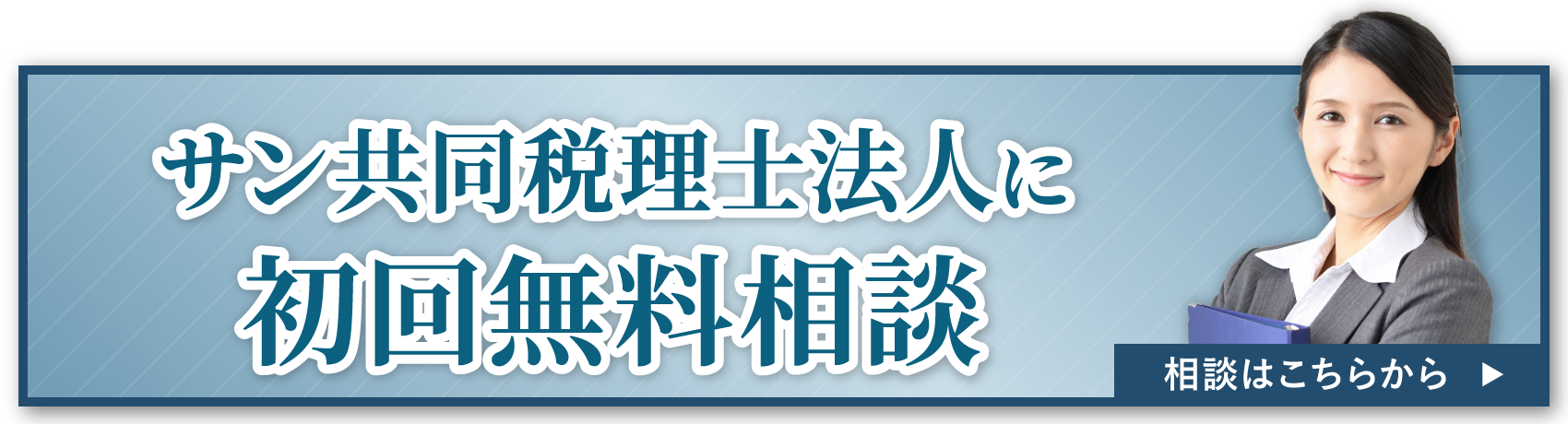
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
目次
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、課税事業者が消費税の仕入税額控除をおこなうときに、仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらう必要があることを定めた、新たな制度のことです。
仕入税額控除とは、売上に含まれる消費税をすべて納税するのではなく、そこから仕入れ費用に含まれる消費税を控除した額を納税すればよいという仕組みを指します。
たとえば仕入先から22,000円(うち消費税2,000円)の仕入れをおこない、それを33,000円(うち消費税3,000円)で顧客に販売したとしましょう。仕入税額控除を適用すれば、3,000円から2,000円を引いた1,000円のみを消費税として納税すればOKになります。
【図解】
控除された2,000円は、仕入先が「自身の売上に含まれる消費税」として国に納税します。つまり仕入税額控除は、国による消費税の二重取りを防ぐための制度であるといえるでしょう。
制度がスタートすると、仕入税額控除ができるのは適格請求書発行事業者のみとなります。
適格請求書発行事業者は課税事業者のみがなれる
インボイスを発行できる適格請求書発行事業者になれるのは、課税事業者のみである点に注意が必要です。
課税事業者とは、売上高に含まれる消費税を国に納税することを義務付けられた事業者を指します。反対の概念は免税事業者です。免税事業者は消費税を納税することなく、自分の収入として計算することが許されています。
免税事業者になれるのは、課税売上高が1,000万円以下の事業者のみです。それ以上の売上を出している事業者は、課税事業者として活動しなければいけません。ただし免税事業者の条件を満たしていても、申請をすれば課税事業者となります。
適格請求書発行事業者になるには登録申請が必要
インボイスを発行できる適格請求書発行事業者となるには、国に対し登録申請が必要となります。現時点で課税事業者であっても、自動的に登録されるわけではありません。
適格請求書発行事業者になるための登録申請の手続きは、以下の通りです。
- 登録申請書を作成する
- 管轄する地域のインボイス登録センターに提出する
- 取引先に登録番号を通知する
登録申請をするには、国税庁のサイトなどから「適格請求書発行事業者の登録申請書」を入手して必要事項を記入します。
申請書の作成が終わったら、管轄する地域のインボイス登録センターに提出します。窓口で渡してもよいですし、郵送でもe-Taxでも受け付けています。
審査を経て、無事に登録番号を取得できたら、取引先に登録番号を通知しましょう。今後発行するインボイスに記載する登録番号が間違っていないかのチェックなどに活用することになります。
インボイス制度に免税事業者の個人事業主が登録しないとどうなる?
インボイス制度が導入されるにもかかわらず、免税事業者である個人事業主が適格請求書発行事業者として登録しないと、以下のようなことが起きると考えられます。
- 取引先が課税事業者(一般課税)の場合は取引先に損失を与える
- 仕事が減る可能性がある
- 値下げ交渉を受ける場合がある
順番に見ていきましょう。
取引先が課税事業者(一般課税)の場合は取引先に損失を与える
取引先が課税事業者である場合、個人事業主が免税事業者であり続けることによって、取引先に損失を与えてしまいます。インボイスを発行できないため、取引先はその個人事業主に対して支払った仕入額等に含まれる消費税を控除できないからです。
たとえば取引先が、免税事業者である個人事業主に対し、110万円(うち消費税10万円)の報酬を支払ったとしましょう。もし個人事業主からインボイスを発行してもらえれば、取引先は仕入税額控除を適用し、支払うべき消費税から10万円分を控除することが可能です。
しかし個人事業主が免税事業者のままだと、上記の控除が適用できないため、単純計算で10万円多く消費税を納税しなければならなくなります。
仕事が減る可能性がある
免税事業者であり続けることによって、仕事が減る可能性があります。インボイスを発行できないため、取引先が仕入税額控除を適用できないからです。取引先としては、より節税に協力してくれる相手と仕事をしたいと考えてもおかしくありません。
免税事業者であることを理由に一方的に仕事を断ることは、独禁法違反に抵触する可能性があります。しかし現実問題として、理由を明かされないまま仕事の発注を減らされるなどの可能性は考えられるでしょう。
値下げ交渉を受ける場合がある
免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先の節税に協力できません。これを理由に、取引先から値下げ交渉をもちかけられる可能性も考慮する必要があります。
前項と同様、「免税事業者だから値下げをしろ」と要求することは独占禁止法違反に抵触する可能性があります。しかし実際には理由を曖昧にしたまま値下げを求められると考えられ、このような行為を独禁法違反であると指摘することはできません。
インボイス制度に対する免税事業者の個人事業主が取りうる対策
免税事業者である個人事業主が、インボイス制度に対して取りうる対策としては、以下のようなものが考えられます。
- 課税事業者となり適格請求書発行事業者の登録を受ける
- 免税事業者のままでいる
- ひとまず免税事業者のままで様子を見る
重大な選択肢となるので、以下の解説をしっかり読んで、どの道を選ぶべきかじっくり検討してみましょう。
課税事業者となり適格請求書発行事業者の登録を受ける
第1の選択肢として、課税事業者となり適格請求書発行事業者の登録を受ける道があります。そうすればインボイスを発行できるようになるため、取引先の節税に協力でき、軋轢が生じることもないでしょう。この点が登録するメリットといえます。
反対にデメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 消費税の納税が必要になる
- 請求書のフォーマットを変更する必要がある
- 税務処理が増える
とくに消費税の納税は大きな負担となって生活にのしかかるので、現実的に考える必要があります。
免税事業者のままでいる
インボイス制度が始まったあとも免税事業者のままでいる、というのも1つの道です。この場合、以下のようなメリットがあります。
- 従来通り、消費税を納税せずに済む
- 従来通りの請求書で事足りる
- 複雑な税務処理をしなくて済む
反対にデメリットとしては、以下のようなものが考えられます。
- 取引先から仕事を発注しにくくなる可能性がある
- 値下げ交渉をされる可能性がある
免税事業者であり続けることは、取引先の税金の負担を増やす行為です。この点がどのように影響するかが、免税事業者のままでいることの是非を決めることになります。
ひとまず免税事業者のままで様子を見る
インボイス制度は2023年10月にスタートしますが、必ずしもそれまでに自分の身の振り方を決めなければいけないわけではありません。2023年10月以降も、適格請求書発行事業者の登録申請をすることは可能だからです。
現時点でどうすべきか判断がつかないのであれば、いったん保留して免税事業者のまま様子をみるのも選択肢のうちでしょう。取引先がそれでよいと言ってくれるのであれば、あえて登録申請する必要はないといえます。
インボイス制度で個人事業主は廃業する?
「インボイス制度が始まると、個人事業主の多くは廃業する」という話を聞いたことはありませんか? それは課税事業者となる必要に迫られる可能性が高く、消費税の納税義務により収入への影響が大きいとされているからです。
しかしインボイス制度には、一定期間の支援措置が設けられています。これらを活用することで、なんとか乗り切れる個人事業主も多いはずです。
具体的な支援措置を見ていきましょう。
免税事業者からの仕入れの一定額を仕入税額控除できる経過措置
インボイス制度がスタートしてからしばらくのあいだは、免税事業者からの仕入れであっても、一定額を仕入税額控除できる経過措置が取られます。つまりインボイスの発行がなくても、仕入税額控除を適用できるということです。
具体的には、開始から最初の3年間(2026年9月まで)は、仕入税額相当額の80%をインボイスなしで控除できます。次の3年間(2029年9月まで)は、同じく仕入税額相当額の50%を控除可能です。
少額取引はインボイス不要で仕入税額控除できる支援措置
前項の経過措置と同じく2029年9月までは、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスがなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能となります。
ただしこの措置の対象となるのは、基準期間(2年前)の課税売上が1億円以下であるか、または1年前の上半期の課税売上が5,000万円以下であるか、どちらかの条件を満たす事業者のみであることに注意してください。
経過措置後も簡易課税制度で納税額を減らせる場合がある
経過措置が過ぎたあとも、簡易課税制度を使って納税額を減らせる可能性があります。
簡易課税制度とは、2年前の課税売上高が5,000万円以下の事業者が受けられる制度です。管轄の税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、簡易課税に基づいた税金を納めればOKになります。
簡易課税制度では、業種ごとに「みなし仕入率」を設定し、課税標準額に対して消費税確認みなし仕入率をかけるだけで仕入税額控除を適用できます。
税額の計算が簡単になるのはもちろんのこと、みなし仕入率の数字によっては納税額を節約できる可能性もあるのが大きなメリットです。
この制度を利用しない場合は、1つ1つの取引についてインボイスを発行してもらい、その詳細に基づいて税金の計算をする必要があります。
売上高1000万円以下の個人事業主のインボイス制度に関するよくある質問
売上高1,000万円以下の個人事業主とインボイスの関係についての、よくある質問に回答します。
- インボイス制度に登録しないとどうなりますか?
- インボイス制度に登録しないと、インボイス(適格請求書)を発行できません。インボイスは取引先にとって、仕入税額控除を適用するために必要なものです。つまり取引先の節税に協力できないことになります。このことによって取引先からの発注が減ったり、値下げを要求されたりする可能性が考えられます。
- インボイス制度に抜け道はありますか?
- インボイス制度に抜け道はありません。インボイスを発行するには適格請求書発行事業者として国に登録する必要があります。登録しなければ、インボイスに記載義務のある「登録番号」を取得できません。また適格請求書発行事業者についての情報は国税庁の用意した公開サイトで調べられるので、虚偽のインボイスを作成しても取引先はすぐに見破れます。参考:国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト
- 白色申告の個人事業主ですが、インボイス制度の影響を受けますか?
- インボイス制度は、青色申告・白色申告にかかわらず個人事業主に影響を及ぼします。制度の本質は「取引先が仕入課税制度を適用できるか否か」であり、自分の税金の申告形式は関係ありません。青色申告であれ白色申告であれ、免税事業者から適格請求書発行事業者になる場合には、新たに消費税の納税が求められます。
- インボイス制度で個人事業主は廃業しますか?
- インボイス制度によって個人事業主に廃業の危機があるといわれている理由は、以下の通りです。
- 免税事業者である個人事業主が、適格請求書発行事業者になることを求められる可能性がある
- 適格請求書発行事業者になれば、新たに消費税の納税義務が発生する
- これにより収入が減少し、廃業のリスクが高まる
たしかに影響は大きいといえますが、本記事で解説した通り経過措置も用意されているので、制度の影響をただちに100%受けるわけではない点も考慮すべきでしょう。参考:国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト
まとめ
インボイス制度が売上1,000万円以下の個人事業主に与える影響について、詳しく解説しました。
売上1,000万円以下の個人事業主の多くは免税事業者であり、現時点では消費税の納税をしていません。しかし制度の導入により、「適格請求書発行事業者にならなければ仕事がもらえない」という圧力を受ける可能性があり、個人事業主を悩ませています。
適格請求書事業者になるべきか否かの判断は難しいものであり、自分1人で悩んでいると袋小路に入り込んでしまう危険があります。
インボイス制度にともなう身の振り方についてのお悩みは、ぜひ弊社・サン共同税理士法人までご相談ください。
サン共同税理士法人では、インボイス制度の導入に関する個人事業主様のお悩みを、多数受け付けてまいりました。豊富なノウハウの蓄積があるので、個人事業主様1人1人にあわせた適切なアドバイスとサポートをご提供できる用意があります。
ご自身が本来全力を尽くすべき事業内容に専念するためにも、インボイス制度のお悩みはぜひ弊社に解決させていただきたく存じます。

税理士登録:2013年
税理士登録番号:123285
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にsankyodo税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。


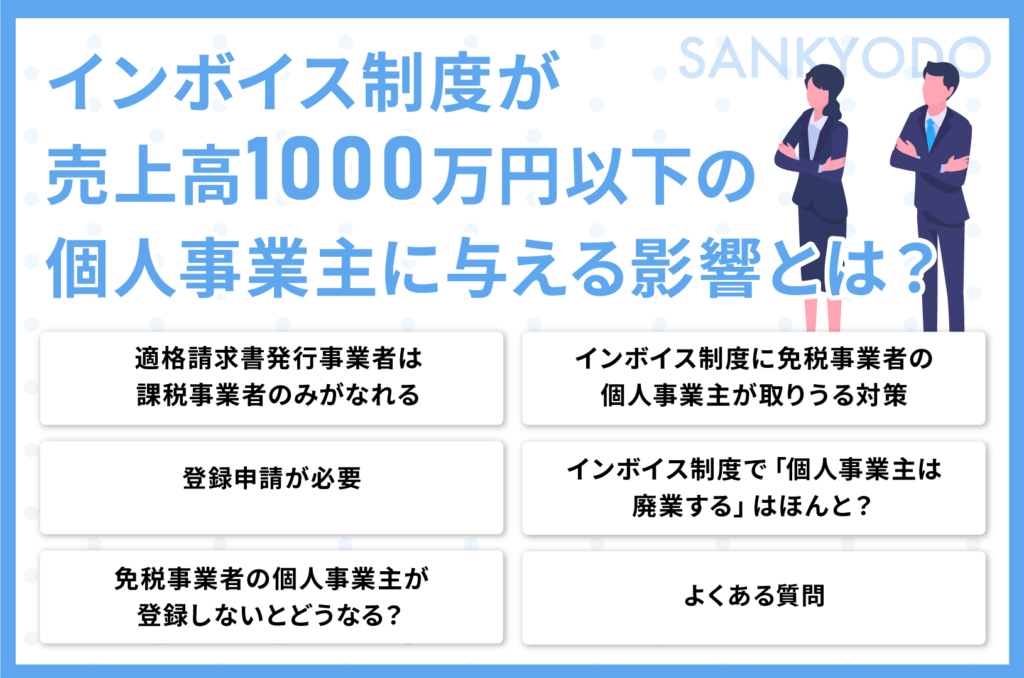


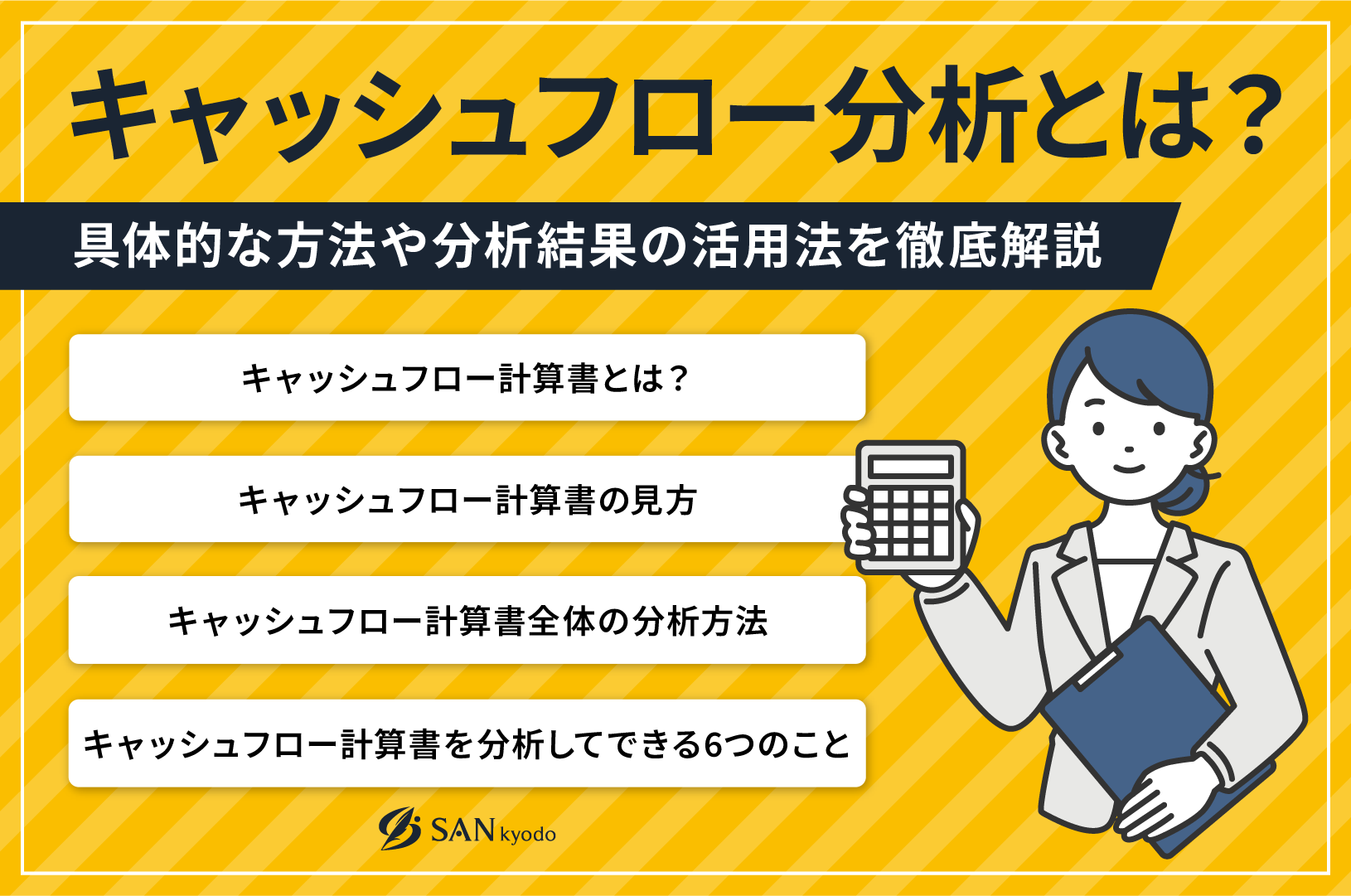
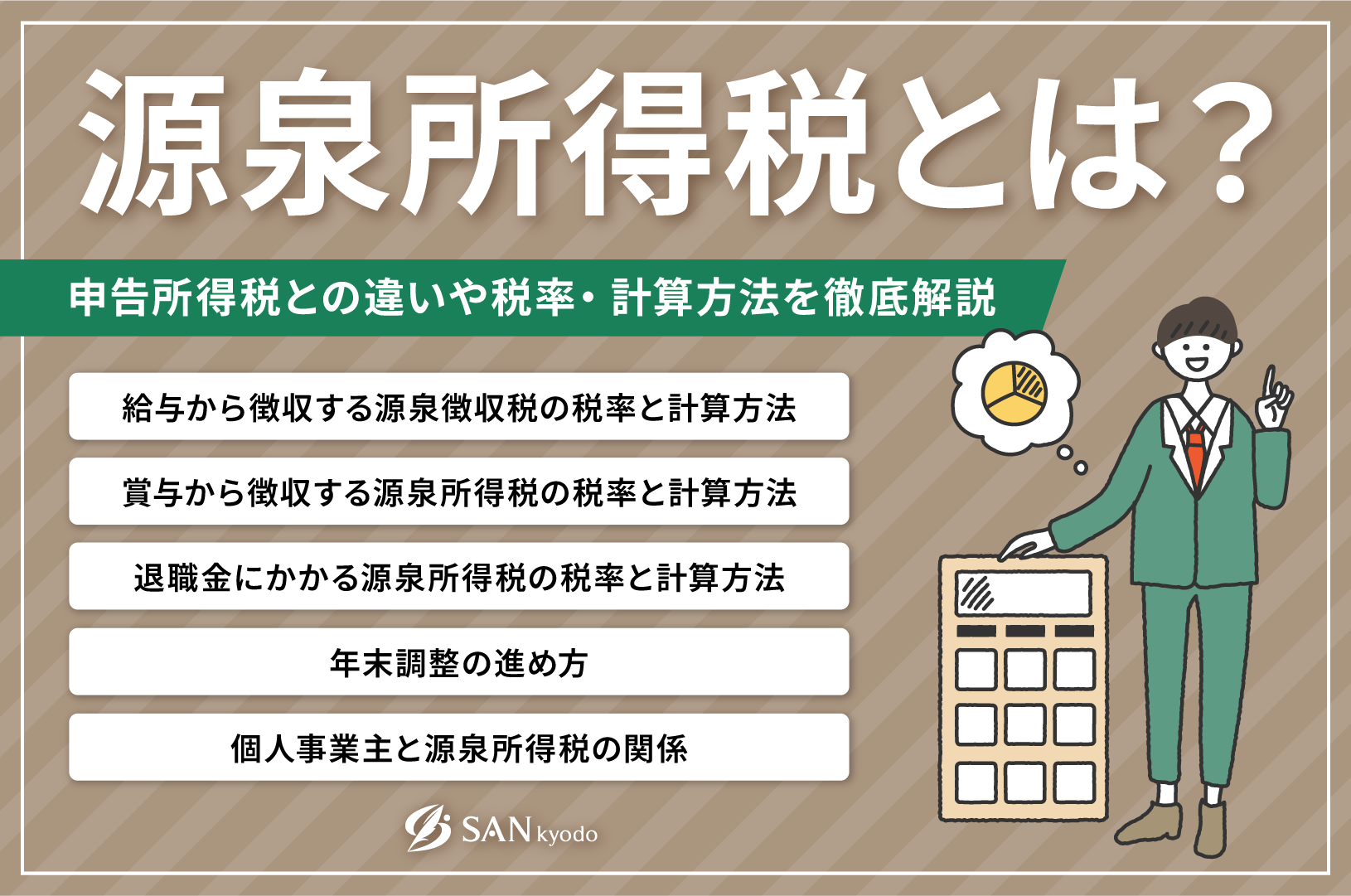
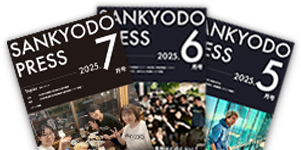
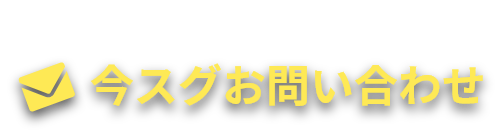

 CLOSE
CLOSE