副業が日本でも一般化してきた今日、多くの人々が何らかの形で副業をしています。通常、副業は本業に対する補完的な収入源とされ、少額であれば、煩雑な手続きをすることなく楽しんで行えるものです。
しかし、副業で稼いだ所得が20万円を超えると、税務上の手続きが必要になります。またその際に、年末調整と確定申告がどう関わるのか、どちらを行えばよいのかといった疑問が浮かぶこともあるでしょう。
年末調整や確定申告について、きちんとした知識を持たないまま手続きをすると、何らかのミスにより税務上のペナルティが課せられる恐れもあります。一連のリスクを避け、確実に手続きを行うためには何をすべきなのでしょうか。
本記事では、副業で20万円超稼いだ場合の年末調整と確定申告に関する知識を、一通り解説します。
目次
年末調整とは?
年末調整とは、1年間の所得に対して支払うべき税金と、すでに支払った税金との差額を調整する手続きのことです。基本的に12月に会社が行います。
年末調整を受けることで、毎月引かれていた源泉徴収の過払いや不足分を精算することが可能です。源泉徴収はあくまで目安であり、年末調整によって正確な数値に直されることになります。
年末調整においてチェックするのは、その年の1月1日から12月31日までに支払われた給与所得や所得税、各種控除額などです。源泉徴収した所得税額との違いを割り出し、過払いがあれば還付され、不足があれば追加で徴収されることになります。
年末調整は所得税に関してだけでなく、生命保険控除や扶養控除をはじめとした各種控除も清算の範囲内です。しかし医療費控除や初年度の住宅ローン控除といった手続きには対応していないため、場合によっては別個に確定申告が必要となります。
年末調整の対象になる人・ならない人
年末調整の対象になる人とならない人は、条件によって比較的明確に区分可能です。具体的には、以下の表のようになります。
【年末調整の対象になる人】
- 1年間を通じて勤務していた人
- 1年の途中で就職し、年末まで勤務した人
- 1年の途中で退職した人のうち、以下の条件に該当する人
- 死亡により退職した人
- 著しい心身の障害で退職し、その年のうちの再就職が見込めない人
- 12月中に支払われる給与を受けたあとに退職した人
- パートやアルバイトとして勤務していた人が退職し、その年に受け取る給与の総額が103万円以下の人
- 1年の途中で、海外へ転勤などの理由により非居住者となった人
【年末調整の対象にならない人】
- 1年間の給与所得が2,000万円を超える人
- 災害の被害を受け「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」により、その年の源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた人
- 2箇所以上から給与の支払いを受けていて、他の雇用主のもとで年末調整を受ける人
- 1年の途中で退職し、その年のうちに再就職が見込まれる人
- 日本国内に住んでいない人
- 継続して同じ雇用主に雇用されていない人
参考:年末調整の仕方|国税庁
副業をしていても年末調整は1ヶ所で行う
副業をしている場合の年末調整で注意しなければならないのは、たとえ副業で収入があったとしても、年末調整自体は主たる勤務先でのみ行われることです。
年末調整を受けるためには、原則として自分を雇用している企業に対し「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなければいけません。しかしこの申告書は1人1枚までしか提出できないため、年末調整は1企業からしか受けられないことになります。
主な勤務先で行われる年末調整は、その勤務先で得られた給与に基づいた税金の清算が行われるものです。副業の収入については、年末調整において考慮されるケースはほとんどありません。したがって、副業の所得が20万円を超えている場合には、確定申告を通じて自ら税金の処理をしなければならなくなります。
副業の収入については確定申告をする
副業で収入を得ており、所得が20万円を超えた場合には、確定申告を行わなければならないという法的な義務があります。確定申告は例年2月16日から3月15日までに行うことが求められ、期間内に税務署やオンラインで手続きを行わなければいけません。
通常、主な勤務先での源泉徴収や年末調整には、副業で稼いだお金の存在は一切含まれません。したがって、副業で得た所得についてはすべて自分で申告することが必要です。副業をしている場合、確定申告を通して初めて自らに課される正確な税金の額が明らかになります。
確定申告を怠ったり、過少申告をしたりした場合には、申告加算税や延滞税などのペナルティが課されることになるでしょう。さらに、故意に情報を隠していた場合には刑事罰も課される可能性があるので、確定申告は正確に済ませることが不可欠です。
確定申告をきちんと行えるか不安な人は、税理士など専門家に相談してみましょう。弊社・サン共同税理士法人でも、副業を行っている人の確定申告について、常にご相談を承っております。
副業と確定申告の関係
副業をしている場合、確定申告が必要かどうかは多くの人が気にする点です。ここでは副業と確定申告の関係について、以下の4つの項目に分けて解説します。
- 副業の所得が20万円を超えたら確定申告が必要
- 会社員が副業をしていて確定申告が必要になるケース
- 副業の所得が20万円を超えた場合、確定申告をしないとペナルティを受ける
- 確定申告には青色申告と白色申告の2種類がある
いずれも重要なものばかりなので、以下の解説を読んできちんと把握しておきましょう。
副業の所得が20万円を超えたら確定申告が必要
まず明確にしておくべきなのは、確定申告が必要になるのは副業の「所得」が20万円を超えた場合です。これは「収入」ではありません。
収入とは、副業などで得た全額のことを指します。一方で所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。たとえば副業で30万円の収入があったとして、10万円の経費が発生した場合、所得は20万円となります。この場合には確定申告の必要はありません。しかし、所得が20万円を1円でも超えた瞬間に、確定申告が必須となります。
必要経費とは、副業を行うために必要な費用のことであり、交通費や備品の購入費、ソフトウェアのライセンス料などです。一連の経費を差し引いたあとに20万円を超える所得が残っていれば、確定申告が必要となります。
確定申告は所得税だけでなく住民税の計算にも影響を与えるため、適切な手続きを怠らないようにしましょう。
会社員が副業をしていて確定申告が必要になるケース
会社員が副業をしている場合、確定申告が必要になるケースはいくつかあります。最も一般的なのは、前項で解説した、副業所得が20万円を超えるケースです。しかしこの他にも、特定の条件下で確定申告が必要とされる場面が存在します。
第一に、本業の給与所得が2,000万円を超えた場合、確定申告が必要となります。高額の所得であるため所得税の計算を厳密に行う必要があり、確定申告で正確な税金の算出をするべきであると考えられているからです。
第二に、2ヶ所以上から給与を受けていて、合計収入が一定の水準を超える場合も確定申告が求められます。源泉徴収がそれぞれの会社で別個に行われているため、正しい数値をはじき出すためには改めて計算をする必要があるからです。
副業の所得が20万円を超えた場合、確定申告をしないとペナルティを受ける
副業で20万円を超える所得があるにもかかわらず確定申告を怠ると、重いペナルティが課される恐れがあります。具体的には、申告加算税や延滞税といった追加の税金です。金銭的な負担が大きくなってしまうため、可能な限り避けるべきであるのはいうまでもありません。
さらに、確定申告を故意に怠ると、脱税とみなされる場合もあります。このような行為が発覚した場合、法的にも厳しく取り締まられ、最悪の場合は刑事罰を下されてしまうかもしれません。
副業の所得が20万円を超える場合には、確定申告を適切に行うことが非常に重要です。法的な問題を避けるだけでなく、適切な税金を納めることで社会全体の公平性が保たれます。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類がある
確定申告には、青色申告と白色申告という2種類の申告方法があります。それぞれにメリットとデメリットがあるので、副業するにあたってどちらを選ぶかはとても大切な決断です。
青色申告は、複式簿記という複雑な形式の帳簿をつけている場合に選択できます。青色申告の最大のメリットは、最大65万円の所得税控除を受けられる点です。また経費計上の自由度が高く、副業に関わる多くのコストを経費として計上できるのも見逃せないポイントでしょう。
さらには赤字繰り越しなども可能なので、全体として大きな節税効果が見込めます。
一方で白色申告の最大のメリットは、手続きが簡易的であることです。帳簿付けを行う必要はありますが、青色申告と比べるとそれほど手間がかかりません。しかし白色申告を選んだ場合、控除額が10万円しかないなどのデメリットもあるので、しっかり考慮したうえで選ぶことが推奨されます。
副業の確定申告の方法
確定申告は多くの人にとって煩雑なプロセスかもしれませんが、副業をしている場合にはさらに注意が必要です。ここでは副業の確定申告の方法を、以下のように順を追って解説していきます。
- 副業が給与所得のとき
- 副業が雑所得のとき
- 副業で納める税金
副業が給与所得のとき
副業が給与所得の場合、確定申告書の給与所得の部分に所得額を記載する必要があります。
給与所得とは、雇用関係にある仕事から得られる所得を差し、通常は会社や個人事業主から給与として支払われます。給与所得は年末調整の際に一度清算されるのが一般的です。しかし副業による給与所得は、一般的に年末調整を受けることができません。
副業で得た給与所得が20万円を超える場合、確定申告が必須となります。給与所得が主な収入でない場合も、確定申告書に金額をきちんと記入することが重要です。
また副業で源泉徴収を受けた場合には、源泉徴収票もしっかりと保管しておく必要があるでしょう。確定申告の際に、収入と税額を証明するための重要な書類となるためです。
副業が雑所得のとき
副業が雑所得の場合、確定申告の際は雑所得の欄に所得額を記載する必要があります。雑所得とは、給与所得や事業所得など他の所得カテゴリーに該当しない所得全般のことです。
紙で確定申告を行う際には、雑所得は「公的年金等」「業務」「その他」の3つに分かれます。副業で得た所得は「業務」に当たるため、業務欄に所得額を記載しましょう。
雑所得の場合も給与所得と同じく、20万円を超えるか否かを正確に計算することが必須です。収入から経費を差し引き、結果が20万円を超えているかどうか、厳密にチェックしなければいけません。ミスなく計算し、確定申告書に間違いのない数字を記載しましょう。
副業で納める税金
副業で20万円を超える所得を得た場合には、必ず税金がかかります。副業の税金は本業の収入とは別に考えなければいけません。多くの場合、副業の税金は自らの手で適切に納める責任があります。
副業での税金は大きく分けて所得税と住民税があります。ここではそれぞれについて解説します。
所得税
所得税はその名の通り、年間で得た所得に対してかかる税金です。所得にもいくつかの種類がありますが、副業の場合は主に給与所得や雑所得が該当します。所得の総額から必要な経費を引いた残りが、所得税の対象となる「課税所得」です。
副業の所得が20万円を超えた場合には確定申告が必須となり、所得税を納めなければいけません。所得税の計算は多少複雑で、所得税率は累進的に設定されています。具体的な税率は以下の表の通りです。
| 所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円以上330万円未満 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円以上695万円未満 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円以上900万円未満 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円以上1,800万円未満 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円以上4,000万円未満 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
所得税は1年間の所得に対して一度だけ計算され、確定申告を通じて納められます。副業を始める際には、あとで困らないように所得税について十分に理解しておくことが必須といえるでしょう。
住民税
住民税は、日本に住所を持つすべての人が対象となる地方税です。住民税は市町村が設定した税率に基づいて計算され、所得と住む地域によって金額が変わる場合があります。住民税は所得税とは別に考慮されるものです。確定申告を行った際には住民税も同時に計算されます。
特に注意すべきなのは、所得が20万円以下であっても、住民税は納めなければならないという点です。これは多くの人が誤解している部分で、20万円以下の所得であれば確定申告は不要とされていますが、住民税まで不要になるわけではありません。
住民税を計算する方法には、所得にかかわらず一定額を課税する「均等割」と、課税所得金額に10%を乗じて求める「所得割」の2種類があります。均等割の金額は自治体によって異なりますが、おおよそ5,000円が目安です。
副業で確定申告をする際の3つの注意点
副業で確定申告をする際の注意点としては、主に以下の3つが挙げられます。
- 副業で経費の計上ができる場合もある
- 副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は必要である
- 副業をする場合には会社に相談する
順番に見ていきましょう。
副業で経費の計上ができる場合もある
副業においても、経費として計上できる項目が存在する場合があります。経費とは、所得を得るために必要な出費のことを指し、正確に計上することで課税所得を減らすことが可能です。
たとえば副業でオフィスを借りたり、専用の機器やソフトウェアを購入したりした場合、経費として計上できる可能性があるでしょう。通信費や交通費も、一定の条件下で経費として認められることが多々あります。
ただし経費の形状には一定のルールがあり、必ずしもすべての出費が経費として認められるわけではありません。たとえば家で使っているパソコンを副業にも使用している場合、パソコンの購入費全額を経費として計上することはできません。パソコンをどれくらい仕事に使っているかという割合を計算し、按分する必要があります。
副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は必要である
副業データ所得が20万円以下であっても、住民税の申告は必要です。一般的に所得税は20万円以下の所得に対しては非課税ですが、住民税についてはその限りではありません。課税所得がゼロであっても、一定の金額が課税されるケースがあります。
副業で少額の所得しか得ていないからといって住民税について無視すると、ペナルティを課される恐れがあるので、注意しましょう。
住民税は主に市町村に対して支払う税金であり、各自治体の窓口に対して申告を行います。申告する際には、副業の所得が給与所得であれば源泉徴収票、事業所得であれば帳簿や領収書などの書類が必要です。
確定申告をしている場合は、改めて住民税の申告をする必要はありません。
副業をする場合には会社に相談する
副業を始める前に、必ず本業の会社に相談することをおすすめします。法的に副業が認められているとしても、企業によっては内部規定で副業を禁止している場合があるからです。内部規定に違反して副業を行った場合、懲戒解雇などの厳しい措置を取られる恐れもあります。
副業が会社の業務に影響を与えないか、競業に当たらないかといったこともしっかり確認する必要があるでしょう。万が一、会社と競合するような副業をしてしまった場合、重大な違反行為とされ、解雇される可能性も考えられます。
副業を行う場合には、事前に会社の規定を確認し、できれば上司や採用担当部門に相談しましょう。会社の許可を得ておくことによって、後々トラブルに巻き込まれるリスクを減らし、安定して副業を続けられます。
副業と年末調整の関係などでお悩みならサン共同税理士法人へ
副業と年末調整、確定申告には多くの複雑な要素が絡み合っています。
会社員である以上、年末調整は避けられないプロセスです。副業をすることにより、その複雑性はさらに増します。どのような収入がどの税制に該当するのか、何が経費として計上できるのか、いつどのように申告すればよいのかなど。多くの人が頭を悩ませる問題はたくさんあります。
副業や年末調整の関係でお悩みなら、ぜひ弊社・サン共同税理士法人までお問い合わせください。
サン共同税理士法人には、確かな知識と豊富な経験を持つ専門家が多数在籍しております。副業と税金に関するあらゆる問題を解決する準備があり、会社員が副業を始める際の注意点から、確定申告の具体的な方法、ペナルティを避けるための適切な手続きまで、トータルでサポート可能です。
副業で成功するためには、税金の管理をきちんとすることが欠かせません。初回相談は無料となっているので、ぜひお気軽にご利用ください。
副業と年末調整に関するまとめ
副業を行うことで得られる収入は確かに魅力的ですが、税務上の手続きも重要な課題となります。
年末調整は基本的に本業の会社で行われ、副業の収入については自ら確定申告が必要となるケースがほとんどです。所得が20万円を超える場合、確定申告は避けて通れない手続きであり、適切な申告を怠ると申告加算税や延滞税といったペナルティが課される恐れがあります。
副業での経費の計上も可能ですが、認められるためには適切な証明が必要です。また所得税がかからなかったとしても住民税がゼロとは限らないので、この点も注意しなければなりません。
このように副業は、ただ楽しんで働けばよいというものではなく、周辺に考えなければならないことがたくさんある行為でもあります。
本記事を参考にして、トラブルなく副業に励めるよう、知識をアップデートしておきましょう。

税理士登録:2013年
税理士登録番号:123285
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にsankyodo税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。


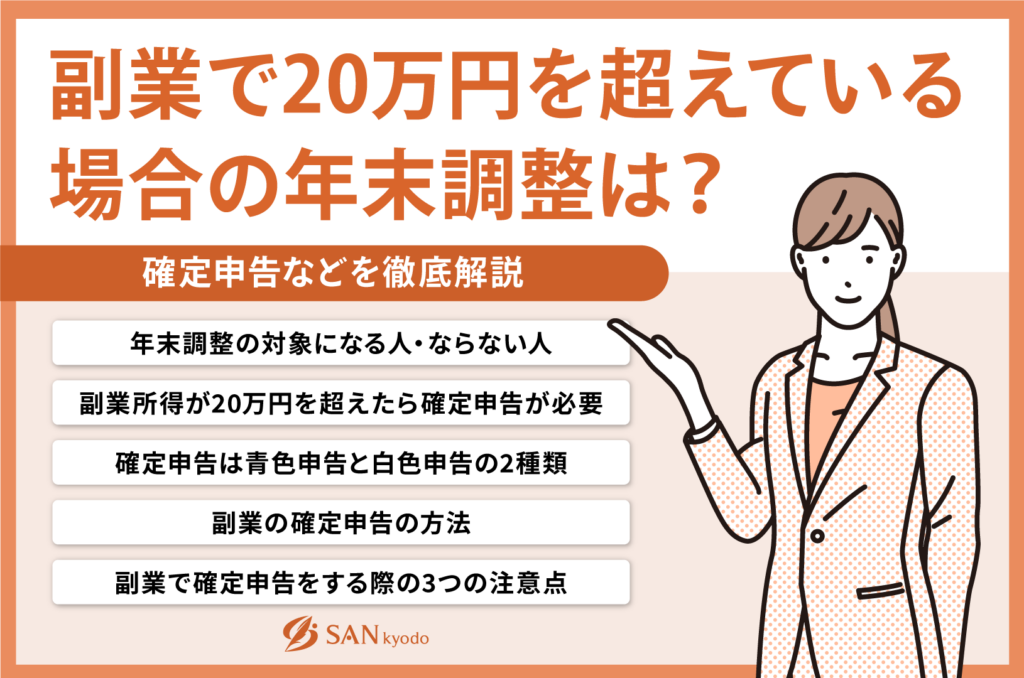
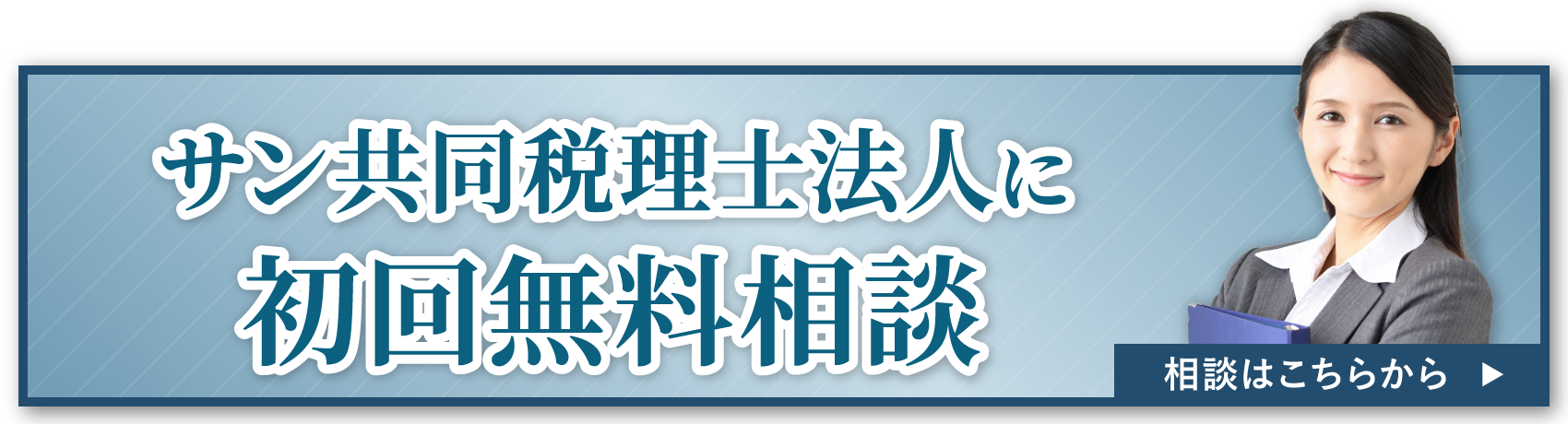

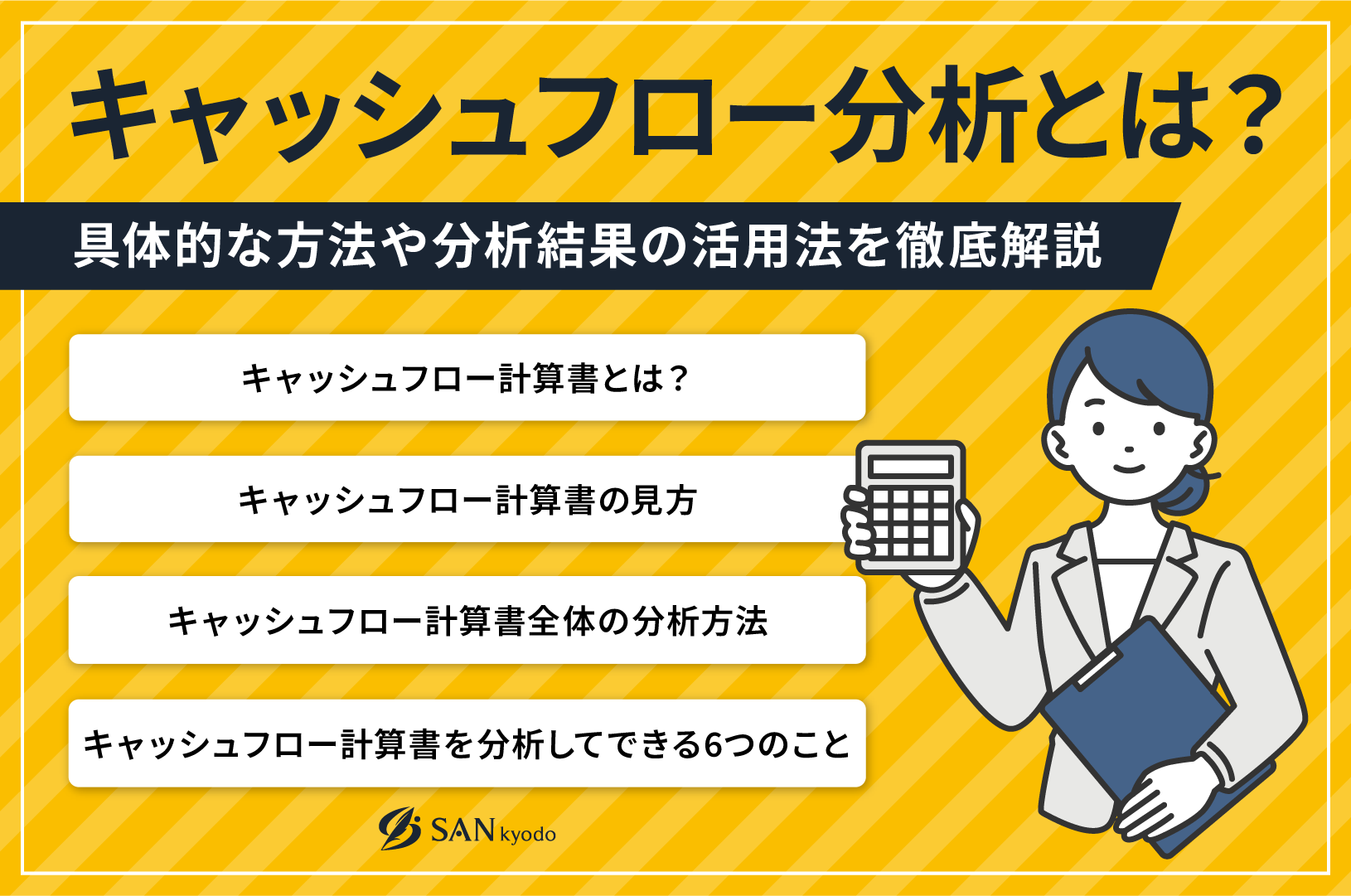
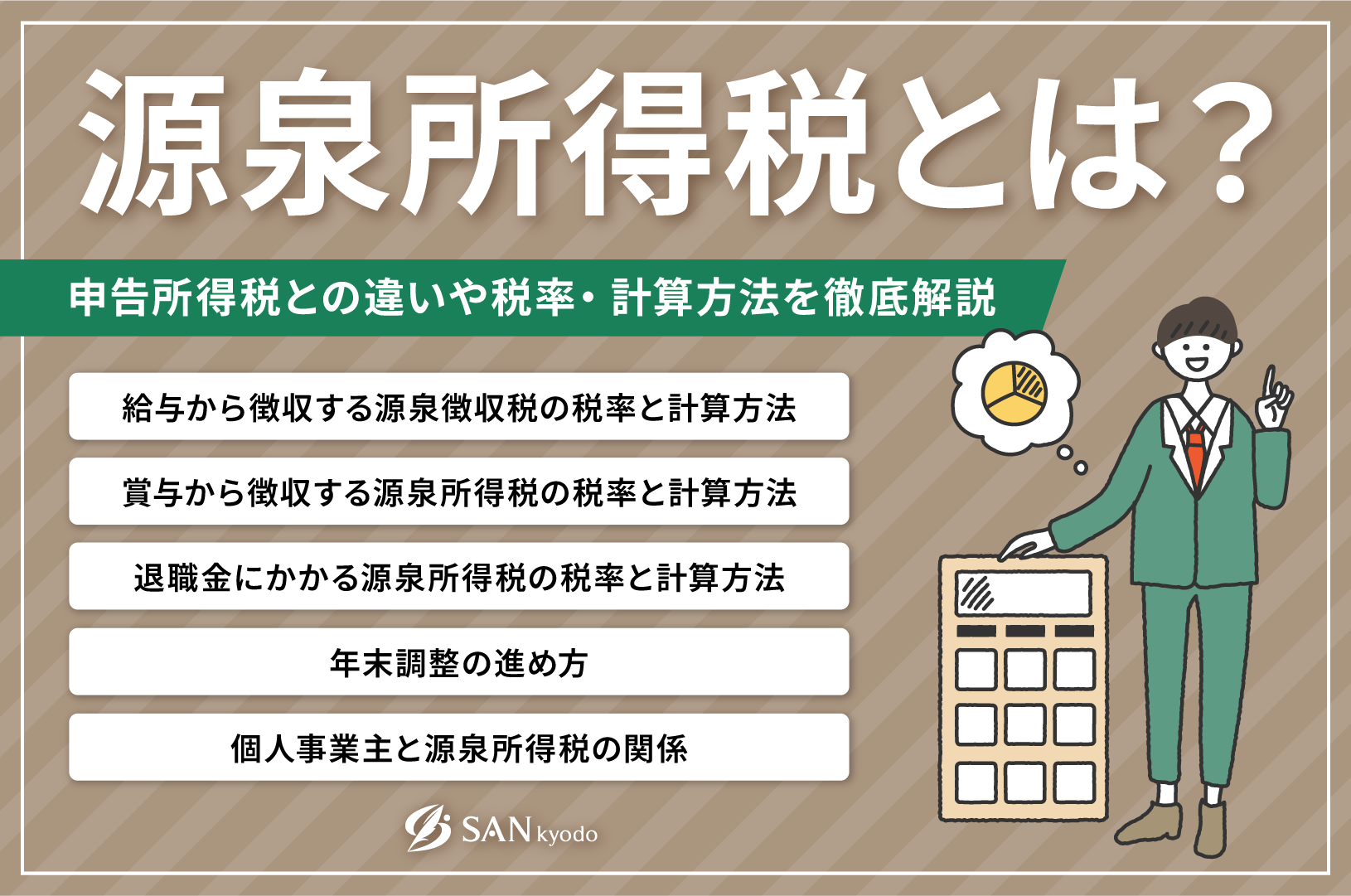
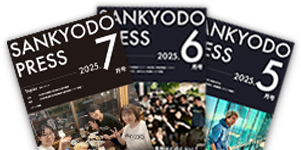
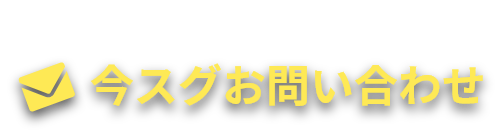

 CLOSE
CLOSE