消費税は私たちの日常生活に欠かせない税金として存在しており、その仕組みは計算方法に関する細かな変更が、事業者にも消費者にも影響を及ぼすことがあります。近年における消費税関連の大きな変更として話題になっているのが、インボイス制度の導入です。
インボイス制度を導入する狙いとしては、税金の透明性や取引の正確性を向上させるというものがあります。ほとんどの事業者にとって直接的に影響を受けるものであるため、具体的な改正内容や影響を正確に把握することは、事業の継続や拡大を目指すうえで極めて重要です。
本記事では、インボイス制度が一体何であるのか、制度の導入によってどのような変更を余儀なくされるのかを深掘りして解説します。
目次
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、課税事業者が消費税の納税に仕入税額控除を適用する際、仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらうことを義務付けた、新たな制度のことです。
これまでは請求書のフォーマットに関する厳格なルールは存在しませんでした。そのため最低限の記載がなされている請求書さえあれば、課税事業者は常に仕入税額控除を適用することが可能でした。
しかし2023年10月1日からインボイス制度が始まり、仕入税額控除のためにはインボイスが必須となります。インボイスに記載されていなければならないものとしては、以下のものが挙げられます。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
どれか一つでも欠けていると、インボイスとしては認められません。
インボイス制度における仕入税額控除の改正
インボイス制度において重要なポイントとなるのは、仕入税額控除の制度です。インボイスは仕入税額控除を行う際に必要になるものであり、このことによって事業者のほとんどが大きな影響を受けることになります。
仕入税額控除とは、売上に含まれる消費税から、仕入額に含まれる消費税を差し引いた残りの部分のみを消費税として納税すれば良いという制度のことです。
たとえば年間の売上が1,100万円(うち消費税100万円)で、仕入額が440万円(うち消費税40万円)だったとしましょう。このとき仕入税額控除を適用しないと、100万円をすべて消費税として国に納めなければいけません。しかし適用した場合には、100万円から40万円を差し引いた残り60万円のみを納めればよいことになります。
仕入税額控除を適用するにあたって、これまでは仕入先から発行してもらう請求書に厳格なルールはありませんでした。しかし2023年10月1日からは、規定のフォーマットに乗っ取ったインボイスを発行してもらわない限り、適用できなくなります。
消費税の区分について
インボイス制度が導入される目的の一つとして、混在する2種類の消費税率を明確に計算し、売り手と買い手が適切に共有することが挙げられます。
2023年現在の日本には、10%と8%の2種類の消費税が存在します。10%が基本的な消費税であり、8%は食品や定期購読の新聞などに適用される「軽減税率」です。このため仕入れの際にも、消費税10%のものと8%のものが混在する可能性が考えられます。
この状況において、消費税額をしっかり明記して正しく算出する方法として、インボイス制度が導入されることになりました。
消費税納税の制度改正に対して免税事業者が準備すること
インボイス制度の導入は、免税事業者に多くの影響をもたらすことが予想されます。従来のシステムとは異なるこの新しい制度を迎えるにあたって、免税事業者は適切な取り組みと調整が必要になるでしょう。
免税事業者が制度改正にあたって準備するべきこととしては、以下の3つが挙げられます。
- 取引先が免税事業者が課税事業者が確認する
- インボイスを発行するために課税事業者になるか検討する
- 課税事業者となる場合は必要な手続きを行う
いずれも事業を安定させるために必要となる意思決定です。以下の解説を読んで、意味するところをきちんと理解しておきましょう。
取引先が免税事業者か課税事業者か確認する
取引先が免税事業者が課税事業者かによって、免税事業者の立場は大きく変動します。そのため取引先がどちらであるかをしっかり確認しておくことが必要です。
免税事業者が課税事業者に対して商品やサービスを提供している場合、取引先である課税事業者から、仕入税額控除のためにインボイスの発行を求められる可能性があります。しかし免税事業者はインボイスを発行することができないので、その要求に応えることはできません。
一方で取引先も免税事業者である場合には、先方の仕入税額控除について考慮する必要がないため、自身が免税事業者のままでも問題は生じないでしょう。
インボイスを発行するために課税事業者になるか検討する
前項でも解説した通り、免税事業者のままではインボイスを発行できず、取引先が課税事業者である場合に先方の仕入税額控除に協力できません。そのことによって取引先から取引を受けられてしまうリスクも考えられます。
取引先と良好な関係を保つことや、新たな取引先を開拓しやすくすることなどを目的として、免税事業者から課税事業者に変わるのも一つの選択です。これにより適格請求書発行事業者となる権利が得られ、インボイスを発行できるようになります。
課税事業者となる場合には、以下の2つの点に注意する必要があります。
- 新たに消費税を納税しなければならなくなる
- 会計処理がこれまでよりも複雑になる
課税事業者は売上が増えたか減ったかにかかわらず、消費税を納めなければいけません。免税事業者の頃と比べて売上が減ったとしても、納税義務に変化はないため、場合によっては資金繰りが苦しくなることもあるでしょう。この点については慎重に計画を立てる必要があります。
インボイスの発行や管理をしなければならなくなるため、会計処理は従来よりも複雑になることが予想されます。問題なくこなすためには、インボイス制度に対応した新たなシステムを導入する必要などがあるでしょう。
課税事業者となる場合は必要な手続きを行う
売上が1,000万円以下の免税事業者が課税事業者になる場合には、決められた手続きを踏まえる必要があります。売上が1,000万円以上になれば自動的に課税事業者となるため、この手続きは必要ありません。
売上が1,000万円以下の免税事業者が課税事業者となる(そしてそのまま適格請求書発行事業者となる)ための手続きは、以下のようなものです。
- 納税地を管轄する税務署長に対し「消費税課税事業者選択届出書」を提出する
- 納税地を管轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する
- 税務署にて審査が行われる
- 審査に通ることができた場合は、税務署から登録通知書が送付される
もし手続きについて不安がある場合は、ぜひ弊社・サン共同税理士法人までお問い合わせください。
サン共同税理士法人には、税制に関する豊富な経験と専門知識を持ったプロフェッショナルが多数在籍しています。お客様のどのようなお悩みに対しても、それぞれの状況に応じた適切なアドバイスとサポートをいたします。
消費税納税の制度改正に対して課税事業者が準備すること
インボイス制度が始まることによって、課税事業者にもさまざまな影響があります。課税事業者はもともと消費税を納税する立場であり、その際に仕入税額控除を少なからず利用してきたことでしょう。この制度を今後も利用できるかどうかが、取引先にかかっているなどの注意点があります。
課税事業者が準備することとしては、以下の5つが挙げられます。
- 取引先が免税事業者が課税事業者が確認する
- 適格請求書発行事業者として登録する
- インボイスを発行するためのシステムを構築する
- インボイスの受取・保存のためのシステムを構築する
- 経過措置について確認しておく
順番に見ていきましょう。
取引先が免税事業者か課税事業者か確認する
インボイス制度の導入にあたって、取引先が免税事業者が課税事業者であることを確認する重要性は、課税事業者にとっても変わりません。なぜなら取引先が免税事業者の場合、インボイスを発行してもらうことができず、仕入税額控除ができなくなるからです。
仕入税額控除が適用できなくなれば、納税する消費税の金額が上がってしまいます。これは純粋に利益の減少につながるものであり、場合によっては取引先を免税事業者から適格請求書発行事業者へと切り替える必要もあるでしょう。
適格請求書発行事業者として登録する
課税事業者はすでに適格請求書発行事業者となる資格を有していますが、自動的に適格請求書発行事業者になるわけではありません。然るべき登録をする必要があります。
適格請求書発行事業者となる手続きは、以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者の登録申請書を入手する
- 必要事項を記載し、住所庁管轄するインボイス登録センター宛に郵送する
- 税務署にて審査が行われる
- 審査に通ることができた場合は、税務署から登録通知書が送付される
またe-Taxによる電子的な申請も可能です。
参考:申請手続|国税庁
インボイスを発行するためのシステムを構築する
インボイスを発行するためのシステムを構築することも大切です。適格請求書発行事業者となった場合、課税事業者である取引先に対してインボイスを発行することが必要となるからです。
すでに使っている会計ソフトや業務システムが、アップデートによりインボイス制度に対応するのであれば、それを使い続ければ問題ありません。しかしそうでない場合には、新たなシステムに変更する必要があるでしょう。
新たなシステムの導入には初期費用がかかりますが、後々の煩雑な作業を簡略化できることを考えれば、コスト削減につながる投資であると考えられます。
インボイスの受取・保存のためのシステムを構築する
インボイスは発行するだけではなく、受け取ることもあり得ます。仕入税額控除を適用するためには、仕入先からインボイスを受け取り、きちんと保存しておく必要があるので、そのためのシステムを構築しなければいけません。
取引先が適格請求書発行事業者であるかどうかを確認し、伝票上で色分けをするなどの工夫が考えられます。取引先が法人の場合には、クラウドシステムを利用することで適格請求書発行事業者か否かの判断が簡単につくため、業務の効率化が期待できます。
会計ソフトをインボイス制度に対応したものにするのは、ここでも必須といえます。クラウド形式のサービスを利用しているのであれば、自動的にアップデートされることが期待できるので、特に何もする必要はないでしょう。しかしインストールするタイプのソフトを利用している場合には、きちんとアップデートされたか確認する必要があります。
経過措置について確認しておく
インボイス制度の導入にあたっては、さまざまな経過措置が用意されていますので、課税事業者は確認しておきましょう。
たとえば適格請求書発行事業者以外から仕入れる場合にも、2026年9月30日までは80%、2029年9月30日までは50%の仕入税額控除が可能です。課税事業者は経過措置をわかっているかいないかで、手元に残る資金に大きな違いが出るので、しっかり把握しておく必要があるでしょう。
インボイス制度に対応するための支援措置
インボイス制度の導入は多くの事業者にとって新たな課題をもたらすものであるため、さまざまな支援策も設けられています。たとえば以下のようなものです。
- 2割特例
- 小規模事業者持続化補助金の増額
- 会計ソフトの導入に対する補助金
- インボイス等の交付義務が免除されるケース
順番に見ていきましょう。
2割特例
2割特例とは、特定の条件を満たす小規模事業者において、2026年9月30日までの期間中に納めるべき消費税額を売上税額の2割にできる特例です。
たとえば売上が990万円(うち消費税90万円)で、仕入額が660万円(うち消費税60万円)だったとしましょう。この場合、通常通り仕入税額控除を適用すれば、90万円から60万円を引いた30万円を納税する必要があります。しかし2割特例を利用すると、90万円の2割である18万円のみを納税すればよいことになります。
2割特例を知っておくことで、大きな節税につながります。
参考:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁
小規模事業者持続化補助金の増額
小規模事業者は、新たな販路の開拓を支援することなどを目的として全国商工会連合会と日本商工会議所が実施している「持続化補助金」を受けられます。
通常の上限額は50万円ですが、新たに免税事業者から課税事業者になる事業者に対しては「インボイス特例」が適用され、補助上限額が50万円増加されます。
この制度は2023年9月7日まで申請可能です。
会計ソフトの導入に対する補助金
インボイス制度の開始にともなって新たに会計ソフトを購入する場合には、経済産業省中小企業庁が行っているIT導入補助金を活用できます。
補助額の上限は450万円で、ソフトウェアを購入する場合には最大2分の1の補助を受けることが可能です。クラウド型のサービスを導入する場合には、最大2年分の利用料が対象となります。
インボイス等の交付義務が免除されるケース
業種によっては、インボイスなどの交付義務が免除される場合もあります。性質上インボイスを交付することが難しいというのが理由です。
具体的には以下のようなケースが挙げられます。
- 30,000円未満の公共交通機関による旅客の運送
- 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
- 生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
- 30,000円未満の自動販売機および自動サービス機により行われる商品の販売等
- 郵便切手類のみを退化とする郵便・貨物サービス
これらに該当するのであれば、国内で課税資産の譲渡などを行ったときに相手方の課税事業者からインボイスを求められても、交付する必要はありません。
参考:交付義務の免除|国税庁
改正後の消費税についてお悩みの方はサン共同税理士法人へ
インボイス制度の導入にともなう消費税の制度改正は、多くの事業者にとって新たな課題や不安をもたらしています。特に新しいルールの詳細や適用方法、適切な対応策をどのようにして取るべきかなど、多岐にわたる疑問や懸念が浮上していることでしょう。
改正後の消費税についてお悩みの方は、ぜひ弊社・サン共同税理士法人までお問い合わせください。
サン共同税理士法人には、税制に関する豊富な経験と専門知識を持ったプロフェッショナルが多数在籍しています。お客様のどのようなお悩みに対しても、それぞれの状況に応じた適切なアドバイスとサポートを提供させていただく用意があります。
初回相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
インボイス制度による消費税納税の改正に関するよくある質問
ここでは、インボイス制度によって消費税納税の仕組みがどのように変わるかに関する、よくある質問に回答していきます。
- インボイス制度で消費税の納税はどう変わりますか?
- インボイス制度が始まることによって、仕入税額控除を適用するために仕入先からインボイスを発行してもらうことが必須となります。仕入先が免税事業者でインボイスを発行できない場合、課税事業者は仕入税額控除を適用できない事態に陥ります。
一方で免税事業者である場合には、そもそも消費税を納める必要がないため、インボイス制度の影響はほとんど受けないでしょう。
このようにインボイス制度は、それぞれの事業者の立場によって異なる影響を受けるものであり、適切な対策の内容もまた事業者ごとに変わってきます。
- 制度開始後も免税事業者のままでいることのデメリットは何ですか?
- インボイス制度が始まった後も免税事業者でいることは可能ですが、デメリットとして以下の2つが考えられます。
- 課税事業者である取引先から取引を切られるかもしれない
- 課税事業者である取引先から報酬額の減額を要求されるかもしれない
これは免税事業者と取引している課税事業者が、インボイス制度の導入以降、仕入税額控除を適用できなくなることに起因しています。課税事業者にとっては、制度の開始以降も免税事業者と取引を続けることは、節税における障壁となるからです。
したがって免税事業者は、上記のデメリットと免税事業者でいることのメリットをきちんと比較したうえで、どのような選択をするか慎重に判断する必要があります。
インボイス制度による消費税納税の改正についてのまとめ
インボイス制度の導入は、ほとんどの事業者に大きな影響を与えます。インボイスを発行できないことで免税事業者が悩む事態だけでなく、インボイスを発行してもらえないことで課税事業者が悩む事態も考えられます。
仕入税額控除は課税事業者にとって節税のための大きな制度であり、取引先次第で仕入税額控除を適用できなくなってしまうのは深刻な問題です。課税事業者は取引先の変更を余儀なくされる場合もありますし、免税事業者にとっては取引を切られてしまうリスクとなります。
インボイス制度に対してどのような対応を取るのが自分にとってベストであるのか、制度に関する正しい情報を集めて慎重に判断しなければいけません。
本記事を参考にして、新たに始まるインボイス制度をベストな形で迎えられるようになっておきましょう。

税理士登録:2013年
税理士登録番号:123285
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にsankyodo税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。


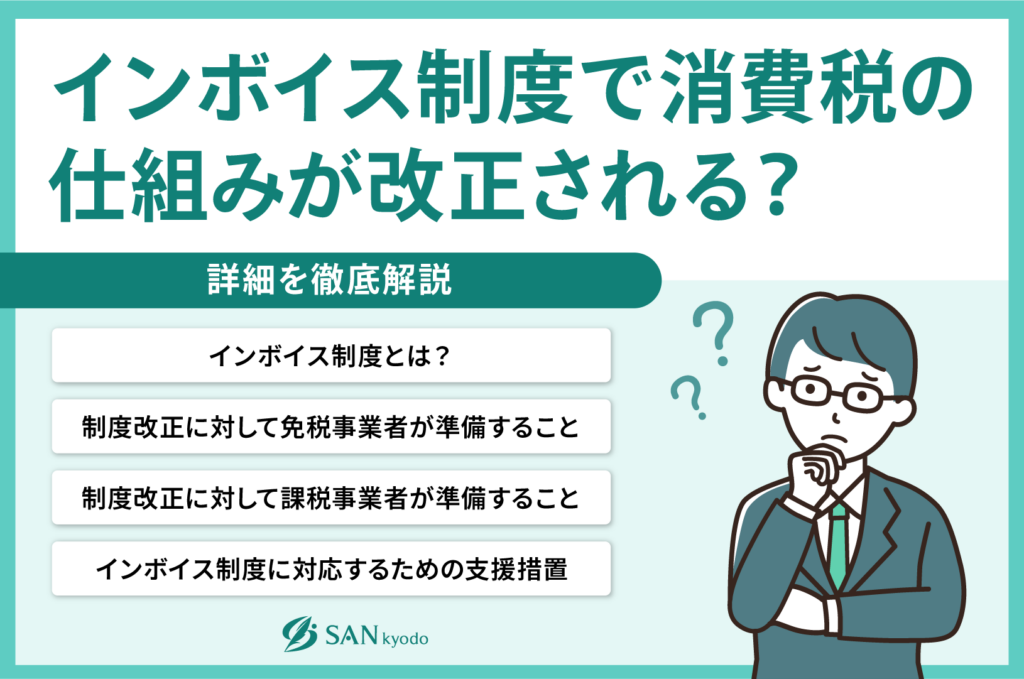
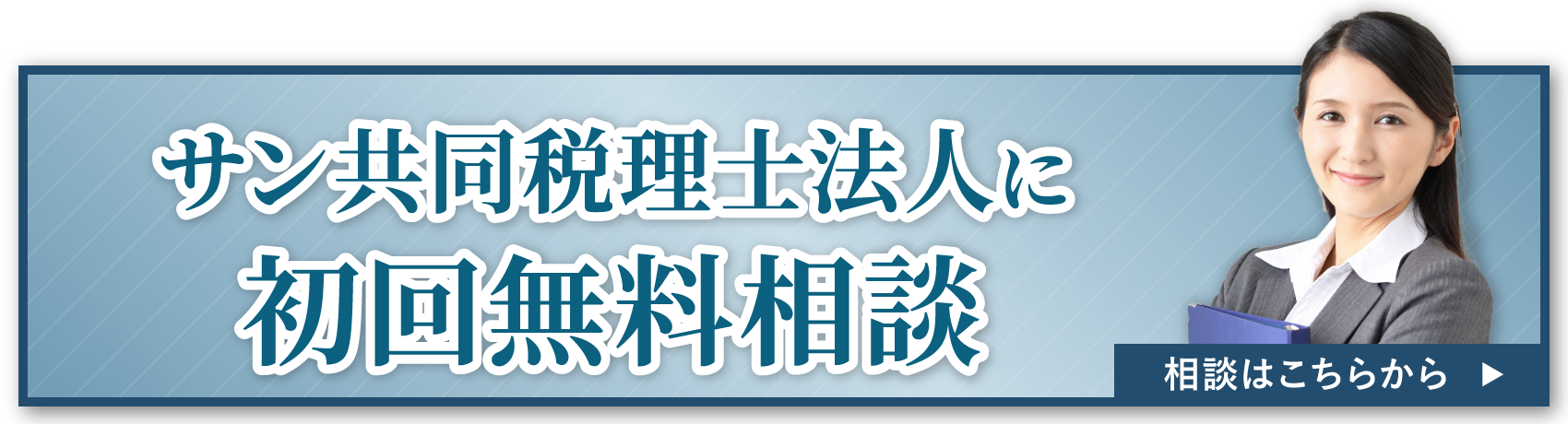

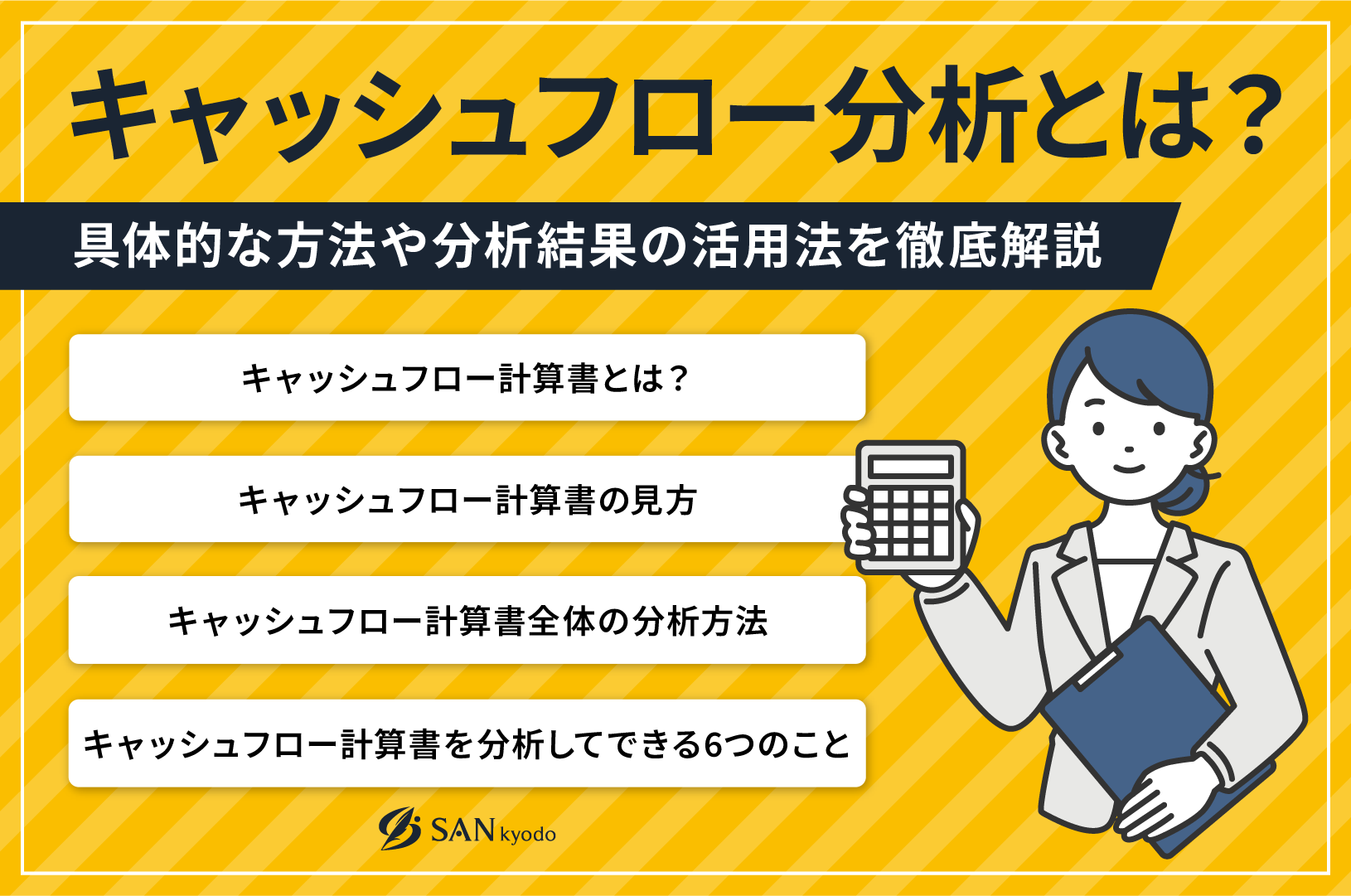
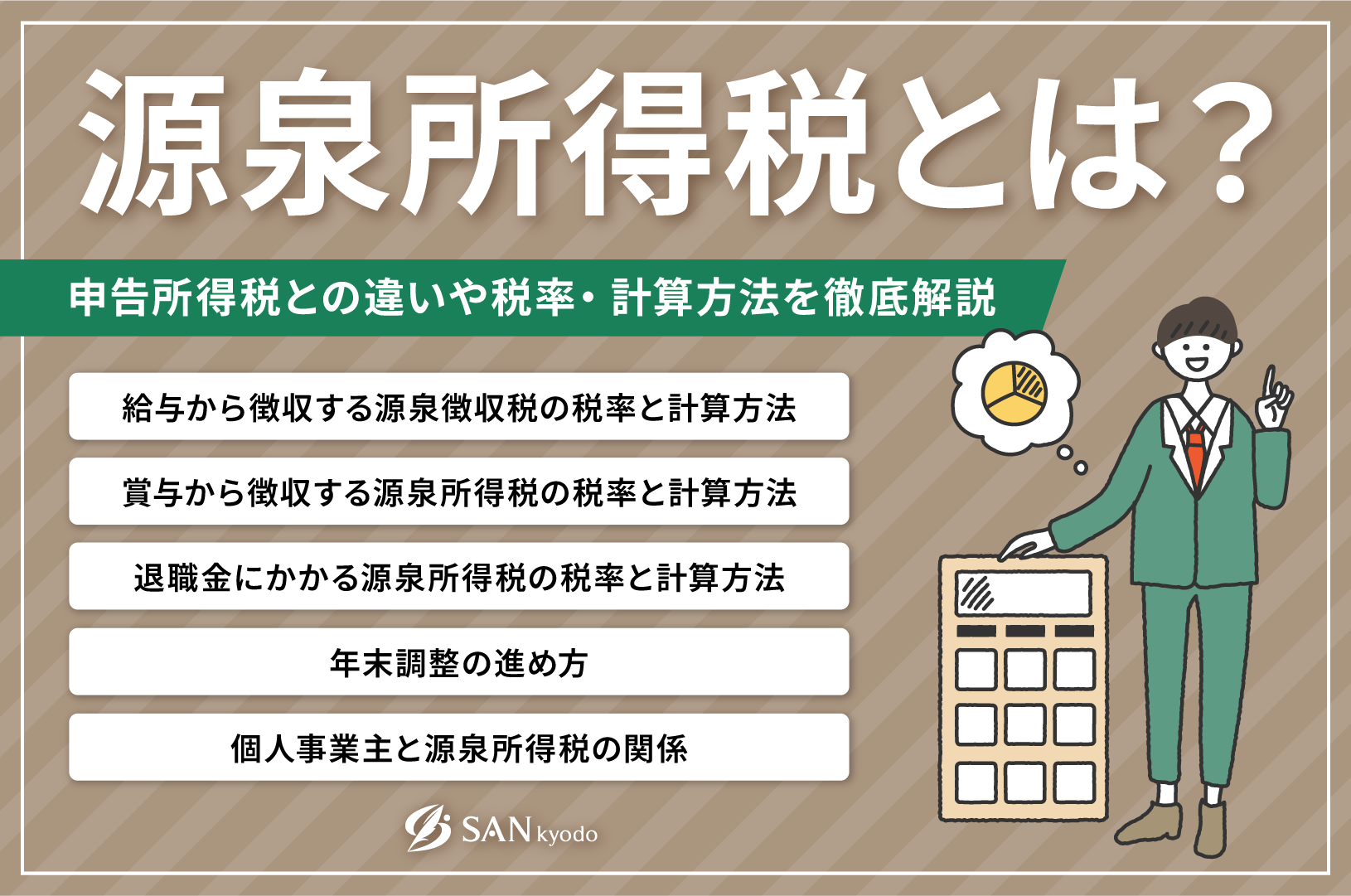
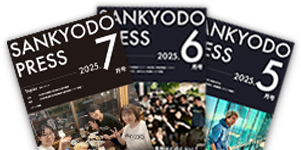
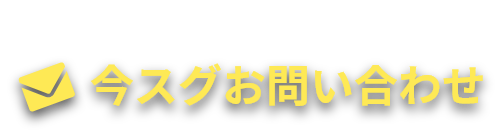

 CLOSE
CLOSE