給与や賞与の支払い時に、納税者に代わって所得税を納める制度を源泉徴収制度といいます。源泉徴収制度を利用して納める所得税が源泉所得税です。源泉徴収制度を利用しなければならない事業所を、源泉徴収義務者といいます。
源泉所得税の範囲は、会社員の給与や弁護士報酬などさまざまです。源泉徴収義務者は、会社で徴収した源泉所得税をすべて支払った日の翌月10日までに納めなければなりません。源泉徴収制度は、所得によりルールが異なります。お金に関わる作業のため、ミスの許されない業務です。
本記事では、源泉所得税の計算方法と税率について詳しく解説します。あわせて、年末調整の流れや個人事業主との関わりについてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
源泉所得税とは?
源泉所得税とは、給与や報酬の支払い者が源泉徴収し、納税者に代わって国へ納付する所得税です。源泉徴収して所得税を納める制度を、源泉徴収制度といいます。源泉徴収制度を利用して所得税を納めなければならない事業所は、源泉徴収義務者です。
源泉徴収義務者は、給与や報酬を支払った日の翌月10日までに「所得税徴収高計算書(納付書)」へ必要事項を記載のうえ、納付します。納税方法は、5通りです。
- 税務署、金融機関またはコンビニで現金納付
- クレジットカード
- インターネットバンキング
- スマホアプリを利用し、PayPayなどのキャッシュレス決済
- ダイレクト決済
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの所得を計算し、確定させます。源泉所得税は、所得税を前もって納めて、年末に調整する税金と考えるとよいでしょう。
申告所得税との違い
申告所得税とは、確定申告により納付した所得税です。源泉徴収制度を利用しない場合、収入のある個人は全員、確定申告をしなければなりません。確定申告は、1月1日から12月31日までの所得を翌年の2月16日から3月15日までに納税者が自ら計算し、納付します。
源泉所得税と申告所得税の違いは、4点です。
- 対象となる所得
- 納税方法
- 計算方法
- 納付タイミング
源泉所得税は、支払う側が計算と納付をする税金です。支払いのたびに源泉所得税を徴収し、翌月10日までに納付します。そのため、年間の所得に対する源泉所得税の額に相違が出るかもしれません。そこで、年末の時点で、既に納めた源泉所得税と支払うべき所得税額の過不足を調整する年末調整が必要です。
源泉所得税の形で差し引かれる所得の種類
源泉所得税で差し引かれる所得には、種類と要件に決まりがあります。たとえば、以下のような場合です。
- 給与や賞与
- 退職手当
- 弁護士や司法書士の報酬
- 原稿や講演の料金
- スポーツ選手の契約金や報酬
- モデルや芸能事務所を営む個人へ支払う報酬
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- 競馬の賞金
- 広告宣伝のための賞金
- 公的年金
- 配当の受け取り
- 利子の受け取り
源泉所得税は、原則として個人に支払われる所得に対して徴収されます。法人へ源泉徴収が適用されるのは、馬主である法人に競馬の賞金が支払われる場合などです。ここで注意が必要なのは、個人事業主です。
たとえば、フリーライターが企業から仕事を受け、個人へ外部委託をしたとします。自分が受け取る報酬は、源泉徴収されたあとの金額です。委託先へは、取引金額から源泉徴収しなければなりません。報酬を受け取るときと、委託料を支払うときの両方で源泉徴収するため、金額を間違えないように管理する必要があります。
給与から徴収する源泉徴収税の税率と計算方法
給与から徴収する源泉所得税の計算方法を解説します。解説の範囲は、毎月の給与で発生する源泉徴収事務です。源泉所得税の算出までには、3つのステップに分かれます。
- 課税支給額の確定
- 課税支給額から社会保険料を除く
- 源泉所得税額を計算
詳しく見ていきましょう。
課税支給額を確定させる
最初に、課税支給額を確定させます。課税支給額とは、給与の総支給額です。支給額は、基本給と各種手当の合計から欠勤や遅刻早退の控除額を差し引いて算出します。各種手当とは、残業手当や役職手当、住宅手当などです。課税支給額の確定には、非課税の手当に注意する必要があります。
非課税の手当と範囲は以下のとおりです。
| 非課税の手当 | 非課税の範囲 |
| 通勤手当 | 公共交通機関の場合=15万円まで非課税
車の場合=3万1,600円~全額まで距離により変動 |
| 転勤や出張の旅費 | 通常必要と認められる範囲まで非課税 |
| 宿直や日直の手当 | 1勤務につき4,000円まで非課税 |
車通勤の場合は、通勤手当を非課税とする範囲が、通勤距離により異なります。詳細は、国税庁が公表している情報を参照しましょう。
参考:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁
課税支給額から社会保険料を除く
次に、課税支給額から社会保険料を除きます。社会保険料の範囲は、以下のとおりです。
- 健康保険料
- 介護保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
健康保険、介護保険と厚生年金保険は、毎年4月から6月までの平均給与を基準として、8月から翌年9月の保険料を算出します。介護保険は、40歳以上の従業員のみ適用される保険です。要介護状態となったときに介護サービスの利用料を一部保障してもらえます。
雇用保険は、失業や雇用を安定させるための保険です。失業保険や育児休業の給付金が受け取れます。社会保険料は、従業員と会社が半分ずつ負担する仕組みです。源泉所得税の計算では、従業員が負担する社会保険料を除きます。
源泉所得税額を求める
最後に、給与所得の源泉徴収税額表を使用し、源泉所得税額を求めます。給与所得の源泉徴収税額表は、給与の計算期間により2種類です。
| 表の種類 | 対象となる給与 |
| 月額表 | 月給制
半月ごと、10日ごと 月の整数倍の期間ごと |
| 日額表 | 日給制
週給制 日割り計算 日雇い賃金 |
月額表と日額表のなかは、甲乙丙の欄に分かれています。甲は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人です。乙は2カ月超の勤務予定があり「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人が該当します。丙は、勤務契約が2カ月以内の場合や、日雇い賃金に対して使用する欄です。
さらに甲欄は、扶養親族等の人数により列が分かれています。給与所得の源泉徴収税額表を見て、社会保険料を控除したあとの給与等の額と、該当する欄および扶養親族等の人数が交差する金額が源泉所得税の金額です。
賞与から徴収する源泉所得税の税率と計算方法
賞与から徴収する源泉所得税の計算方法を解説します。算出までに必要なステップは3つです。
- 前月の給与から社会保険料と非課税交通費を差し引く
- 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を使用し、税率を確認する
- 源泉所得税額を求める
詳しく見ていきましょう。
前月の給与から社会保険料と非課税交通費を差し引く
最初に、前月の給与から社会保険料と非課税交通費を差し引きます。前月の給与から社会保険料などを引いた金額が、源泉所得税率の基準となる額です。前月の給与に残業や役職などの手当が含まれている場合も給与の金額に含めます。
たとえば、賞与金額が50万円、前月の給与が40万と社会保険料が6万円、非課税交通費が4万円としましょう。
前月の給与40万円-社会保険料6万円-非課税交通費4万円=30万円
賞与にかかる源泉所得税率の基準額は、30万円です。社会保険料と非課税の交通費は、前月の給与計算と同じく作業をします。そこで、実務の場面では、前月の給与計算を行った記録を残しておくことで、賞与計算の作業がスムーズに進みます。
税率を確認する
次に、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を使用した税率の確認です。「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を参照し、前月の給与から社会保険料等を除いた額と扶養親族等の人数に該当する欄の一番左に税率が表示されています。
たとえば、前月の給与から社会保険料等を除いた額が30万円、扶養親族等が2人としましょう。
賞与にかかる源泉所得税の税率は、4.084%です。
企業によっては、前月の給与がなく「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の基準となる金額が算出できないケースもあるでしょう。その場合は「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を使用して源泉所得税を算出します。
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の最新版は、国税庁のホームページに掲載中です。
源泉所得税額を求める
最後に、源泉所得税額を計算します。社会保険料等を除いた前月の給与を基準に源泉所得税率を算出しました。この源泉税率を使用して税額を計算します。
たとえば、以下の条件で賞与にかかる源泉所得税を求めるとしましょう。
- 賞与金額50万円
- 賞与の社会保険料8万円
- 前月の給与40万円
- 前月の社会保険料6万円
- 前月の非課税交通費4万円
- 扶養親族等2人
前月の給与40万円-社会保険料6万円-非課税交通費4万円=30万円
賞与にかかる源泉所得税の税率=4.084%
源泉所得税=(賞与50万円-賞与の社会保険料8万円)×税率4.084%=1万7,152.8
計算結果が1円未満となる場合は、切り捨てます。本例の源泉所得税は、1万7,152円です。
退職金にかかる源泉所得税の税率と計算方法
退職金にかかる源泉所得税の計算方法を解説します。算出までに必要なステップは3つです。
- 課税対象となる退職所得金額を算出
- 所得税額を計算する
課税対象となる退職所得金額を算出するには、勤続年数の情報が必要です。
課税対象となる退職所得金額を算出する
課税対象となる退職所得の金額は、退職手当の区分ごとに異なります。
| 退職手当の区分 | 計算式 |
| 一般退職手当 | (一般退職手当等-退職所得控除額)×1/2 |
| 短期退職手当 | ①短期退職手当等-退職所得控除額≦300万円の場合
(短期退職手当等-退職所得控除額)×1/2 |
| ②短期退職手当等-退職所得控除額>300万円の場合
150万円+{短期退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)} |
|
| 特定役員退職手当等 | 特定役員退職手当等の収入金額-退職所得控除額 |
特定役員退職手当等とは、役員としての勤続年数が5年以下である者が、役員の勤続年数に応じて受ける手当です。課税対象となる退職所得の計算に使用する退職所得控除額は、退職する会社の勤続年数で変わります。1年未満の勤続年数は切り上げです。
| 勤続20年以下 | 40万円×勤続年数
(80万円に満たない場合には、80万円) |
| 勤続20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
退職手当が1,500万円、勤続年数が18年の場合は以下が課税対象額です。
(一般退職手当等1,500万円-退職所得控除額720万円)×1/2=390万円
一方、退職手当が1,500万円、勤続年数が21年の場合は以下のように計算します。
退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数21年-20年)=870万円
(一般退職手当等1,500万円-退職所得控除額870万円)×1/2=315万円
所得税額を計算する
課税対象となる退職所得金額を算出したら、以下の計算式で源泉所得税の金額を計算します。
源泉所得税額=課税対象となる退職所得×所得税率-控除額×102.1%
計算に使用する所得税率と控除額は「退職所得の源泉徴収税額の速算表」を参照します。
| 課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 | 計算式 |
| 195万円以下 | 5% | ー | (課税所得×5%)×102.1% |
| 195万円超~330万円 | 10% | 9万7,500円 | (課税所得×10%-9万7,500円)×102.1% |
| 330万円超~695万円 | 20% | 42万7,500円 | (課税所得×20%-42万7,500円)×102.1% |
| 695万円超~900万円 | 23% | 63万6,000円 | (課税所得×23%-63万6,000円)×102.1% |
| 900万円超~1,800万円 | 33% | 153万6,000円 | (課税所得×33%-153万6,000円)×102.1% |
| 1,800万円超~4,000万円 | 40% | 279万6,000円 | (課税所得×40%-279万6,000円)×102.1% |
| 4,000万円超~ | 45% | 479万6,000円 | (課税所得×45%-479万6,000円)×102.1% |
退職手当が1,500万円、勤続年数が18年の場合における源泉所得税額は以下の通りです。
課税退職所得=(一般退職手当等1,500万円-退職所得控除額720万円)×1/2=390万円
源泉所得税額=(390万円×20%-42万7,500円)×102.1%=35万9,902円
一方、退職手当が1,500万円、勤続年数が21年の場合における源泉所得税額は以下のように計算します。
退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数21年-20年)=870万円
課税退職所得=(一般退職手当等1,500万円-退職所得控除額870万円)×1/2=315万円
源泉所得税額=(315万円×20%-42万7,500円)×102.1%=20万6,752円
年末調整の進め方
年末調整とは、源泉徴収された所得税の合計金額と、1年間の所得に対する所得税額を調整する手続きです。年末調整の作業は、以下の流れで行います。
| 作業の流れ | 概要 |
| 書類の回収 | 書類は主に4種類。付随する証明書を添付して提出
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書 (任意)保険料控除申告書 (任意)住宅借入金等特別控除申告書 |
| 1年間の給与所得控除額を計算 | 1年間に支給した給与から社会保険料等を控除 |
| 源泉徴収税額を合計 | 既に徴収した源泉所得税の金額を合計 |
| 所得控除・扶養控除を計算 | 回収した書類を元に、所得控除・扶養控除を計算
所得控除は、生命保険料控除や地震保険料控除など 扶養控除は、配偶者特別控除やひとり親控除など |
| 課税所得金額を算出 | 1年間の給与所得控除額から所得控除・扶養控除を差し引いた金額を算出
1,000円以下は切り捨てる |
| 算出所得税を計算 | 「年末調整のための算出所得税額の速算表」を参照し、算出所得税を計算 |
| 年調年税額を確定 | 年調年税額=算出所得税-住宅ローン控除額 |
| 過不足額の還付または徴収 | 年調年税額と源泉徴収税額を比較し、過払いの場合は還付を、不足の場合は徴収 |
従業員への年末調整が終了したら、翌月10日までに調整した源泉所得税を納税します。年末調整により、納税額がマイナスとなる場合は、翌月以降に過払い分の控除が可能です。
個人事業主と源泉所得税の関係
個人事業主は、業務内容によって源泉徴収を受ける立場にも、源泉徴収義務者の立場にもなりえます。たとえば、個人で運営している弁護士が、事務作業員を雇ったとしましょう。事務作業員へは源泉所得税を差し引いた金額の支給が必要です。
徴収した源泉所得税は、翌月10日までに納付しなければなりません。一方、クライアントから報酬を受けるときは、源泉所得税を差し引いた金額を受け取ります。
どちらも名前が源泉所得税なので、受け取った分と支払った分を混同するケースも少なくありません。そこで、個人事業主は、源泉所得税の受け渡し記録をつけておきましょう。源泉所得税の受け渡し記録は、確定申告のときにも申告書へ記載する事項です。
源泉所得税の税率についてお悩みの方はサン共同税理士法人へ
給与の源泉所得税を計算する作業は、毎月発生するため比較的覚えやすいでしょう。しかし、賞与や年末調整は、年に1回もしくは2回ほどの作業なので、忘れがちになってしまいます。
さらに、年末調整は、短期間で細かい作業が多く発生します。従業員の給与に関わる内容なので、間違いの許されない作業です。短時間で慎重に作業するのは負担を感じる人も多いのではないでしょうか。そこで、源泉所得税の計算手続きについてお困りの方は、サン共同税理士法人へご相談ください。
弊社は、今まで培ってきたプロのノウハウがあるので、源泉所得税の計算作業のご相談に加えて正しい節税知識のアドバイスができます。給与計算作業の工数削減にお悩みの場合は、毎月のように発生する源泉徴収作業の代行も可能です。初回相談は無料で実施しています。ぜひお気軽にご相談ください。
源泉所得税と税率に関するよくある質問
源泉所得税と税率についてよくある質問に回答していきます。
- 源泉所得税とはどのようなものですか?
- 源泉所得税の税率はどれくらいですか?
気になる疑問から確認してみましょう。
- 源泉所得税とはどのようなものですか?
- 源泉所得税とは、支払い者が源泉徴収し、納税者に代わって納めた所得税のことです。所得税を前もって納めて、年末に所得税額を確定し、過不足を調整します。
- 源泉所得税の税率はどれくらいですか?
- 給与や退職手当にかかる源泉所得税の計算は、税額表を使用します。一方、利子や報酬にかかる場合は、税率が定められています。イラストレーターの報酬が10万円だった場合を例にしてみましょう。
源泉徴収税額=1回の所得10万円×10.21%=1万210円
この税率は、源泉所得税を算出する場合においての税率です。確定申告でさまざまな所得を合算して所得税額を算出する場合は、別の税率が適用されるので注意しましょう。
源泉所得税と税率についてのまとめ
源泉所得税の計算方法と税率について解説しました。源泉所得税とは、支払い者が納税者に代わって納める所得税です。給与等の支払い者は、源泉徴収した所得税を支払った日の翌月10日までに納めなければなりません。
源泉徴収制度は、所得税の前払い制度でもあります。給与等の支払い者は、1年間の給与支給額を元に、所得税額を算出し、過不足を調整する年末調整が必要です。給与計算の作業は、源泉所得税の徴収や年末調整など、短期間にミスの許されない業務が多くあります。
本業と兼務で作業する人や、多くの従業員を抱える企業では、手間に感じることも少なくないでしょう。そこで、源泉徴収作業や源泉所得税についてお困りの人は、税務のプロである税理士に相談することをおすすめします。
ぜひ本記事を参考に、源泉所得税の計算方法を身に付けてください。

税理士登録:2013年
税理士登録番号:123285
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にsankyodo税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。


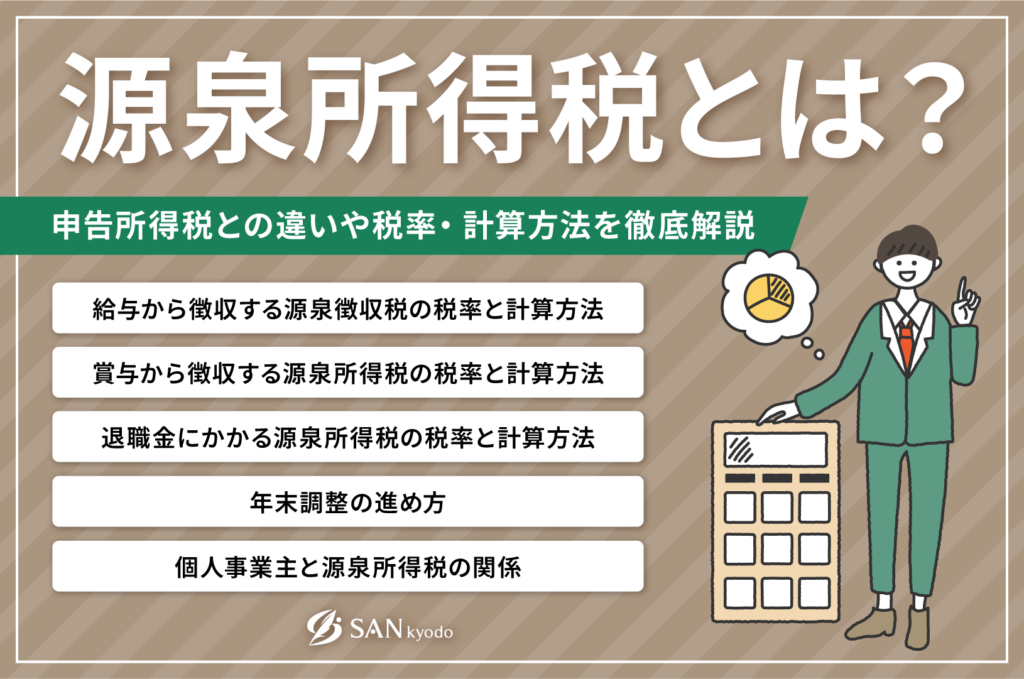
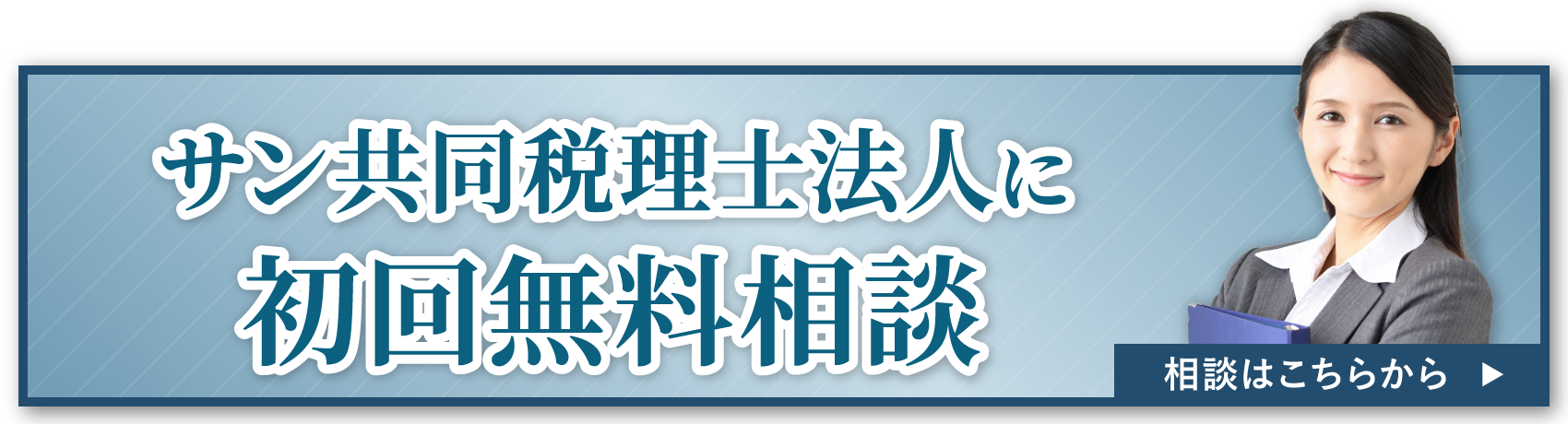

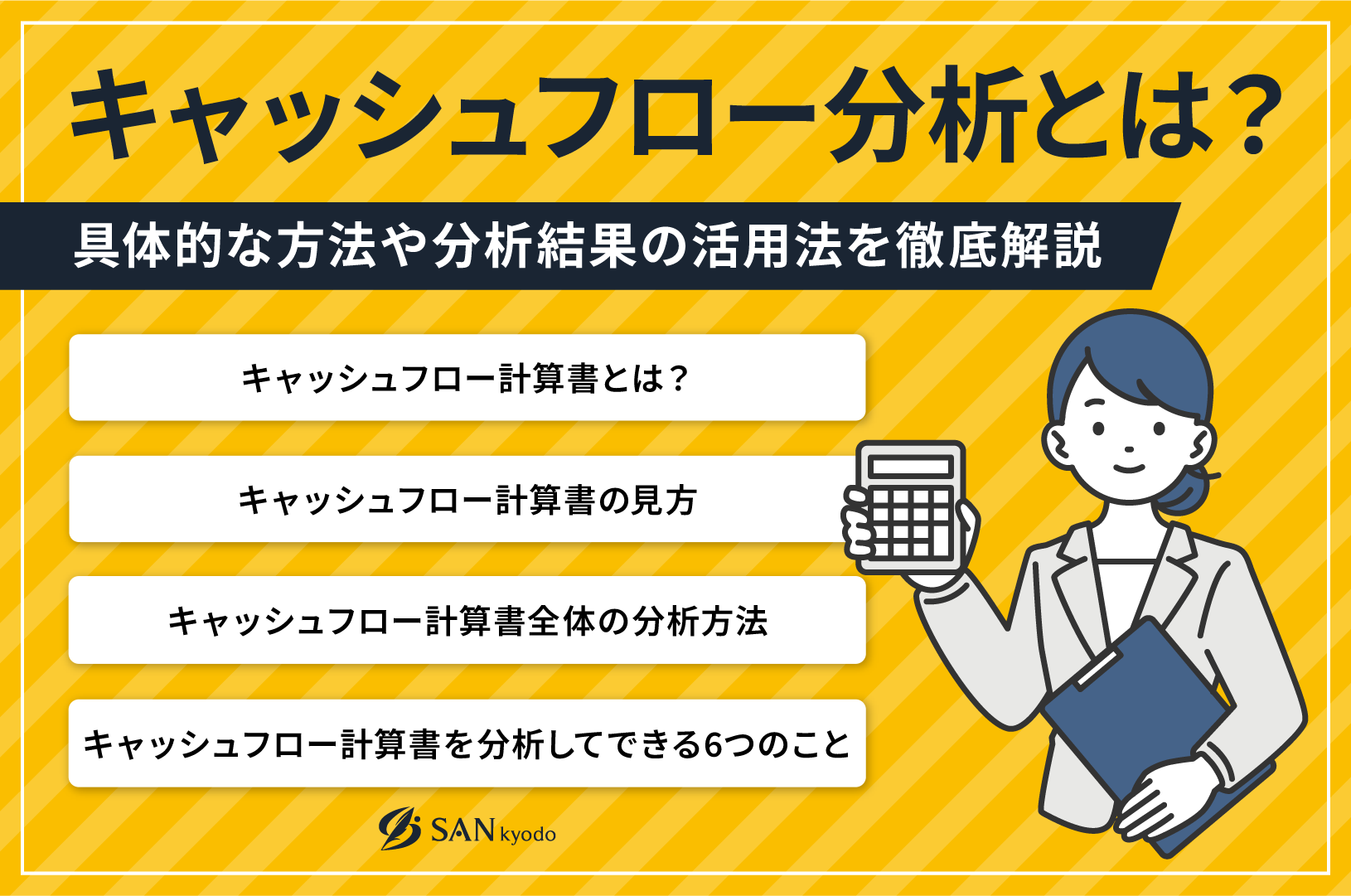
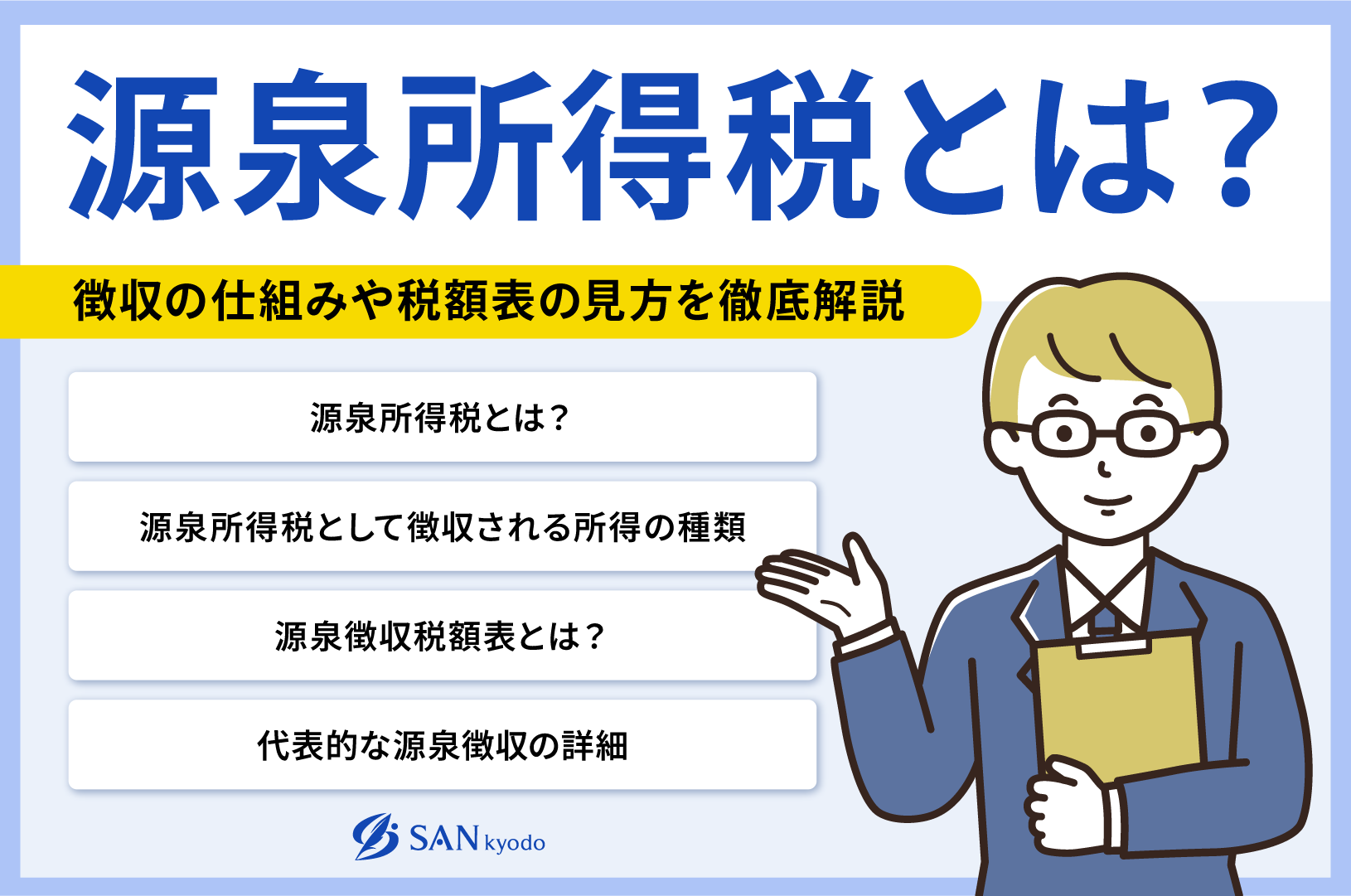
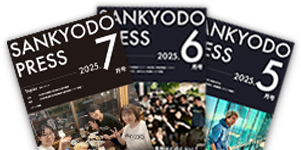
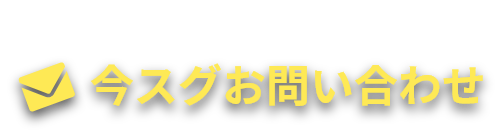

 CLOSE
CLOSE