2023年10月1日から、消費税に関連する新たな制度としてインボイス制度が導入されます。
仕入税額控除に関する取扱いを改めたものであり、さまざまな事業者に影響を与える内容です。
とくに個人事業主やフリーランスに与える影響は大きいといわれており、該当する方は今のうちにきちんと内容を把握し、備えておく必要があります。
しかしニュースなどでインボイス制度という言葉自体は知っていても、具体的な内容を理解できていない方も多いのではないでしょうか。
実際、インボイス制度は内容が複雑であるため、すぐには理解しにくい面もあります。
そこでこの記事では、インボイス制度が個人事業主やフリーランスに与える影響について、わかりやすい解説を試みています。
最後まで読むことで、個人事業主やフリーランスの方がどのように動けばよいのか、おおよそのところが理解できるでしょう。
2023年10月から導入されたインボイス制度ですが、どのように対応したらよいのかがわからない方も多いのではないでしょうか?
サン共同ではお客様への対応事例を元に作成したインボイス制度に関する資料を無料配布しております。
個人事業主の方・法人の方どちらにも対応しておりますので、ご興味のある方はこちらからダウンロードください。⇒インボイス制度まるわかりBookの無料ダウンロードはこちら
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
目次
インボイス制度とは?
インボイス制度とはどのようなものか、まずはその全般的な知識を、以下の3つのポイントに分けて解説します。
- 仕入税額控除にインボイスが必要になる
- 仕入税額控除ができない場合の影響
- インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者のみ
上記はインボイス制度の根幹をなす部分なので、まずはここをしっかりと理解しておく必要があります。
以下の解説をじっくり読んで頭に入れておきましょう。
仕入税額控除にインボイスが必要になる
インボイス制度が導入されたあとは、仕入税額控除をするにあたってインボイスが必要になります。
仕入税額控除とは、事業者が売上にかかる消費税を国に納める際、支払った経費等の金額に含まれる消費税を差し引くことができるという制度です。
たとえば11万円(うち消費税10,000円)で仕入れたものを22万円(うち消費税2万円)で顧客に売った場合、20,000円から10,000円を引いた残り10,000円が、国に納めるべき消費税となります。
仕入税額控除自体は以前からあった制度ですが、インボイス制度が導入されると、仕入税額控除を適用するために仕入先から得たインボイスが必要になります。
インボイスによって仕入れ値に含まれる消費税を証明できなければ、控除を受けられないルールに変更されるからです。
仕入税額控除ができない場合の影響
仕入税額控除ができないと、支払った経費等の金額の中に含まれる消費税を控除できないため、余計な消費税を国に納める必要が生まれてしまいます。
たとえばYouTubeの動画制作で考えてみましょう。
YouTube制作会社が企業Aから動画制作の仕事を受注し、動画編集業務の一部をフリーランスの動画編集者に外注したとします。
このときのお金の流れとしては、企業AがYouTube制作会社に報酬を支払い、YouTube制作会社が動画編集者に報酬を支払う形になります。
しかし動画編集者はフリーランスであるため、インボイス制度を発行できる「適格請求書発行事業者」として登録していないかもしれません。
インボイスを受け取れないYouTube制作会社は、動画編集者に対して支払った報酬に含まれる消費税分を、企業Aから受け取った報酬に含まれる消費税から差し引けないことになります。
仕入税額控除ができないことにより、上記のような事態の発生が考えられます。
インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者のみ
インボイスは誰でも任意に発行できるものではありません。インボイスを発行するためには、前項でも触れた「適格請求書発行事業者」として国に登録する必要があります。
適格請求書発行事業者になると、国から登録番号が割り振られます。
インボイスにはこの登録番号を記載しなければならないので、登録なしではインボイスを発行できない仕組みです。
適格請求書発行事業者とは?
すでに解説した通り、適格請求書発行事業者とは、簡単にいえば「インボイスを発行できる事業者」のことです。
適格請求書発行事業者になるためには、以下の2つのポイントを押さえておく必要があります。
- 適格請求書発行事業者は課税事業者のみがなれる
- 適格請求書発行事業者になるには登録申請が必要
順番に見ていきましょう。
適格請求書発行事業者は課税事業者のみがなれる
適格請求書発行事業者は、課税事業者のみがなれるものです。課税事業者とは、国に対して消費税を納めている事業者のことを指します。
個人事業主やフリーランスの多くは、一定以下の売り上げであれば消費税を納税する必要のない「免税事業者」の立場で仕事をしています。
しかしそのままでは適格請求書発行事業者になれないため、登録のためにまず課税事業者になることから始めなければいけません。
適格請求書発行事業者になるには登録申請が必要
適格請求書発行事業者になるには、税務署へ登録申請をする必要があります。具体的な手順は以下の通りです。
- 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する
- 税務署の審査のあと「登録通知書」が発行される
- 登録が完了したら、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号や事業者名、登録年月日などを確認できる
前項でも触れた通り、免税事業者の場合は、上記の手順を経る前にまず課税事業者になる必要があるので注意してください。
【売り手側】免税事業者の個人事業主・法人が課税事業者になった場合に受ける影響
免税事業者である個人事業主や法人が、新たに課税事業者となった場合に受ける影響について見ていきます。
まず前提として、免税事業者になれる条件は「基準期間における課税売上高が1,000万円以下であること」です。
つまり小規模のビジネスをおこなっている者しか、免税事業者になることはできません。それ以上の売上があるならば、この項は読み飛ばしても問題ないでしょう。
免税事業者が課税事業主になった場合、以下のような変化があります。
- 消費税の納税が必要になる
- 請求書のフォーマットを変更する必要がある
- 税務処理が増える
いずれも重要な要素であり、多くの場合、事業内容に大きな影響を与えます。以下の解説を読んで、事前にしっかり把握しておきましょう。
消費税の納税が必要になる
免税事業者であったときは、売上に含まれる消費税を国に納める必要がありませんでした。
たとえば免税事業者であるフリーライターが10,000円で記事を執筆した場合、受け取れる総額は消費税込みで11,000円です。消費税分が1,000円含まれていますが、免税事業者であればこれはそのまま自分の収入となります。
しかし課税事業者になった場合には、上記1,000円分の消費税を、国に納めなければいけなくなります。
現在インボイス制度の導入について激しい議論が繰り返されている主な理由は、このような形で小規模事業者に経済的な負担があるからです。
ただし簡易課税制度という制度が用意されており、上手に利用することにより支払う税金を減額できる可能性もあります。
簡易課税制度についての具体的なことは後述します。
請求書のフォーマットを変更する必要がある
課税事業者となったあとは、請求書のフォーマットを変更する必要があります。
具体的には、請求する総額だけでなく、含まれる消費税を内訳として記載しなければいけません。
消費税は8%のものと10%のものがあるので、それぞれを区分して記載する必要があります。
消費税がどのくらい含まれているのかきちんと記載した請求書(インボイス)を適格請求書発行事業者が取引先に渡すことで、取引先はこれを仕入税額控除に利用できるようになります。
また請求書には、適格請求書発行事業者の登録番号も記載しなければいけません。
税務処理が増える
課税事業者となることで、税務処理はどうしても増えてしまいます。
消費税の計算を細かく行わなければならないので、免税事業者の頃と比べて手間がかかってしまうのは仕方のないところでしょう。
しかし後述する支援装置や簡易課税制度を利用することにより、税務処理の負担を軽くすることができます。
【売り手側】免税事業者の個人事業主・法人が免税事業者のままの場合に受ける影響
現在免税事業者である個人事業主・法人が、インボイス制度導入後も免税事業者のままでいる場合には、以下のようなことを想定しておく必要があります。
- 仕事が減る可能性がある
どういうことなのか、具体的に解説します。
仕事が減る可能性がある
インボイス制度導入後も免税事業者であり続けることにより、仕事が減る可能性があります。
インボイス制度導入後は、免税事業者を相手に支払った額に関して、仕入税額控除を適用できなくなるからです。
免税事業者が自らの立場を維持し続けることは、取引先にとっては実質的な増税のようなものです。
必然的に「同じ金額を支払うのであれば課税事業者相手のほうがよい」という判断になり、免税事業者が取引先として選ばれなくなる可能性が高まります。
上記のような流れで、仕事が減ってしまうかもしれないことに注意が必要です。
【買い手側】課税事業者の法人・個人事業主に与える影響
インボイス制度の導入が、すでに課税事業者である法人や個人事業主に与える影響としては、以下のようなものが挙げられます。
- 免税事業者から仕入れ・外注すると仕入税額控除ができない
- 免税事業者への対応方針を決める必要がある
- インボイスの保存方法を決める必要がある
手元に残る資金の額に関わる重要な要素なので、以下の解説を読んでしっかり概要をつかんでおきましょう。
免税事業者から仕入れ・外注すると仕入税額控除ができない
インボイス制度導入後、免税事業者を相手に仕入れや外注をすると、支払った金額に関して仕入税額控除ができなくなります。
たとえば仕入先が免税事業者であり、22,000円(うち消費税2,000円)の仕入れをしたとします。
この消費税2,000円は、仕入先が適格請求書発行事業者であれば、仕入税額控除の対象として扱えます。
しかし免税事業者であると仕入税額控除が行えないので、自身が支払うべき消費税からこの2,000円を差し引くことができません。
上記のように、仕入先・外注先が免税事業者であることにより、支払うべき消費税額が増えてしまうことになります。
免税事業者への対応方針を決める必要がある
前項で解説したデメリットが存在するため、取引先が免税事業者である場合、今後どのように付き合っていくか、対応方針を決める必要があります。
あるいは取引を終わらせて、別の適格請求書発行事業者と新たに継続的な取引をおこなう選択肢もあります。
いずれにせよ、免税事業者に対してどのように対応するのか、インボイス制度が導入されるまでにしっかり決めておくことが大切です。
インボイスの保存方法を決める必要がある
適格請求書発行事業者は取引先にインボイスを送付する義務がありますが、同じくインボイスを受け取る側にも、それを適切に保管する義務があります。
インボイスは消費税に関する証明書であり、紛失した場合には仕入税額控除を受けられないので注意が必要です。
またデジタルインボイス(標準化され構造化された電子インボイス)である場合には、電子帳簿保存法の改正にもとづき、電子化された状態のまま適切に保存しなくてはいけません。
消費税の負担を抑える方法と緩和措置
インボイス制度には、いくつかの緩和措置が用意されています。具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 簡易課税制度
- 仕入税額控除の経過措置
- 少額の仕入のインボイス不要
- 納税額の支援措置
きちんと理解しておくことでコスト削減につながるので、以下の解説をしっかり読んでおきましょう。
課税事業者の簡易課税制度
インボイス制度が導入されると、これまで免税事業者であった者は消費税負担が増えるだけでなく、事務処理の手間も増えてしまいます。
それらに対する緩和措置として、簡易課税制度というものが用意されています。
簡易課税制度とは、消費税額を売上と仕入それぞれについて計算するのではなく、業種によって「みなし仕入率」を定め、支払うべき消費税を売上に係る消費税に比例した計算で行って構わないという制度です。
みなし仕入率は、事業区分ごとに以下のように設定されています。
- 第1種事業(卸売業):90%
- 第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係るもの)):80%
- 第3種事業(農業林業漁業(飲食料品の譲渡にかからないもの)、鉱業、建設業など):70%
- 第4種事業(第1、2、3、5、6種事業に当てはまらないもの):60%
- 第5種事業(運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業):50%
- 第6種事業(不動産業):40%
上記の値を用いることで、計算が簡易になるだけでなく、支払うべき消費税額を減らせる可能性があります。
参考:令和5年10月1日からインボイス制度が始まります|国税庁
仕入税額控除の経過措置
インボイス制度の導入は2023年10月からと定められていますが、制度開始にあたって一定の経過措置が取られる予定です。
具体的には、適格請求書発行事業者以外からの仕入れに関しても、インボイス制度導入からしばらくのあいだは消費税の一部が仕入税額控除の対象となります。
最初の3年間、すなわち2026年10月までは、課税仕入の80%を控除可能です。
次の3年間、すなわち2029年9月までは、課税仕入の50%を仕入税額控除の対象にできます。
少額の仕入のインボイス不要
すべての取引に対してインボイスが必要なわけではありません。
1万円未満の課税仕入れについては、インボイスを保存しなくてもよいと定められています。帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能です。
この措置の対象となるのは、基準期間(2年前)の課税売上が1億円以下、または1年前の上半期の課税売上が5,000万円以下の方です。
対象期間は、2029年9月30日までとなっています。
納税額の支援措置
小規模事業者向けに、給付金の支援措置も用意されています。
持続化給付金について、免税事業者が適格請求書発行事業者に登録した場合に、補助上限額が一律50万円加算されるという内容です。
通常の補助上限は50〜200万円ですが、これが100〜250万円にアップします。
ただしすべての出費が補助の対象となるわけではありません。対象となるのは、以下のようなものです。
- 機械装置導入
- 広報費
- 展示会等出展費
- 開発費
- 委託費
何に使ってもよいお金ではないことには注意してください。
免税事業者の個人事業主は適格請求書発行事業者になるべき?
免税事業者である個人事業主は、インボイス制度の導入にともない、適格請求書発行事業者になるべきなのでしょうか。
答えは1人1人の状況によって変わります。ここでは以下の3つのケースに分けて考えていきます。
- 顧客が個人の場合
- 顧客が法人(課税事業者)の場合
自分に当てはまる項目にはとくに注目してお読みください。
顧客が個人の場合
顧客が個人、すなわち仕入税額控除をおこなわない相手の場合には、免税事業者のままでもとくに問題とはなりません。
こちらが免税事業者であることが、顧客に対してデメリットを及ぼさないからです。
顧客が法人(課税事業者)の場合
顧客が課税事業者である法人の場合には、適格請求書発行事業者に登録しておいたほうがよいでしょう。
取引先である法人は仕入税額控除を行うため、こちらが免税事業者のままだと、少なからず負担を背負わせることになってしまうからです。
ただし絶対的な指標ではないため、顧客である法人が「あなたは免税事業者のままでもよい」と言ってくれたのであれば、無理に適格請求書発行事業者になる必要はないでしょう。
インボス制度についてのよくある質問
インボイス制度についてよくある質問に回答しました。
- インボイス制度の導入目的は何ですか?
- インボイス制度の導入目的は、消費税を正確に把握し納税の不正防止が主な目的です。
令和元年10月より消費税の軽減税率が導入されましたが、仕入税額の中に8%のものと10%のものが混在へと変わりました。このため、正しい消費税の納税額を把握する目的で、商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存することになりました。
- インボイス制度の問題点は何かありますか?
- インボイス発行事業者に登録する必要があり、登録番号を記載しないと適格請求書として認められない問題点があがります。
また、適格請求書の交付義務、返還インボイスや修正インボイスの交付義務、写しの保存義務などが発生し、事務負担が増える可能性もあるでしょう。
複雑なインボス制度についてインボイス発行事業者になるべきかどうかお悩みの方は、専門家による正しい知識をもとに解決に導いてもらうと安心です。
まとめ
インボイス制度のおおまかな内容を解説するとともに、売り手側と買い手側それぞれの場合に分けて、インボイス制度によって起こり得る変化について見てきました。
インボイス制度は内容も複雑で理解しにくいものです。また、免税事業者のままでいるべきなのか、適格請求書発行事業者になるべきなのかは簡単に判断できるものではありません。それぞれの状態にメリットとデメリットがあるからです。
自分だけではうまく判断するのが難しいとお考えになったときには、ぜひ弊社・サン共同税理士法人にご相談ください。積み重ねてきた豊富なノウハウにもとづき、お客様の現状においてどのような選択が最適であるかを丁寧にアドバイスし、必要なサポートを提供いたします。

税理士登録:2007年
税理士登録番号:107222
2006年 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)入社
2016年 sankyodo税理士法人に代表社員として参画
今日、経営環境は不断に変化し、それに対応して税制・会計基準も複雑化してきております。そのため、そうした動向を絶えずキャッチアップし続け、お客様に常に最高水準のサービスを提供するスペシャリストであり続けたいと願いそれを実行し続けていることを自負しております。上場企業をはじめとしたクライアント様の要求水準は高くなる一方ですが、圧倒的に信頼されるスペシャリストとして、深い知的研鑽を積み、専門的な実務経験に裏打ちされた顧客本位のサービスをご提供し続けることを信念に、邁進して参りたいと思っております。



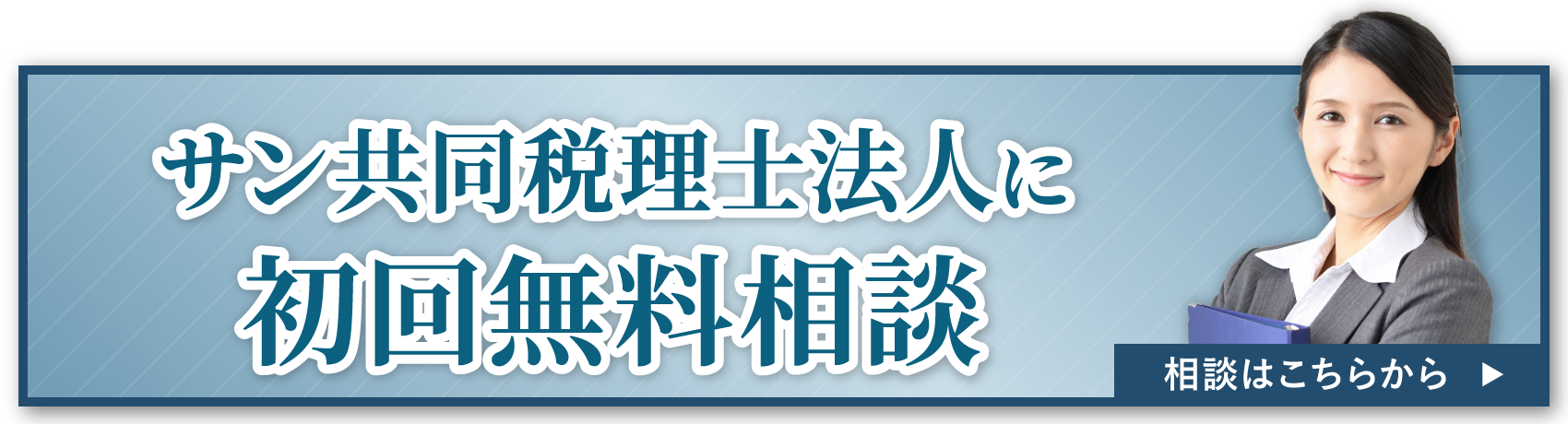




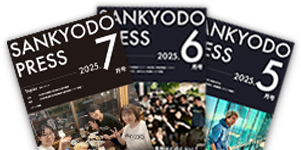
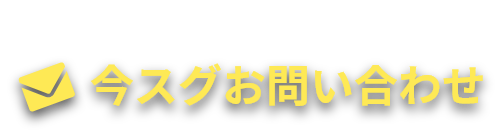

 CLOSE
CLOSE