2023年10月から、消費税の納税に関わる新たな制度である適格請求書保存方式(インボイス制度)がスタートします。
すべての事業者に多かれ少なかれ影響を及ぼすので、しっかりと理解しておくべきなのですが、内容が複雑であるためいまだに把握しきれていない方も多いのではないでしょうか。
適格請求書保存方式の核となる要素は、インボイス、すなわち適格請求書です。インボイスを活用するためには、適切な方法で保存する必要があります。
ここには電子帳簿保存法なども関わってくるため、幅広く学んでおかなければいけません。
この記事では、適格請求書に関するさまざまなルールの紹介を中心に、制度の詳細をわかりやすく解説します。
2023年10月から導入されたインボイス制度ですが、どのように対応したらよいのかがわからない方も多いのではないでしょうか?
サン共同ではお客様への対応事例を元に作成したインボイス制度に関する資料を無料配布しております。
個人事業主の方・法人の方どちらにも対応しておりますので、ご興味のある方はこちらからダウンロードください。⇒インボイス制度まるわかりBookの無料ダウンロードはこちら
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
目次
適格請求書保存方式(インボイス制度)とは?
インボイス制度は、すべてを日本語で表現すると「適格請求書保存方式」となります。
両者は同じものを指しているので、同じ知識で捉えて問題ありません。
適格請求書保存方式に関する基本的な知識を、ここでは以下の4つに分けて解説します。
- 仕入税額控除に適格請求書が必須となる
- 適格請求書の国税庁フォーマット
- 電子インボイスの発行も可能
- 適格請求書の消費税の端数処理
細かい論点もありますが、しっかり読んで把握しておきましょう。
仕入税額控除に適格請求書が必須となる
インボイス制度が始まることによる最大の変化は、仕入税額控除を適用するために適格請求書(インボイス)の保存が必須となることです。
仕入税額控除とは、売上に含まれる消費税を納税するときに、仕入れ費用に含まれていた消費税分を控除できる仕組みです。
たとえば仕入先から33,000円(うち消費税3,000円)で仕入れたものを44,000円(うち消費税4,000円)で販売した場合、仕入税額控除は適用すれば、4,000円から3,000円を引いた1,000円のみを消費税として納税すればOKになります。
このとき控除された3,000円は、仕入先が売上に含まれる消費税として支払っています。
つまり仕入税額控除は、国による消費税の二重取りを回避するための制度であるといえるでしょう。
インボイス制度の開始後は、仕入税額控除をするために仕入先からインボイスを発行してもらい、それを適切な手段で保管する必要があります。
適格請求書の国税庁フォーマット
適格請求書(インボイス)は、好きなように書いていいわけではありません。規定にしたがって作成する必要があります。
国税庁のサイトには、適格請求書の具体的な書き方が公開されているので、取引先に発行するときには以下を参考にすることをおすすめします。
適格請求書に必ず記載しなければならないのは、以下の2点です。
- 適格請求書発行事業者としての登録番号
- 消費税の内訳(8%と10%を区分けする)
これらを書いた適格請求書には効力がないので、注意しましょう。
電子インボイスの発行も可能
適格請求書は、電子データとしても発行できます。必ずしもプリントアウトして紙の形式で取引先に渡さなければいけないわけではありません。
電子データの形で発行された適格請求書は、電子データとして保存することが義務付けられています。
これは電子帳簿保存法の改正に基づく新たなルールです。
適格請求書の消費税の端数処理
適格請求書の消費税額は、請求書ごと・税率ごとに1回の端数処理をおこないます。
適格請求書には消費税の内訳が8%と10%に区分けされて記載されているはずです。
そのそれぞれに対して、1回ごとに端数処理をする必要があります。ただし、個々の商品ごとに端数処理をすることは許されていません。
端数処理の方法は、「1円未満の端数を切り上げる」「1円未満の端数を切り捨てる」「四捨五入する」など、自由に決められます。
適格請求書が発行できるのは適格請求書発行事業者のみ
適格請求書は、誰でも発行できるものではありません。適格請求書発行事業者として国に登録した事業者のみが発行できます。
適格請求書の必須記載事項として、適格請求書発行事業者の登録番号があります。
登録をしなければこの番号を発行してもらうことはできません。
必然的に、適格請求書発行事業者のみが適格請求書を発行できることになります。
適格請求書の登録番号
前項で解説した適格請求書の登録番号は、アルファベットのTから始まり、13桁の数字が続く構成になっています。
法人の場合、Tのあとに続く数字は法人番号です。
それ以外の個人事業者などの場合は、13桁の数字として「法人番号と重複しない事業者ごとの番号」が用いられます。このときマイナンバーは用いないことに注意してください。
参考:登録番号とは|国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト
適格請求書の登録番号発行方法
適格請求書の登録番号を発行してもらうには、以下の手順を踏まえる必要があります。
- 登録申請書を作成する
- 管轄のインボイス登録センターに提出する
- 登録番号を取得したら取引先へ通知する
まずは国税庁が公開している「適格請求書発行事業者の登録申請書」に必要事項を記載します。
作成した申請書は、管轄区域に用意されているインボイス登録センターに提出します。
窓口に提出・郵送・e-Taxのいずれの方法でも申請可能です。
登録番号が発行されるまでの期間が早いのはe-Taxによる申請となります。
申請書は税務署によって審査され、問題ないと判断されれば登録番号が発行されます。
発行された登録番号は、取引先に通知しておきましょう。
後に適格請求書を発行した際、記載された番号が間違っていないかチェックするといった目的で使われます。
適格簡易請求書とは
適格簡易請求書とは、不特定かつ多数の人々に対して商品やサービスを提供する業種が発行できる、簡易的な適格請求書のことです。
ここでは以下の2点に分けて解説します。
- 適格簡易請求書が発行できる事業者
- 適格簡易請求書の記載内容
順番に見ていきましょう。
適格簡易請求書が発行できる事業者
前項で軽く触れた通り、適格簡易請求書を発行できる事業者は「不特定かつ多数の人々に対して商品やサービスを提供する業種」に限られています。
具体的には以下のような業種です。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真鏡
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業
- その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数のものに資産の譲渡等を行う事業
上記の業種は、実態にかかわらず適格簡易請求書を発行できます。
たとえば小売業者が必ずしも不特定多数を相手に商品を提供しているとは限りませんが、どのような業態であるにせよ小売業者である時点で適格簡易請求書を交付できると定められています。
参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁
適格簡易請求書の記載内容
適格簡易請求書に記載すべき内容としては、以下のものが定められています。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 税率ごとに区分した消費税額など、または適用税率
これらがきちんと記載されていれば、請求書だけでなくレシートや領収書も適格簡易請求書として発行できると定められています。
適格返還請求書とは
適格請求書発行事業者が、課税事業者に対して返品や値引きなど「売上に係る対価の返還」を求める場合、適格返還請求書の交付義務が課せられています。
きちんとした手続きを踏まないと、後の税務処理において混乱してしまうからです。
ただし以下の条件に当てはまる場合には、適格返還請求書の交付義務が免除されます。
- 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
- 出荷者などが卸売市場においておこなう生鮮食料品等の販売
- 生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
- 3万円未満の自動販売機および自動サービス機により行われる商品の販売等
- 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁
帳簿のみで仕入税額控除が認められる場合
通常であれば、仕入税額控除を適用するためには適格請求書が必須となります。
しかし一定の事項を記載した帳簿の保存のみで、仕入税額控除が適用されるケースもあります。代表例は以下のようなものです。
- 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
- 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
- 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
- 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入等
適格請求書保存方式の一定期間の経過措置
適格請求書保存方式は2023年10月から開始されますが、開始後すぐに完全な状態で適用されるわけではありません。
一定期間の経過措置が設けられています。具体的には以下の3つです。
- 免税事業者からの仕入れの経過措置
- 少額取引の適格請求書不要
- 課税事業者になった際の納税額の支援措置
順番に見ていきましょう。
免税事業者からの仕入れの経過措置
適格請求書保存方式においては、適格請求書発行事業者から適格請求書(インボイス)を発行してもらわない限り、仕入税額控除を適用することはできません。
しかし制度の導入からしばらくのあいだは、免税事業者からの仕入れであっても消費税の一部が仕入税額控除の対象となります。
最初の3年間(2026年9月まで)は、課税仕入れの80%を控除できます。次の3年間(2029年9月まで)は、同じく50%を控除可能です。
少額取引の適格請求書不要
2029年9月までは、1万円未満の課税仕入れについて、適格請求書を発行してもらわなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能です。
この措置の対象となるのは、基準期間(2年前)の課税売上が1億円以下であるか、または1年前の上半期の課税売上が5,000円以下である事業者です。
課税事業者になった際の2割特例
小規模事業者に対して、納税額の支援措置も用意されています。その代表的なものが「2割特例」です。
2割特例とは、消費税の納税額を計算する際に仕入税額控除を「預かり消費税×80%」で計算すれば良いという特例制度です。
計算の結果として納税額が消費税全体の2割程度になるため、2割特例と呼ばれています。
2割特例が導入された背景としては、個人事業主を中心としてインボイス登録があまり進んでいないことが挙げられます。
個人事業主の多くは免税事業者であり、インボイス登録をするためには課税事業者に変わらなければいけません。
そこで生じる消費税の負担に抵抗感を持つ人が多いと見られています。
そこで納税の負担と会計処理の簡略化の両方を満たす措置として、2割特例が考え出されました。
上記のような背景から、2割特例の対象となるのは課税売上高が1,000万円以下の免税事業者のみとなっています。
【売り手側】適格請求書保存方式が免税事業者に与える影響
適格請求書保存方式は、取引における売り手にも買い手にも影響を与えます。
ここではまず、売り手側に与える影響を、適格請求書発行事業者になった場合と、免税事業者のままでいた場合の2つに分けて解説します。
適格請求書発行事業者(課税事業者)になった場合
売り手が適格請求書発行事業者になった場合受ける影響としては、以下の3つが挙げられます。
- 消費税の納税が必要になる
- 請求書のフォーマットを変更する必要がある
- 税務処理が増える
免税事業者は消費税を納税する必要はありませんが、適格請求書発行事業者は課税事業者であるため、売上に含まれる消費税を国に納めなければいけません。
次に、適格請求書には必ず記載しなければならない項目があるため、請求書のフォーマットを変更する必要に迫られます。
そして適格請求書に消費税の内訳を記載しなければならない関係上、税務処理の負担はどうしても増えてしまうことになります。
免税事業者のままでいた場合
適格請求書保存方式がスタートしたあとも売り手が免税事業者のままでいた場合には、以下のような影響が考えられます。
- 仕事が減る可能性がある
- 値下げを求められる可能性がある
適格請求書保存方式が導入されたあとは、免税事業者を相手に支払った額に関して、仕入税額控除を適用できなくなります。
つまり免税事業者を相手におこなった取引では、2023年10月以降、消費税の節税ができません。
このことから、免税事業者は取引先を失ってしまうリスクがあります。
また同様の理由から、仕入額の値下げを求められる可能性もあるでしょう。
値下げの要求に法的な強制力はありませんが、立場が弱いのでしたがうしかない個人事業主やフリーランスは多いと考えられます。
【買い手側】適格請求書保存方式が課税事業者に与える影響
買い手側が課税事業者であった場合、適格請求書保存方式が与える影響としては以下の3つが挙げられます。
- 免税事業者から仕入れると仕入税額控除ができない
- 免税事業者への対応を決めなければならない
- 適格請求書の保存方法を決めなければならない
適格請求書保存方式がスタートしたあとは、免税事業者からものを仕入れた場合に仕入税額控除を適用できなくなります。
これは純粋に利益の低下につながります。
上記の現象への対策として、免税事業者である取引先と今後どう付き合うか、対応を決めなければいけません。
免税事業者との取引を切って、新たに適格請求書発行事業者と取引を始めるといった意思決定が必要になります。
まだ適格請求書は電子データの場合もあるので、保存方法をあらかじめ決めておかないと混乱を招きかねません。
適格請求書保存方式に関するよくある質問
適格請求書保存方式に関する、よくある質問に回答していきます。
- 適格請求書保存方式(インボイス制度)をわかりやすく教えてください
- 適格請求書保存方式とは、消費税の仕入税額控除を受けるために、仕入先から適格請求書(インボイス)を発行してもらうことを義務付ける新たな制度です。
適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
適格請求書発行事業者は課税事業者であるため、免税事業者が新たに登録する場合には、それ以降消費税の納税が新たに課せられることになります。
- 適格請求書の国税庁が出しているフォーマットはありますか?
- 国税庁は適格請求書のフォーマットについて、公式サイトで公開しています。
そのフォーマットにしたがって適格請求書を作成すれば問題ありません。以下のリンク先を参照してください。
- 適格簡易請求書とは何ですか?
- 適格簡易請求書とは、不特定かつ多数の人々に対して商品やサービスを提供する業種が発行できる、簡易的な適格請求書のことです。
このような業種においては正規の条件を満たす適格請求書を毎回作成するのが困難であるため、特例として認められています。
具体的には、小売業や質屋業などが該当します。
- 適格返還請求書とはなんですか?
- 適格返還請求書とは、課税事業者に対して返品や値引きなど「売上に係る対価の返還」を求める場合に発行しなければならない請求書のことです。
ただし以下のような条件に当てはまる場合には、適格返還請求書の交付義務が免除されます。
- 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
- 出荷者などが卸売市場においておこなう生鮮食料品等の販売
まとめ
適格請求書等保存方式に関して、一通りのことを詳細に解説しました。
適格請求書等保存方式は内容が複雑であるため、事業者にとって大切な制度であるにもかかわらず、深く理解するのは簡単ではありません。
しかし利益を大きく左右する制度であり、事業者にとって避けて通ることのできないものです。
とくに判断が難しいのは、適格請求書発行事業者になるべきか否か、でしょう。
どのように事業をおこなうのが適切であるかお悩みの方は、ぜひ弊社・サン共同税理士法人にお問い合わせください。
サン共同税理士法人は、適格請求書等保存方式に関するご相談を、これまでに数多く承ってまいりました。その豊富なノウハウにもとづき、お客様1人1人のご事情にあわせた
最適なアドバイスとサポートをご提供する用意があります。
煩雑な作業はその道のプロにお任せいただき、ぜひお客様が本来全力を尽くすべき事業に専念していただきたく存じます。

税理士登録:2013年
税理士登録番号:123285
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にsankyodo税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。



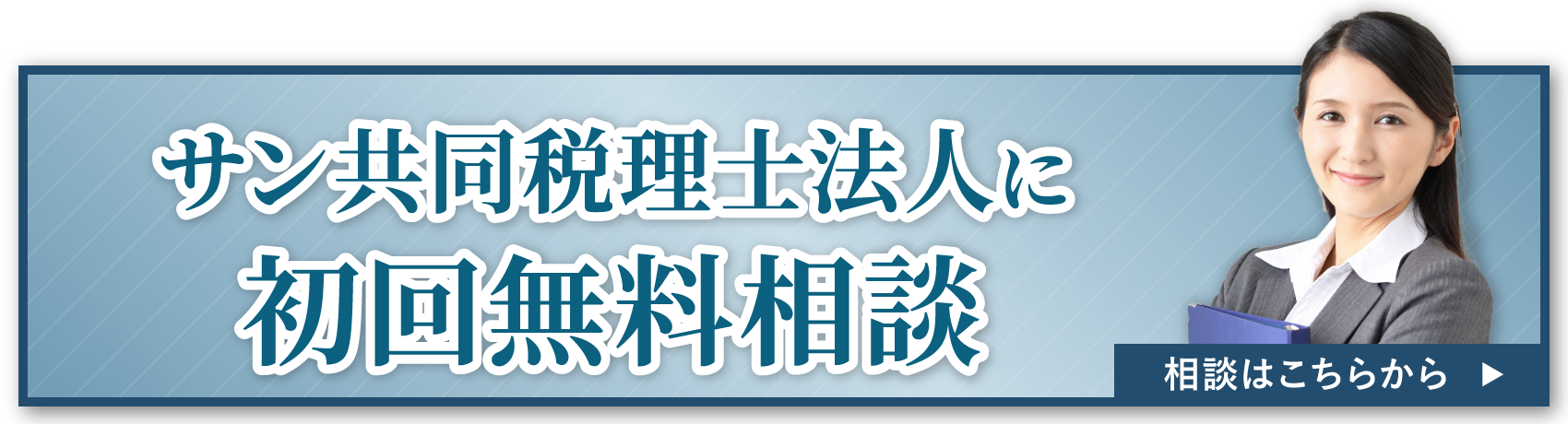




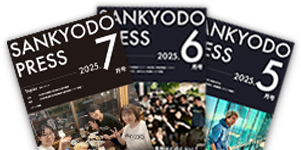
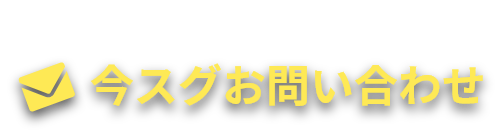

 CLOSE
CLOSE